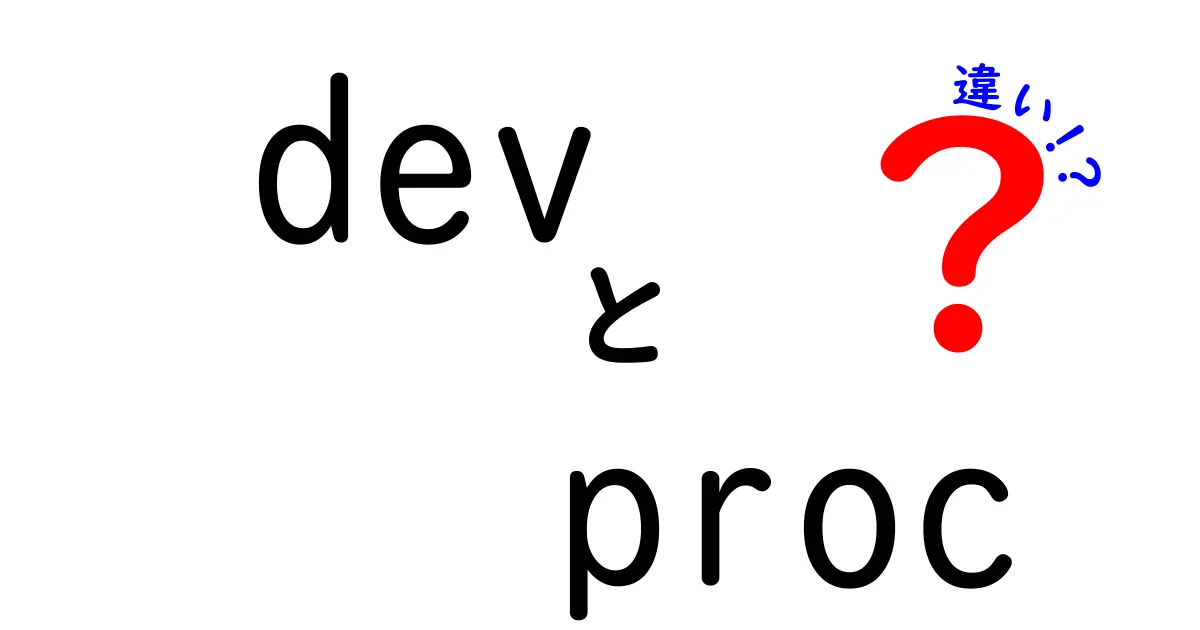

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
devとprocの違いを分かりやすく解説
この節では dev と proc の基本的な違いをやさしく説明します /dev はデバイスファイルを集めた場所であり 実体のデバイスをソフトウェアに結ぶ窓口です ここにはハードディスクや USB端子 端末デバイスなどのファイル名が並び それぞれのファイルを読むことでデバイスの状態や操作を行います
それに対して /proc は仮想ファイルシステムと呼ばれ カーネルが内部の情報をファイルの形で公開している場所です CPU 情報 メモリ状況 実行中のプロセスなどが読み取り専用のファイルとして現れます
このふたつの性質の違いを押さえると システムの挙動理解が進み トラブル時の原因追跡にも役立ちます ポイントとしては /dev が現実のデバイスを表すノードであり /proc がカーネルの現在状態を映す窓だという点です
実務的にはこの二つを使い分ける感覚が大切で ほかのファイルと同じように扱える場面もあれば 取り扱いに注意が必要な場面もあります この理解は Linux の基礎力を底上げします
実務での使い分けと注意点
この節では 実務的な使い方と注意点を詳しく説明します /proc の中身を読むことで システムの負荷 状態 環境情報をリアルタイムで把握できます 例えば cpuinfo meminfo の情報を参照する例として cat の後にファイル名を入力するだけで 現在の値を確認できます これを活用すれば 応答の遅さの原因や 負荷のピーク時間帯を特定する手助けになります 一方 /dev は デバイスを操作するための道具箱のようなものです 実際のデバイスを操作するには権限が必要ですし デバイスノードを間違って操作すると危険が生じます 代表的な使い方としては デバイスファイルを読み取ることで情報を得る あるいは書き込みを伴う操作を行う場合がある ここでの注意は 書き込み権限がある場合も 取り扱い先の安全性を確保することです
この二つを使い分けるコツは 現在の情報を必要とする時は /proc から読む 動的なデバイス操作は /dev を使う という基本方針です ただし /proc の値はすぐ変わる性質があるため 連続して情報を取りたいときはスクリプトを組んで定期的に取得します また /dev については新しいデバイスが追加されるたびにノードが現れることがあるため udev や systemd の管理を理解しておくと便利です
放課後の部室で友だちと最新のパソコンをいじりながら dev と proc の話をしていた 私は最初 ただの名前の違いだと思っていたが 友だちは実務での使い分けを例にしてくれた まず dev は現実の機器を表す窓 ここではディスクや端末などのデバイスノードが並ぶ これを使ってデバイスの情報を引き出したり 実際に操作することがある 次に proc はカーネルの状態を生のまま見せる窓だ と教えてくれ 星の数ほどのファイル cpuinfo meminfo などを読むと システムの状態が頭の中でつながる そんな気がした それから私たちは自分のノートに どちらをどんな場面で使うべきか メモを取り 似たような状況を想定して簡単なスクリプトを書いてみた こうした小さな発見が IT の入り口を開くきっかけになると感じた





















