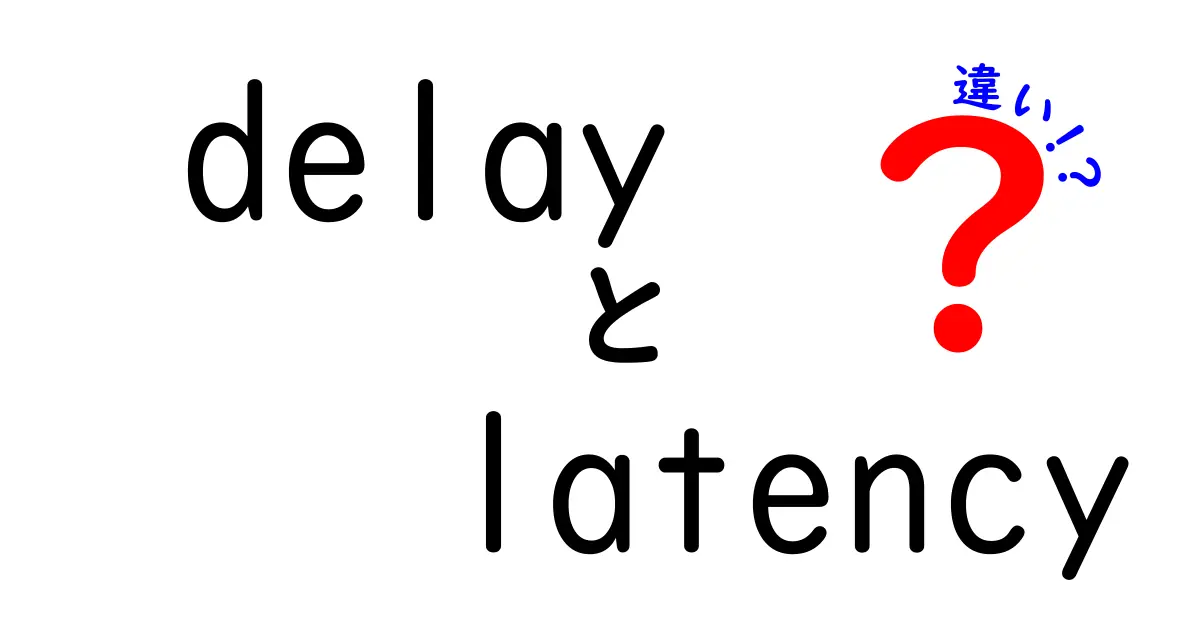

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
delay latency 違いを徹底解説!ネットワーク用語の混乱をスッキリ理解
ここでは「遅延」と「レイテンシ」という言葉の違いを、身近な例とともに丁寧に説明します。基本的な意味の違いから、実務での使い分け、ゲームや動画配信での影響、そして測定方法まで順番に見ていきます。
最初に結論を言うと、遅延」は時間の経過そのものを指す日常語、レイテンシ」は通信回線を横断する信号の「待ち時間」が主な意味です。ここを押さえるだけで用語の混乱はかなり減ります。
また、現場では「遅延」と「レイテンシ」を同義で使う場面もありますが、厳密さを求められる場面では区別が重要です。
以下では、誰にとっても分かりやすい順序で詳しく解説します。
1章:基本の意味を分けて考える
まず大切なのは、言葉の使われ方を「人が感じる時間の長さ」か「通信の遅れ」かで分けることです。遅延は私たちが日常生活で使う時間の感覚を指します。たとえば動画を再生しているときの「止まらずにつながってくれるまでの時間」や、スマホの反応が遅いと感じる瞬間などがこれにあたります。
一方でレイテンシは主に「データがある場所から別の場所へ届くまでの待ち時間」を意味します。回線の距離、経路の混み具合、機器の処理能力などが影響します。ここを混同すると、どこが原因か分からなくなりがちです。実務ではこの差を意識して、通信の品質改善を図ります。
この違いを意識することで、トラブルの原因追及や改善策の検討が格段に早くなります。
2章:実際の場面での使い分けと注意点
実際の現場で「遅延」と「レイテンシ」を使い分ける場面は多いです。たとえばオンラインゲームでは、プレイヤーが入力してからゲーム内に反映されるまでの時間を「遅延」と呼ぶこともあれば、「レイテンシ」が原因と表現することもあります。これらの語を正しく使い分けるのは、技術的な原因を特定するうえでとても重要です。
家庭用インターネットでは動画配信の再生が止まりやすいとき、「遅延」が大きいのか、それとも回線の混雑による「レイテンシ」が原因なのかを区別します。
測定方法としては、まず「ピング(ping)」で往復時間を測ります。結果が100ミリ秒を超えると、体感での遅さを感じやすくなります。ここでの基準は用途によって変わります。ゲームなら30〜50msが望ましいとされ、動画視聴なら100ms程度が許容範囲といわれます。
さらに、経路の混雑状況やルータの処理遅延を見極めるためにはpingだけでなくtracerouteや jitter などの指標を組み合わせて診断します。
下の表は、遅延とレイテンシの違いを簡潔に整理したものです。
まとめとして、日常的な「待ち時間の感覚」は遅延の領域、通信の品質を扱う指標としての待ち時間はレイテンシの領域と考えると、混乱が減ります。
実務では、原因の特定と対策をセットで考えることが大切です。例えば、端末の性能を改善する、経路の最適化を行う、QoS(Quality of Service)を設定するなどの対策が挙げられます。
このような理解を持つことで、友人や同僚と用語を共有するときにも説明がしやすくなります。
latencyという言葉を深掘りした雑談風の小ネタです。友達とカフェで『 latency って何だろう?』と話し始めたとき、私はこう説明します。距離が遠いほど遅く感じるという直感も、実は通信機器の処理や経路の混雑という現実の要素が複雑に絡んでいます。光回線の速さそのものより、端末の処理能力やルータの混雑具合、経路の混雑頻度が大きく影響する場面が多いのです。だから latency は、道を歩く人の混み具合に例えると伝わりやすい。道が混んでいると進むのが遅くなるように、データも「混雑した経路」を通ると待ち時間が長くなる、という説明が私のお気に入りです。これで友人にも「待ち時間の理由」がイメージしやすくなるはずです。





















