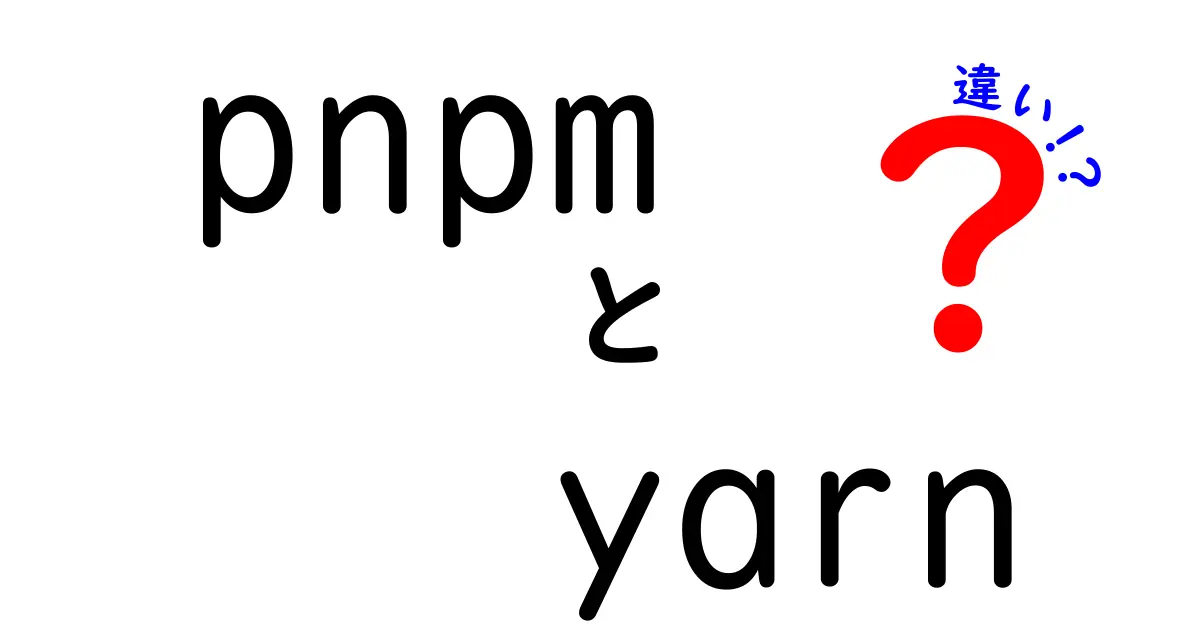

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
pnpmとyarnの違いを理解するための基礎と全体像
このセクションではまず pnpm と yarn がどんなものかを整理します。どちらも Node.js のパッケージ管理ツールとして npm の代替として広く使われてきました。重要な点は「パッケージをどう整理し、どのように再現性を保つか」という設計思想の違いです。
pnpm は「内容を参照するリンクの仕組み」と「止まらないキャッシュ戦略」で、同じパッケージを複数の場所で重複させずに使う設計をとっています。これに対して yarn は従来の npm に比べて高速化と安定性を重視しつつ、ワークスペース機能やキャッシュ、プラグイン的な拡張を積極的に取り入れてきました。
この違いを理解することで、プロジェクトのサイズが大きくなるほどどちらを選ぶべきか、どう設定すれば開発体験がよくなるかの判断材料が見えてきます。
結論の要点としては、pnpm はディスク使用量と再現性の面で強く、yarn は使い勝手とエコシステムの広さで有利という点です。これを踏まえて、次のセクションで実務での使い分けを詳しく見ていきます。
まず覚えておくべき用語を整理します。パッケージマネージャーは依存関係の解決とロックファイルの生成を担いますが、同じパッケージでも内部のディレクトリ構造やリンクの仕組みが異なると、実行速度やディスク容量、CIでの再現性が変わってきます。pnpm はノード_modules の扱いを「ハードリンクとパス参照」で実現するため、同じ依存が複数のプロジェクトに跨って存在してもファイルを重複させません。一方 yarn はキャッシュとワークスペースの設計で、パッケージの探索・解決を高速化します。これらの違いは実際の開発現場でのインストール時間・ディスク使用量・継続的インテグレーションの挙動に影響します。
次のポイントを押さえておくと、チームでの選択がスムーズになります。まず ディスクの使用量。pnpm は共通のキャッシュを活用し、重複を避ける設計なので大規模プロジェクトではディスク容量を節約できます。yarn は過去の実装でのキャッシュが強力で、ネットワークを抑えつつ素早い再インストールを可能にしますが、pnpm のような厳密な重複排除の効果はデフォルトでは見られません。次に 再現性。ロックファイルの扱い方やワークスペースの動作が重要です。pnpm は依存関係のリンクを厳密に管理しており、同じバージョン・同じ解決結果を再現しやすい設計です。yarn も再現性は高いですが、設定次第で少し異なる挙動になることがあります。最後に 実務の使い分け。小規模プロジェクトや個人開発ならどちらを使っても問題ありませんが、CI の速度とディスク容量が重要な大規模チームでは pnpm の利点が顕著になるケースが多いです。
現場の実例としての結論としては、ディスク容量を抑えつつ複数リポジトリを横断する開発体験を重視する場合は pnpm が有利です。ワークスペースやプラグインの豊富さを活かして一つのリポジトリ内で複数のパッケージを管理する場合は yarn のエコシステムと柔軟性が役立ちます。どちらを選ぶにしても、ロックファイルの管理方法とCIの再現性を最初に共通化しておくことが成功の鍵です。
実務での使い分けとパフォーマンス比較
このセクションでは実務での使い分け方と、パフォーマンスの観点からの比較を詳しく見ていきます。pnpm はリンクとキャッシュの仕組みでディスク使用量を抑えることに長けています。複数のリポジトリやモノリポ構成のプロジェクトで、同じ依存パッケージが何度もダウンロードされる状況を避けるのが得意です。また、pnpm は node_modules 配下のディレクトリ構造を独自に最適化しており、エンジニアが直接ファイルアクセスを意識する必要を減らします。実務では、CI 上での数十回のインストールを短縮できたり、ローカルの開発環境での起動時間を短く抑えられるケースが多く報告されています。
yarn は一方で長年の安定性と広いエコシステムを活かせます。特に Yarn v2/v3 以降は Plug'n'Play の選択肢やワークスペースの改善、キャッシュの高度な活用といった新機能が追加され、複数パッケージの連携やモノリポ構成での開発体験が向上しています。
以下のポイントを整理して使い分けると、プロジェクトの性質に合わせた最適解を選べます。
- サイズと構成: 大規模プロジェクトで依存が多い場合は pnpm の重複排除が効果的。
- CI再現性: ロックファイルの扱いとインストール安定性を重視する。
- エコシステムと拡張性: Yarn のワークスペースとプラグインの活用が有利な場面を選ぶ。
- オペレーションの安定性: チームの運用ルールに従って、同じ方法で統一する。
次に、簡易な比較表を用いて両者の違いを視覚的に整理します。表は実務で判断する際の分かりやすい指標として使えます。
実務での選択は、プロジェクトの性質とチームの開発フローに大きく影響されます。安全側に倒したい場合は、まず同じツールで一貫性を保つことが大切です。急なリポジトリ移行や新機能の追加が発生したときには、環境差が原因で問題が発生することもあるため、導入時にはCIのビルドログを丁寧に確認しましょう。総じて、pnpm はディスク容量と再現性を重視する現場に適し、yarn はパフォーマンスと拡張性を活かしたい場面で有利です。あなたのプロジェクトに合った選択を見つけてください。
ねえ、pnpmとyarnの違いって結局何なの? 公式のドキュメントを読んでも難しく感じることってあるよね。私はある日、同じコードベースを両方のツールで試してみたんだ。pnpmはお菓子の箱を開けるとき、中身が他の箱と重ならないようにテープで結んでおく感じに近い。つまり同じ依存が複数のリポジトリにまたがっていても、重複してダウンロードしたり、ディスク上に無駄なファイルを増やさない。対して yarn は、箱を積み上げていくやり方がとても直感的で、ワークスペース機能を使えば複数のパッケージを一本の大きな家として管理できる。もちろんどちらも良い点がある。結局のところ、開発チームのスタイルやCI環境、プロジェクトの規模によって向き不向きが変わるんだ。私が実際に感じたのは、“使い分けの考え方”が最も大事だということ。新しい依存が増えたときに、誰が何をダウンロードするのか、どのくらいの時間でビルドが終わるのか、そしてどれだけ安定して再現できるか――これらを一貫して見据えると、 pnpm か yarn かという選択肢は自然と見えてくる。





















