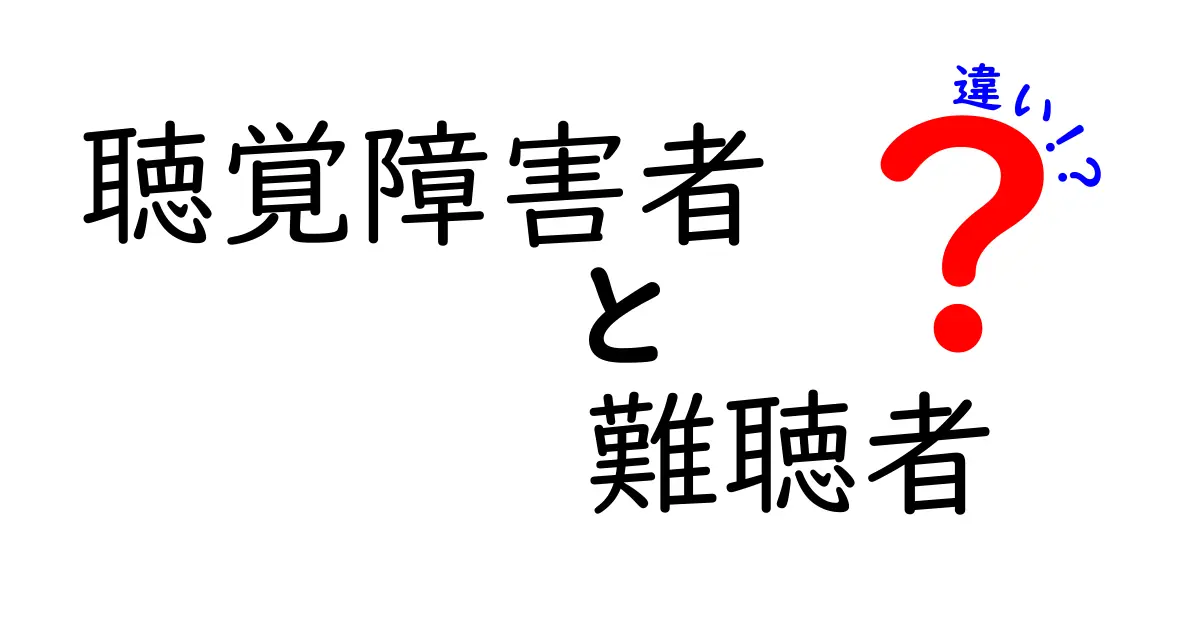

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
聴覚障害者と難聴者の違いを理解するための前提知識
まず最初に知っておきたいのは、言葉の意味は時代や社会の状況とともに変わるということです。聴覚に関する状況を表す言葉は長い歴史の中で生まれ、医療用語や教育現場の実務用語として使われ方が変化してきました。
このセクションでは、聴覚障害者と難聴者という二つの語の根本的な違いを、起源・定義・使われ方の観点から整理します。日常生活での誤解を避け、適切に伝えるための基本を身につけましょう。
この話は「人を傷つけず、正確に伝える」ための配慮が前提になります。
なお、障害の出方は人それぞれ異なるため、個人の尊厳と自己決定を尊重する姿勢が大切です。
まず押さえるべき点は、二つの語が必ずしも同じ意味を持つわけではないということです。
「聴覚障害者」は、聴覚に関する機能が何らかの形で長期的・恒久的に制限されている人を指すことが多い言い方です。対して「難聴者」は、聴力の低下がある人を指す日常語として使われることが多く、重さの感じ方(軽度/中等度/高度)が文脈で変わる場合があります。
この差は、医療・教育・行政の場で意味が少しずつ異なる使われ方につながります。
つまり、同じ人でも場面によって呼び方を変えることがあり、それが混乱の原因になることがあります。
使い分けのポイントは、相手が自分のことをどう表現してほしいかを尊重すること、または公式な場面で適切な用語を選ぶことです。
まずは話す相手の希望を確認し、次に状況に応じて適切な語を選ぶとよいでしょう。学校・病院・役所といった場面では、用語の正式さが求められることが多いです。
さらに、障害の有無を話題にする場合は、個人情報としての取り扱いにも注意してください。
このセクションの要点は、「言葉の選択は相手を尊重する行為である」という視点を忘れないことです。
定義の違いと用語の起源
次に、二つの語の定義の違いを歴史的な背景と現在の実務の視点から見ていきます。
「聴覚障害者」は、聴覚機能の障害を持つ人全般を指す総称として使われることが多く、医療・福祉・教育の現場で広く用いられます。障害者という言葉自体には社会的な包摂の意味と、支援を必要とする人を指す実務的な意味が混在しています。
一方「難聴者」は、聴力が低い人を日常語で指す言い方で、程度が軽い人から中等度・高度まで幅があります。
この語は、個々の聴力の程度を説明する場面で使われることが多く、個人の聴覚状態を端的に表す実務的な表現として機能します。
歴史的には、社会的認知や医療モデルが変化する中で、どちらの語が適切かの判断が変容してきました。
現代では、「聴覚障害者」は法的・制度的な文脈で頻繁に見られ、「難聴者」は日常会話や非公式な説明でみられるケースが多いという傾向があります。
この違いを理解することで、伝えたいニュアンスを誤りなく伝えられるようになります。
実際の場面での使い分けを例に挙げると、教育現場では「聴覚障害をもつ児童生徒」が公式文書で使われることが多く、医療機関や一般の対話では「難聴の人」や「難聴者」という表現が用いられることがあります。
ただし、地方自治体の案内パンフレットや学校の説明資料では、「聴覚障害者」という表現を避け、より中立的な表現を使う傾向が強まっています。
いずれにせよ、語の選択は“相手の尊厳を守る”という基本方針のもとで決めるべきです。
日常生活での使い分けと注意点
ここでは、家庭・学校・職場・公共の場での使い分けのコツと、避けるべき表現の例を紹介します。
第一に、相手が自分の diagnosis をどう呼ぶかを尋ねることが最も大切です。相手が自分の聴覚状態を「聴覚障害」として受け止めている場合には、それを尊重して「聴覚障害者」という表現を使うべきです。逆に、自分の聴覚状態を軽く捉えたい、日常的に話す場面では「難聴」と説明するのが適切なこともあります。
第二に、場面に応じた適切さを意識しましょう。公的な文書・案内・障害者支援の申請書類などでは、正式な用語の統一が推奨される場合が多いです。対して、学校の連絡ノートや友人同士の会話では、より分かりやすく温かい表現を選ぶことが多いです。
第三に、配慮の表現を加えることも大切です。たとえば「聴覚障害をお持ちですか」「難聴の程度はどのくらいですか」といった言い回しは、相手の気持ちを尊重しやすい傾向があります。
最後に、テクノロジーの進歩と社会の理解の進展により、補聴器・人工内耳・手話通訳といった支援が身近になってきました。
このような背景を踏まえ、私たちは言葉の力を正しく使い分け、相手の人間性を損なわないコミュニケーションを心がけるべきです。
社会的な意味と法的な区分
障害者権利の視点から見ると、用語選択は社会参加の機会に影響を与えうる重大な要素です。公的機関の文書や教育現場では、相手を尊重する言葉づかいが求められ、障害を理由に差別を生まないよう配慮されます。日本では「障害者差別解消法」などの法制度が整備され、適切な呼称の使用が促される場面が増えています。
一方、言葉の選択だけでなく、実際の支援やアクセスの機会が確保されることが最も重要です。補聴器の提供、手話通訳の配置、教育現場のアクセシビリティの改善など、社会全体の取り組みが進むほど、語の使い分けはより自然で意味のあるものになります。
この点を理解しておくと、日常の会話だけでなく、ニュースや行政の案内を読むときにも適切な判断ができるようになります。
表で学ぶ用語の対照
| 定義 | 説明 |
|---|---|
| 聴覚障害者 | 聴覚機能に障害を持つ人を指す総称。教育・福祉・医療の場で頻繁に使われ、法的・制度的文脈も含む。 |
| 難聴者 | 聴力の低下がある人を指す日常語。程度は軽度から高度まで幅広く、個人の状態を具体的に表現する場面で使われることが多い。 |
この表は用語の対照を簡潔に示したものです。実際には文脈に応じて語の選択が変わるため、相手の表現を尊重することが最も重要です。繰り返しますが、用途が変われば適切な言い換えを選ぶことが大切です。
要点まとめ:聴覚障害者は障害を含む総称、難聴者は聴力低下を指す日常語。状況と相手の希望を尊重して使い分けること、そして社会的支援の実践が重要です。
難聴者って言葉を友だちと話していたとき、ふと「難しそうな漢字みたいな響きだな」と思ったんだ。でも実際には、難聴者は聴こえの程度が人それぞれで、軽い人もいれば補聴器を使って生活する人もいる。語の選び方ひとつで相手の気持ちは変わるから、まずは相手がどう呼んでほしいかを尋ねることから始めよう。私たちが日常で使う言葉は、相手を安心させる優しい道具になり得る――そんな話を友だちと雑談していて、改めて実感しました。
前の記事: « 耳垢と鼓膜の違いを徹底解説!正しい耳ケアとよくある誤解を解く





















