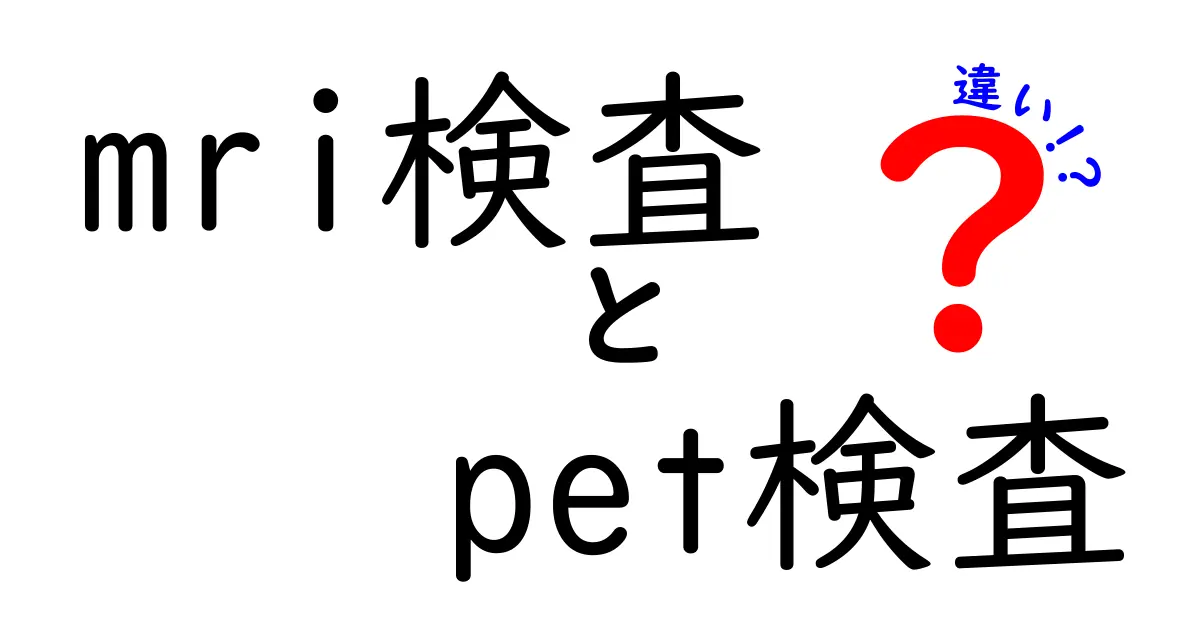

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
MRI検査とPET検査の違いを徹底解説|いつ使うべきかを中学生にもわかる図解付き
医療現場で使われる画像検査には、MRI検査とPET検査の2つがよく登場します。これらは同じ目的のように見えますが、撮れる情報の種類が異なるため、使い分けがとても大切です。
MRIは“形”や“組織の状態”を詳しく描く装置で、体の内部の構造を見るのに向いています。
一方、PETは“機能”や“代謝の動き”を映し出します。体の細胞がどれだけエネルギーを使っているか、どの部分が活発に働いているかを知ることができます。
この違いを知っておくと、病気の診断だけでなく、治療の計画(手術をするか、薬で治すのか、もう少し観察するのか)を立てるときにも役に立ちます。
次に、それぞれがどんな場面で選ばれるのか、検査のしくみを分かりやすく見ていきましょう。
なお、どちらの検査も痛みはほとんとんなく、体に大きな負担がかかるわけではありませんが、準備や注意点が少しずつ違います。
MRI検査の基本
MRI検査は、体を構成する水素原子の磁力と回転を利用して、体の断層像を作ります。磁石の強さは施設ごとに違い、1.5テスラや3テスラと呼ばれる機種が一般的です。被ばくはありませんが、磁場と高周波の電波を使うため、金属体内の磁性物質がある人は検査を受けられないことがあります。
また、体内にコントラスト剤を使う場合は、注射をして血流の動きを強調します。
検査中は沈黙の狭い筒の中で横になりますが、機械音が大きいので耳栓を使うことが多いです。検査時間は部位によりますが、頭部や脊髄なら15分から40分程度、四肢の場合はもう少しかかることがあります。
MRIは特に、筋肉の状態、靭帯の断裂、関節の形、脳の構造、腫瘍の形状など“見た目の特徴”をはっきりさせたいときに適しています。病変の形が滑らかかどうか、境界がくっきりしているかなど、画像の質で診断の難易度が変わる場面で強い味方です。
PET検査の基本
PET検査は、体の代謝活動をカラーで映し出す、機能志向の検査です。検査に使われる放射性物質は“トレーサー”と呼ばれ、ブドウ糖の類似物質であるFDGが最も一般的です。注射後、体の細胞がどれだけエネルギーを使っているかをカメラがとらえます。がん細胞は通常より多くブドウ糖を使うことが多いため、活発な部分が光って見えることが多いです。検査は数十分程度の待機の後、専用の機械で全身をスキャンします。通常、MRIより放射線の影響を受ける量があるため、妊娠中の方や授乳中の方には注意が必要です。検査前には絶食が求められることもあり、糖分の摂取を控える指示が出る場合があります。トレーサーは半減期が短く、検査後は日常生活に戻ることができます。PETは、がんの転移の有無、脳の機能異常、心臓の血流不足など、機能的な異常を広く探す能力に長けており、しばしばMRIと組み合わせて使われます。
実際の違いと使い分け
日常の診療現場では、まず何を知りたいかで検査を選びます。
もし“見える形”を詳しく知りたい、腫瘍の境界、組織の状態、損傷の程度などを評価したい場合はMRIが第一候補です。
一方で“体の機能”を知る必要がある場合、特にがんの活動度や脳の働きを見る場合にはPETが優先されることが多いです。
がんの診断では敷衍してPET-CTを使い、構造の情報と機能の情報を同時に得ることがあります。
また、手術計画を立てる際には、周囲の組織の関係をMRIで把握し、治療の反応を把握するためにPETを併用するケースもあります。検査の順序は医師の判断だけでなく、施設の設備、患者さんの体の状況、急ぎの診断かどうかにも左右されます。
表で比較
以下の表は、MRIとPETの代表的な違いを簡易的に整理したものです。実際の数字は施設ごとに異なることが多いので、医師と相談して確認してください。
小ネタ:PET検査は“糖の探偵”みたいなもの。授業で友だちに『体の中で糖がどう使われるかをリアルタイムに教えてくれるカメラがあるんだよ』と話すと、みんな目を輝かせました。検査中は静かで、体の中の小さな動きまで色をつけて映す。トレーサーが体内で短い時間だけ働くので、検査後はすぐに普段どおりの生活に戻れます。医療現場の雰囲気を感じると、科学は“動きと色”で世界を説明してくれるんだと実感します。





















