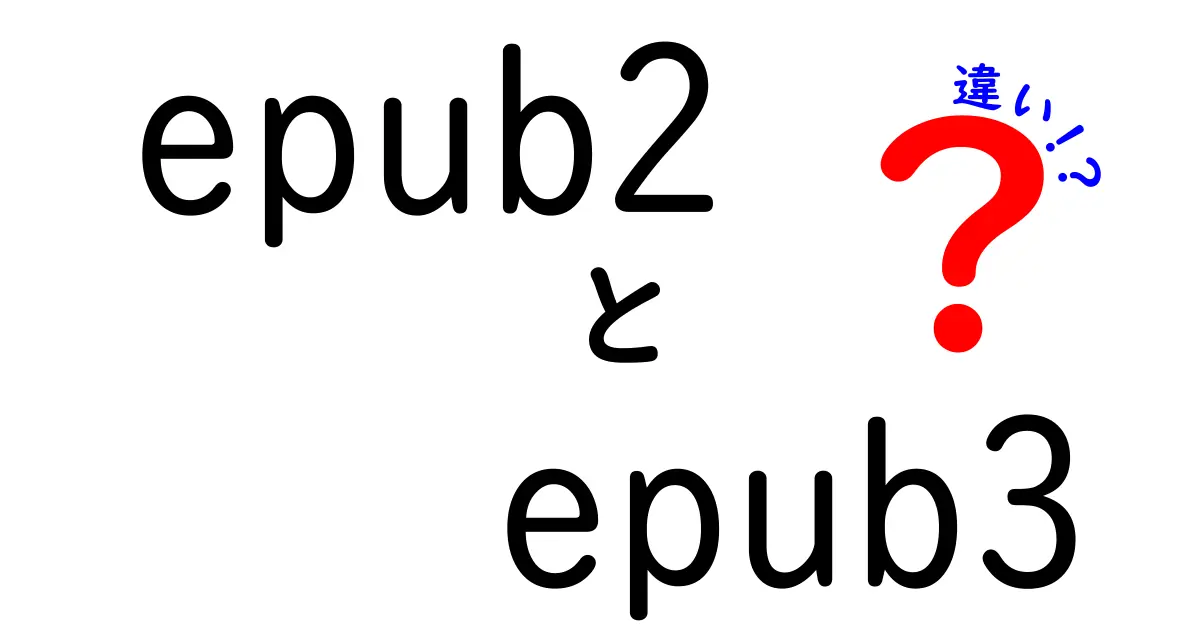

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
epub2とepub3の違いを理解するための基礎
epub2とepub3はどちらも電子書籍の標準形式ですが、作る側にも読む側にも違いを理解しておくと役立ちます。EPUBは国際標準で、複数のファイルをひとつの圧縮ファイルにまとめて配布しますが、規格ごとにサポートする機能が異なります。まず覚えておきたいのは「再流し可能な本文」と「固定レイアウトの有無」「マルチメディアの扱い」といった点です。EPUB2は昔から使われてきた安定した規格ですが、HTMLの最新機能はほとんど使えません。対してEPUB3はHTML5やCSS3を前提に作られており、読みやすさやアクセシビリティの改善が進んでいます。これらの違いを知ることで、配布するファイルの互換性や、制作コスト、読者の体験のバランスを判断しやすくなります。読者がどんなデバイスで読むのか、どんな機能を本に持たせたいのかを考えると、EPUB3を前提にする場面が増えるでしょう。しかし、古い端末や特定のリーダーでの互換性を重視する場合にはEPUB2の選択肢もまだ残ります。
このため、現在の制作現場では「対象デバイスの範囲」「必要な機能の有無」「制作コストと納期」を三つの軸として検討するのが基本となります。
このセクションでは、EPUBの基本概念と2つの規格の立ち位置を押さえ、どの場面でどちらを選ぶべきかの判断基準を作る土台を作ります。読者は「再流しの仕組み」「固定レイアウトの用途」「マルチメディアの扱い」という3つの観点を、実際の制作フローと結びつけて理解すると、後の具体的な比較がスムーズになります。
技術的な話だけでなく、実務での運用面やデバイスの現状も一緒に見ていくことで、迷いを減らすことができます。
EPUB2の特徴と制約
EPUB2は2007年頃に公開された古参の規格であり、OPFファイルというパッケージ定義とNCXと呼ばれる目次ファイルを組み合わせるのが基本形です。本文はXHTMLベースの文章とCSS2.1によるスタイリングで、再流し(本文が画面幅に合わせて折り返される表示)を実現します。
しかしこの設計には限界があり、以下の点が主な制約になります。アクセシビリティのサポートが現代の水準に比べて弱く、スクリーンリーダーや要約機能、見出し構造の自動検出といった機能を十分に活用しづらい場面が多いです。固定レイアウトの選択肢は少なく、デザインの自由度はHTML5/CSS3時代には追いついていません。フォントの埋め込みに対応していますが、デバイス側のフォントと組み合わせたときの表示がばらつきやすい点も注意点です。
さらに、検索機能やブックマーク、注釈の扱いなど、ユーザー体験を高めるための新しい機能はEPUB2では限られており、制作側は代替手段を自分で追加する必要がある場合が多いです。これらの制約は、長編のリサーチノートや図表の多い教材、動的な要素を多く含む作品には向かないことを意味します。
EPUB2の制作を続ける現場では、CSS2.1の範囲で試行錯誤してデザインを作るケースが多い一方で、アクセシビリティを全体設計の初期段階から考えるのは難しく、後回しにされがちです。つまり、互換性を確保する一方で、現代的な読み心地をどう両立させるかというジレンマを抱えやすいのです。
このジレンマを回避するには、まず対象の読者層とデバイスの組み合わせを把握し、必要最小限のCSSとXHTMLの構造で再現性を担保する方法を選ぶのが実務的です。
総じてEPUB2は「安定と互換性」を重視する現場には適していますが、最新の機能やアクセシビリティを最大限活用したい場合には不向きです。長期的にはEPUB3への移行を検討することが、将来的な保守性と機能拡張の点で有利になります。
この表を見れば、EPUB2とEPUB3の根本的な差が一目でわかります。
ただし“互換性と機能の両立”という現実的な問題は、プロジェクトごとに異なる予算や納期にも影響されるため、最終決定はケースバイケースで行うべきです。
EPUB3の特徴と新機能
EPUB3はHTML5とCSS3を前提に設計され、前提となる技術が現代のWebと近いものになったことで、表現力が大幅に向上しました。本文はXHTML5で構成され、CSS3を使って色・フォント・レイアウトを柔軟に調整できます。さらにJavaScriptの利用も可能になり、対話的な要素を本の中に取り入れることができます。読みやすさの点ではリフロー可能なテキスト、固定レイアウトの選択肢、リーディング順序の適切な管理、アクセシビリティの配慮(代替テキストや構造化タグの活用など)が強化されました。目次にはNAVドキュメントを使い、従来のNCXの代替として、より適切な構造を提供します。ぶ厚い図版を含む教材でも、固定レイアウトを選ぶことでページのデザイン性を保ちつつ、再流し可能な本文も提供できるようになりました。
また、EPUB3では語句のメタデータの取り扱いが改善され、検索性やヒット率が向上します。読み手の側では、フォント埋め込みの安定性が増し、文字のサイズ・間隔の微調整が容易になるため、視覚的な快適さが向上します。開発者側には、モジュール化されたCSSとセマンティックなHTML5構造を活用することで、後の更新作業が楽になるメリットがあります。総じてEPUB3は「表現力とユーザー体験の最適化」を目指して進化した規格と言えるでしょう。
ただし導入には学習コストが伴います。特に従来のEPUB2ベースのワークフローからの移行には、ファイルの構造やメタデータの新しい慣習、固定レイアウトの設定方法などを改めて整理する時間が必要です。企業や学校のような組織では、移行計画を段階的に実施し、段階的な検証と公開リリースを組み合わせるのが安全です。
EPUB3の実務適用には、まず対象デバイスの最新情報を把握し、互換性テストの枠組みを整えることが重要です。次に、メタデータの充実と画像・フォントの適切な扱いを計画に入れ、読者体験を高める工夫を追加します。こうした準備を経て、EPUB3は現代の読書環境に最も適した規格として機能します。
実務での選択とまとめ
現場での実務には、EPUB2とEPUB3のどちらを選ぶべきかという判断がつきものです。最適な選択は「対象読者のデバイス環境」と「必要な機能の組み合わせ」に左右されます。もし、古い電子書籍リーダーや特定の端末での互換性を最優先する場合はEPUB2を検討します。しかし現代の読書体験を重視するならEPUB3を推奨します。
EPUB3を選ぶと、HTML5やCSS3の機能を活かした美しいデザイン、セマンティックな見出し構造、検索性の高い書誌情報、そしてアクセシビリティの強化が期待できます。制作時にはメタデータの充実、適切な語集・用語の統一、画像の圧縮と文字コードの統一、フォント埋め込みの適切な管理など、細かい点を丁寧に整えることが重要です。最後に、読者の体験を最優先に考え、対象デバイスのリストと優先機能を事前に整理しておくと、開発スケジュールや品質管理がぐっと楽になります。
| 項目 | EPUB2 | EPUB3 | コメント |
|---|---|---|---|
| ファイル構成 | OPF + NCX | OPF + NAV + XHTML5 | 現代的な导航が取り入れやすい |
| 本文表現 | XHTMLとCSS2.1 | HTML5とCSS3 | デザインの自由度が高い |
| アクセシビリティ | 限定的 | 改善済み | スクリーンリーダー対応が向上 |
| デバイス互換 | 旧機種にも対応するケースが多い | 新機種を優先する傾向 | 新規制作はEPUB3が主流 |
この表を見れば、EPUB2とEPUB3の根本的な差が一目でわかります。
ただし“互換性と機能の両立”という現実的な問題は、プロジェクトごとに異なる予算や納期にも影響されるため、最終決定はケースバイケースで行うべきです。
ある日友達と話していて、EPUB3の話題が出たときの私の雑談風のおやこ話です。友達は「EPUBって何が新しいの?」と尋ね、私はこう答えました。EPUB3はHTML5とCSS3の世界に近づいた新機能の集まりで、フォントの埋め込みや色の管理、固定レイアウトの活用などで読みやすさとデザインの自由度がぐんと高くなっています。EPUB2は堅実ですが時代遅れの機能も多く、最新機器との相性はやや不安定です。だからこそ、私は「今どのデバイスで読まれるのか」「必要な機能は何か」を最初に決めるべきだと思います。デジタルの世界は日々進化しますから、長期的な視点でEPUB3へ移行する計画を立てておくと安心です。
次の記事: 楽天koboと楽天ブックスの違いを徹底解説!どっちを選ぶべき? »





















