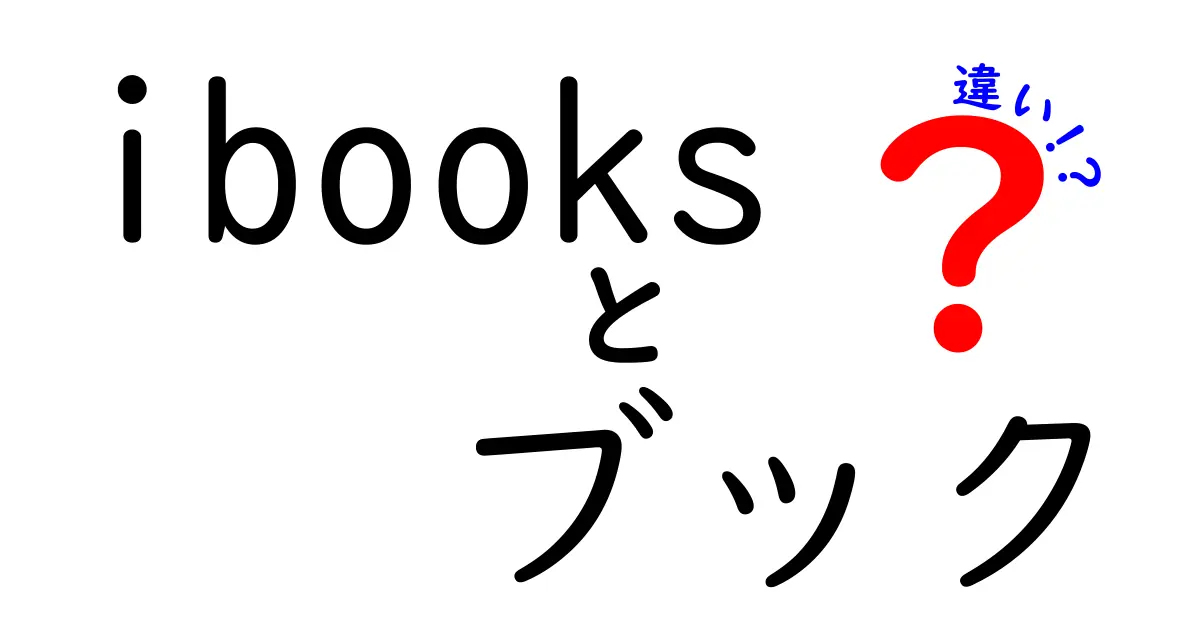

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに iBooksとBooksの違いを知ろう
この解説は、iBooksと Books の違いを理解したい人向けです。まず前提として、iBooks は以前から存在した電子書籍のアプリで、購入した本を読む以外にもしおりやメモ、辞書機能などを提供していました。
一方、現在の名称は Books で、デザインや機能が一部刷新され、教育機関向けの機能や蔵書の管理が改善されています。
この差は端末間での同期、ファイル形式の扱い、作者向けツールの継承といった点にも及び、日常の読書体験にも影響しています。
歴史的には、iBooks Store や iBooks Author の存在が大きく、前者は電子書籍の販売を、後者は対話型の教科書作成を可能にしました。
名前の変更は単なるブランド変更ではなく、アプリの機能統合と将来の拡張性を見据えた戦略の一部です。
読者としては、現在のBooksアプリを使えば、購入履歴の管理や読書の進捗同期、ハイライトやメモの共有ができます。
1) 名称の変遷と時代背景
初期の iBooks は、2010年頃に登場し、iPad の普及とともに電子書籍市場を広げました。
その後、iBooks Store が登場し、世界中の蔵書が手元の端末に入る時代が始まりました。
時を経て、2018年のブランド変更でアプリ名は Books へと改名。
この背景には、教育向け機能の拡充や、iCloud を通じた同期強化、書籍のファイル形式の標準化などが挙げられます。
現在でも Books は日常的な読書のパートナーとして広く使われ、 iBooks の名残を残しつつ、新しい機能が徐々に追加されています。
歴史的には、iBooks の Store は電子商取引の初期段階を代表するもので、デジタル書籍の購入体験を家庭や学校の読書習慣へと根づかせました。
一方、iBooks Author は教育用の対話型コンテンツを作るためのツールとして登場し、教科書のデジタル化を後押ししました。
こうした背景は、現在の Books の多機能な蔵書管理と教育機能の礎となっています。
2) 対応アプリと主な機能の違い
旧 iBooks は基本的な読書支援とメモ、しおりなどの機能が中心でしたが、現在の Books では、蔵書の管理や検索性、進捗の同期、ハイライト・メモの共有、フォントや背景の調整、ダークモードなどのUI要素が追加されています。
また、教育向けの機能強化により、教科書的な本の扱いが改善され、大学や学校での活用も進んでいます。
この変化はユーザーの使い勝手を高め、複数端末間の作業をスムーズにします。
さらに、Apple のエコシステム内での統合も進み、Apple Books Store で購入した書籍が iPhone から Mac へと自然に引き継がれることが増えました。
検索機能はローカルだけでなくクラウドにも連携され、辞書機能やハイライトの共有機能が強化されています。
教育用途では、教科書向けの固定レイアウトや美しい組版を保つ EPUB の活用が容易になり、学習の現場での活用が広がっています。
3) ファイル形式と入手手段
iBooks の時代には、EPUB や PDF が主な対応形式で、iBooks Author で作成した本は IBA 形式という特別なファイルもありました。
このIBA は作成元のアプリでのみ表示・編集され、Books アプリへの直接の互換性は限定的でした。
現在の Books では、出版物は主に EPUB と PDF で入手可能です。書籍の取得は Apple Books Store を通じて行われ、購読機能や家族共有などの仕組みも整っています。
また、iBooks Author のような対話型教科書作成ツールは終了し、代わりに Pages などのツールで出版準備を進める形になりました。
入手手段は基本的に同様ですが、運用面は大きく変化しました。旧 iBooks では端末内のファイルを直接管理する感覚が強かったのに対し、現在の Books ではクラウド上の蔵書とローカルの本が共存する形で整理されます。
教育現場では、学校専用のアカウント経由での配布や、学習用の課題としての配布が行われることが多くなりました。これにより、学習の連携が取りやすくなっています。
4) 使い勝手と UI の変化
デザイン面では、 Books は洗練された library 表示と読みやすさを追求しています。フォント選択、行間、背景色、ダークモードなどが細かく設定でき、端末間で同じ設定の再現性も高いです。
また、メモやハイライトの整理方法が改善され、共有機能の選択肢も増えました。初期のiBooks と比べ、教育現場での利用を想定したインターフェースの直感性が高まっており、スマホとタブレットの両方で安定した閲覧体験を提供します。
この違いは、長時間の読書や動画付きの教科書を扱う際に特に感じられ、学習の効率化につながります。
UI の変更だけでなく、アプリの設定項目自体も整理され、使い方のガイドが以前より公開されやすくなりました。
家族間でのアカウント共有が増え、進捗の同期やしおりの共有が容易になることも、日常の学習をサポートしています。
5) まとめと今後の動向
本記事のポイントは、 iBooks と Books は名前と一部機能の刷新を伴いながらも、読書体験の中核となる機能は連続しているという点です。
将来的には、Apple Books の教育向け拡張、クラウド連携の高度化、より豊かな EPUB3 のサポートなどが期待されます。新しい機能が出るたびに使い方の変化を探りつつ、最終的には自分の学習スタイルに合わせた環境を作ることが大切です。
読書という行為は道具によって変わるものではなく、どう活用するかが重要です。
友だちと放課後の話題でよく出るキーワードが Books です。昔は iBooks というアプリ名で、蔵書を読むだけのイメージだったよね。今は Books へ名前が変わり、見た目も機能も少し変わったんだ。例えば同じ本を複数の端末で一度に開けるようになったのは嬉しいポイント。だけど大事なのは、名前が変わっても本を読む体験そのものは基本的には同じ、ということ。新機能の話をしても、結局は自分が読みたい本に早く辿り着くための道具が整えられているだけ。私は結局、暗いところで読みやすいフォント選びとしおりの活用を楽しんでいる。





















