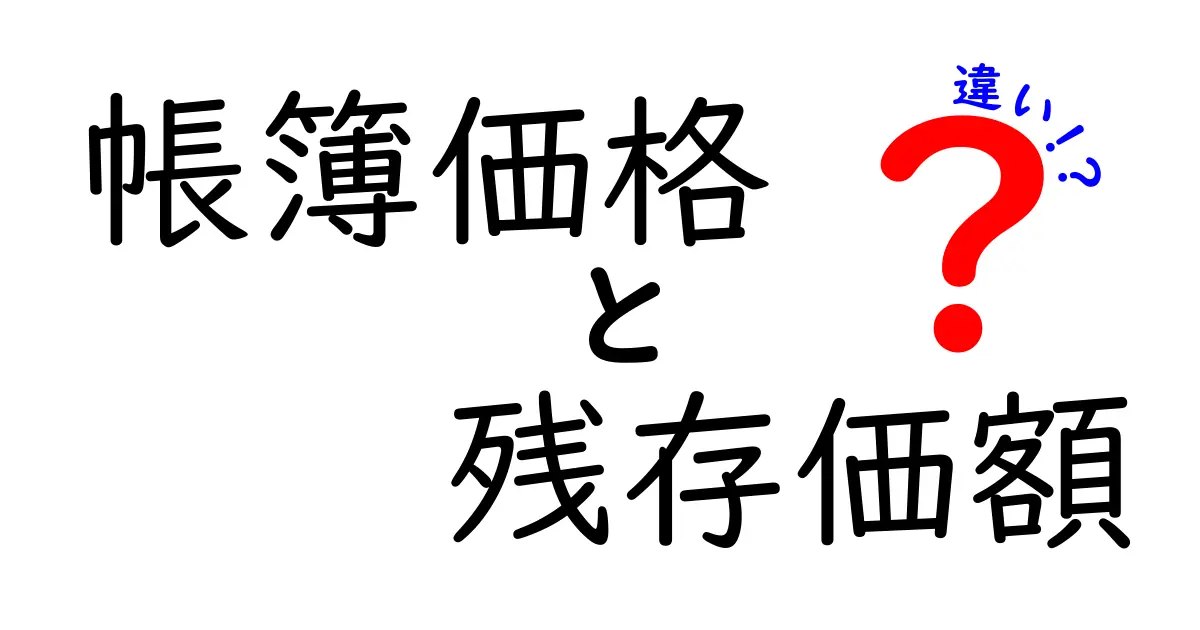

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
帳簿価格とは何か?基本からわかりやすく解説
帳簿価格は、企業や個人が所有する資産の価値を会計上で記録するときの金額のことを指します。これは購入した時の価格から、減価償却などで価値が減った分を差し引いた金額で表されます。
たとえば、パソコンを10万円で買ったけど、1年で価値が1割落ちた場合、帳簿価格は9万円になります。 こうして資産の現在の価値がわかるようにするのが帳簿価格の役割です。
帳簿価格は、どのくらい資産が減ったのか、またどれだけ残っているのかを数字で把握できる便利なものです。
この帳簿価格は会計のルールに基づいて算出されるので、実際の市場価値とは異なることがあります。つまり、実際に売るときの値段とは違う数字ということですね。
ここで大切なのは、帳簿価格はあくまで会計的な価値で、『今この資産がどれほど企業の財産として残っているか』を示しているという点です。
残存価額とは?資産の最後の価値を意味する重要なポイント
残存価額とは、資産が使い終わったとき、または耐用年数が終了したときに残っている価値のことを指します。
例えば、機械を5年間使う予定で購入した場合、5年後にまだ使えそうな部品やスクラップとして値打ちがあると見積もる金額が残存価額です。
この残存価額は、減価償却の計算にも関わっていて、資産の価値を減らす際の目安となります。つまり、購入価格から残存価額を差し引いた金額が減価償却の対象となり、毎年の経費として計上されることになります。
残存価額は常にゼロとは限らず、資産の種類や状態によってはかなり高い価値が残っている場合もあるため、見積もりが重要になります。
帳簿価格と残存価額の違いを比較!理解しやすい表で解説
ここまで説明した内容を元に、帳簿価格と残存価額の違いを表でまとめます。
| 項目 | 帳簿価格 | 残存価額 |
|---|---|---|
| 意味 | 購入価格から減価償却などを差し引いた現時点の価値 | 資産の使用期間終了時に残る見積もられた価値 |
| 計算の目的 | 資産の現在の会計上の価値を示す | 減価償却の計算に使う |
| 変動 | 年々減価償却に伴い減る | 通常固定で事前に設定される |
| 会計処理での役割 | 貸借対照表に表示される | 減価償却費を決定する基準になる |
このように、帳簿価格は時点ごとの資産価値で、残存価額はその資産の最後の価値として設定されるものです。両者は似ていますが用途も意味も異なるので、混同しないよう注意しましょう。
これらの違いをきちんと理解すると、会社の資産管理や決算の際に正しい判断ができるようになります。
「残存価額」という言葉を聞くと難しそうですが、実はとても身近な考え方です。例えば、自転車を買って5年使ったとしますよね。5年後の自転車は、使わなくなるかもしれませんが、まだ部品として売れたり、鉄としての価値が残っていたりします。この価値が「残存価額」にあたります。会計の世界では、この価値を事前に見積もっておくことで、毎年どれくらい価値が減ったかを計算しやすくしています。つまり、残存価額は物の「最後の価値」を予想して、資産の減り具合をチェックするための大切な数字なんですね。知らないと損かもしれません!





















