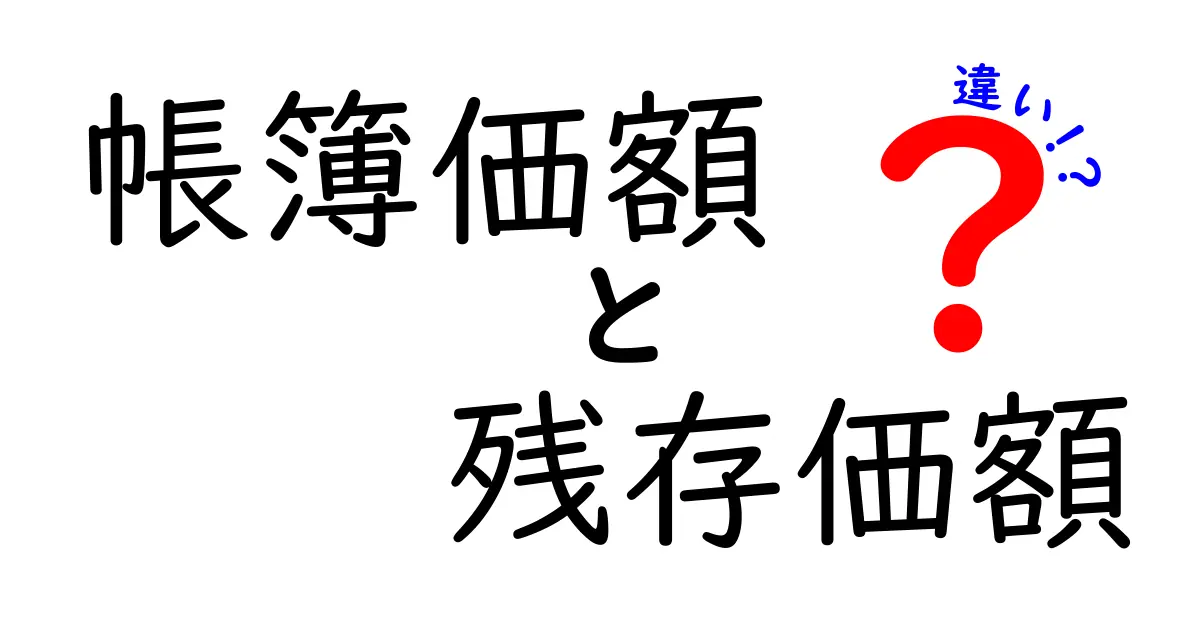

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
帳簿価額とは何か?基本を理解しよう
帳簿価額(ちょうぼかがく)とは、会社や個人が持っている資産の価値をお金の数字で表したもので、特に会計や経理で使われます。たとえば、新しいパソコンを10万円で買ったとき、そのパソコンの帳簿価額は最初10万円です。
しかし時間が経つと、そのパソコンの価値は下がっていきます。パソコンは古くなると使い勝手が悪くなったり、故障しやすくなったりするためです。会社では、こうした価値の減りを「減価償却」と呼びます。つまり、帳簿価額は資産を買ったときの値段から、減価償却分を引いた、現在の価値を表しています。
たとえば、1年ごとに2万円ずつ価値が下がるパソコンなら、1年後の帳簿価額は8万円、2年後は6万円と減っていきます。このように、帳簿価額は資産の価値の変化を会計上で記録するための数字です。これは会計の正確な経営判断に欠かせない数字と言えるでしょう。
残存価額とは?資産の最後に残る価値
残存価額(ざんそんかがく)とは、その資産が使い終わる最後の時点でどれだけの価値が残っているかを表す数字のことです。
たとえば、冒頭のパソコンの場合、使い終わった後でも、本体の部品をリサイクルしたり、他の用途に使ったりできることがあります。そうしたとき、その価値を残存価額と言います。
経理では減価償却を計算するときに、資産がゼロの価値にならない前提で残存価額を設定します。例えば、10万円のパソコンの残存価額を1万円と決めると、減価償却の対象となる金額は9万円となり、この9万円を使った期間で割って償却します。
残存価額は、資産の減価償却を計算するうえで終了時の最小価値の目安として使われ、資産の価値を完全に0にしないことで現実的な見積もりを行っています。
帳簿価額と残存価額の違いを表で比較!
ここまでの説明を簡単にまとめると、帳簿価額は現在の資産の簿記上の価値であり、残存価額は資産の寿命の最後に残る価値です。違いを見やすく表で比較してみましょう。
| 区分 | 帳簿価額 | 残存価額 |
|---|---|---|
| 意味 | 資産購入価格から減価償却した現在の簿記価値 | 資産使用後に残る価値・廃棄時の価値 |
| 使い方 | 会計上の資産価値の記録 | 減価償却の計算で減価償却費の基準となる |
| 計算時期 | 毎会計期間ごとに変動 | 資産購入時にあらかじめ決定 |
| 価値の変化 | 減っていく値 | 固定された値 |
まとめ:帳簿価額と残存価額の違いを理解して経理を楽にしよう
今回ご説明した通り、帳簿価額と残存価額は共に資産の価値を表す言葉ですが、意味と使い方が異なります。
帳簿価額は資産の現時点での価値を記録するもので、減価償却により毎年変わります。一方で、残存価額は資産が使い終わった時に残る価値のことで、あらかじめ決めておきます。
これらの違いをきちんと押さえることで、会計処理がスムーズになり、会社の資産管理や経営判断がしやすくなります。
経理初心者の方も、資産の価値がどう変わっていくのかを理解して、スッキリとした会計処理を目指しましょう!
残存価額って聞くとなんだか難しそうですが、実は資産の最後の“おこづかい”みたいなものです。例えば古くなった自転車、完全に壊れたわけじゃないから一部パーツは売れたり、誰かにあげたりできますよね。それが残存価額です。帳簿価額は減っていく価値全体のこと、残存価額は残っている最後の価値、と覚えるとわかりやすいですよ!
次の記事: 備忘価額と残存価額の違いとは?誰でもわかる簡単解説! »





















