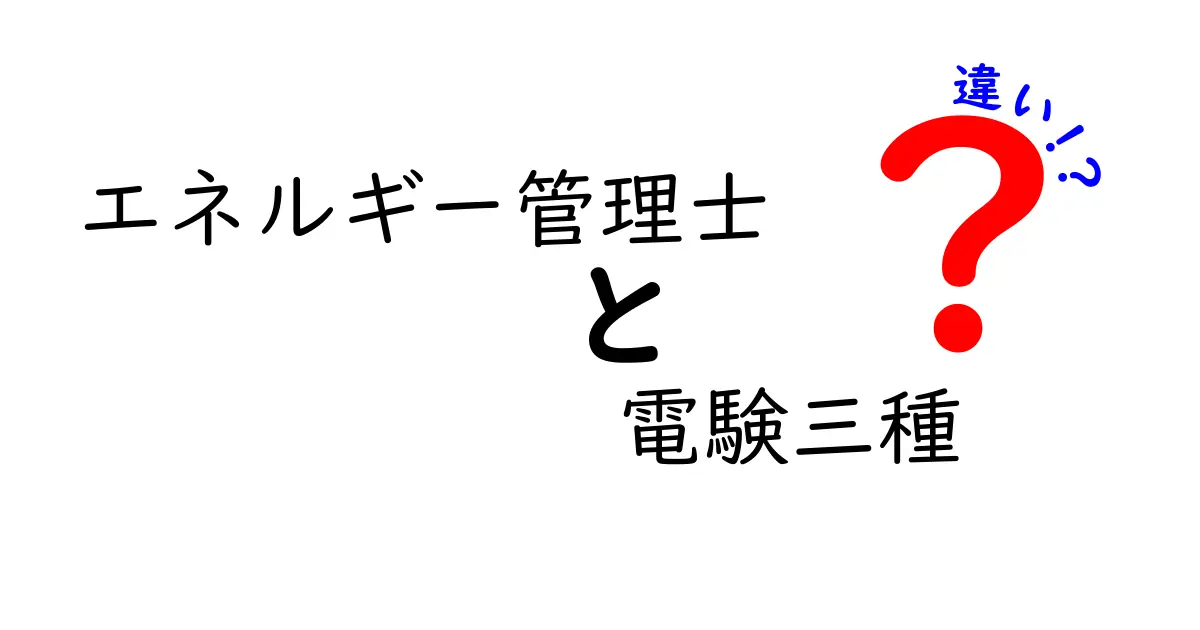

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
エネルギー管理士と電験三種って何?基本の違いを理解しよう
エネルギー管理士と電験三種は、どちらも電気に関する資格ですが、じつはその目的や役割が大きく異なります。
エネルギー管理士は、工場やビルなどのエネルギーの使用を効率よく管理し、省エネを推進する専門家の資格です。
対して、電験三種(第三種電気主任技術者)は、電気設備の保守や運用を担う技術者向けの国家資格です。
どちらも電気の専門知識が必要ですが、その使い道や働く場所が違うのがポイントです。
簡単に言うと、エネルギー管理士は“エネルギーの使い方を上手にする人”、電験三種は“電気設備を安全に動かす人”というイメージです。
この違いをしっかり理解することが、どちらの資格を目指すかの第一歩になります。
資格試験の内容と難易度を比較!どちらがどんな知識を問う?
エネルギー管理士と電験三種は、試験科目や難易度にも違いがあります。
エネルギー管理士は、エネルギーの使用状況の測定や、省エネルギーの技術に関する問題が中心です。
具体的には、エネルギー管理に関する法規、省エネ手法、設備の運用・管理方法について学びます。
一方、電験三種は、電気の理論や電気設備の保守・運転技術がメイン。
電気回路や電気機器、法規、電力管理の知識を幅広く問われ、計算問題も多いです。
どちらも国家資格であり、合格率は30%前後。
ただし勉強の内容が異なるため、自分の興味や将来の仕事に合った資格選びが重要です。
| 資格名 | 主な試験科目 | 難易度 | 合格率(目安) |
|---|---|---|---|
| エネルギー管理士 | 省エネルギー技術、エネルギー法規、運用管理 | 中程度 | 約30% |
| 電験三種 | 電気理論、機械、法規、電力管理 | 中~高め | 約25~30% |
活躍の場と仕事の内容の違い!どんな職場でどんな役割?
エネルギー管理士の活躍場所は主に製造業の工場や大きな建物です。
彼らの仕事は、エネルギーの無駄遣いを見つけて効率よく使う方法を提案したり、法律を守るように指導したりします。
最近は環境問題の意識が高まり、省エネの重要性も増しているため需要が伸びています。
電験三種保有者は、電気設備を管理・運用し、トラブルがあればすぐに対応します。
発電所や変電所、ビルの電気室など様々な現場で安全な電気の運転を支える役割です。
また、設備の点検やメンテナンス計画を立てる重要なポジションでもあります。
このように、エネルギー管理士は「エネルギーを効率的に使う専門家」、電験三種は「電気設備の安全守衛」と言えます。
どちらも社会に欠かせない役割ですが、自分の得意分野や興味に合わせて選びましょう。
電験三種の試験には計算問題が多いのですが、中でも電気回路の問題はちょっとしたパズルのようです。
例えば複雑な回路の合成抵抗を求めたり、交流の電圧や電流の位相を考えたりします。
これができると電気の流れを数学的にイメージできるようになり、電気設備の問題解決がスムーズに!
電気に興味がある人なら、この試験の計算問題が意外と楽しく感じられるかもしれませんね。
前の記事: « CO2排出量と温室効果ガス排出量の違いとは?わかりやすく解説!





















