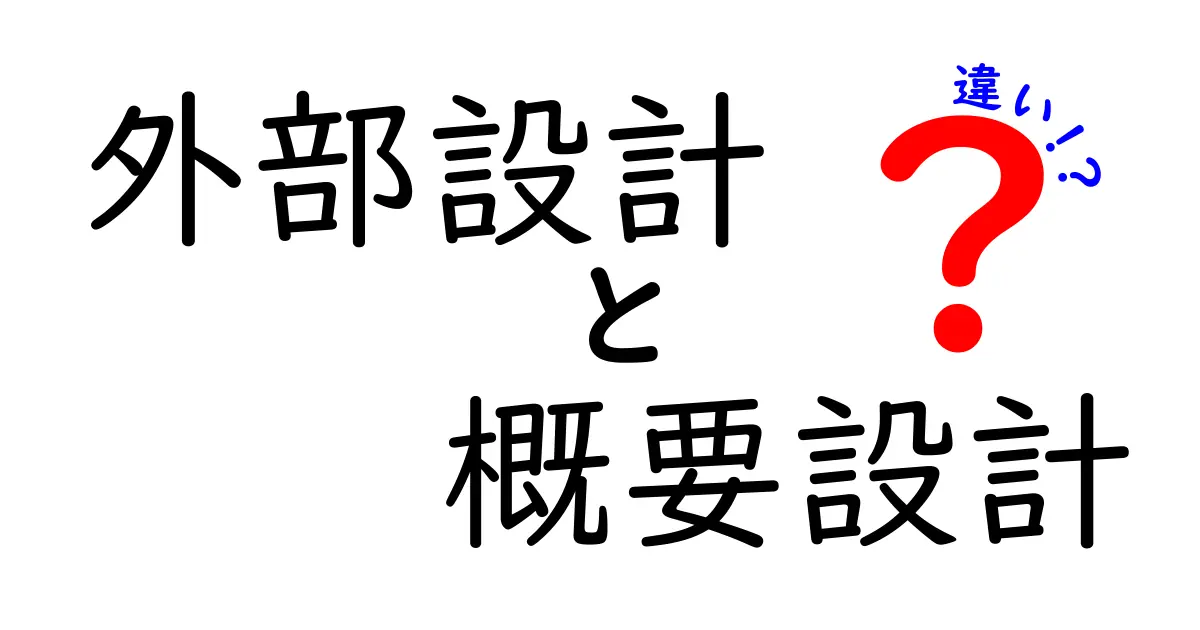

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
外部設計と概要設計の基本的な違いとは?
システム開発の世界でよく出てくる言葉に「外部設計」と「概要設計」があります。これらはどちらもシステムを作るための大切なステップですが、実は役割や内容が少し異なります。
簡単に言うと、外部設計はお客さんやユーザーの視点でシステムの動きを決める段階です。
一方、概要設計はシステム全体の仕組みや機能を技術者の視点でまとめる段階です。
つまり、<外部設計>は「どんなことができて、どう見えるか」を決め、<概要設計>は「そのシステムをどうやって中で動かすか」を決めるイメージです。
この違いを押さえることが、システム開発をスムーズに進めるカギとなります。
外部設計の詳細とは?ユーザー目線での設計ポイント
外部設計ではユーザーが使う画面や操作方法、入力項目などを決めます。例えば、ウェブサイトでどのように情報を見せるか、どんなボタンが必要かなどを考えます。
具体的には、
- 画面設計(画面レイアウトや表示内容)
- 操作の流れ(ユーザーが行う動作や順序)
- 入出力のデータ(何を入力し、何が出るか)
これらはプログラマーではなく、ユーザー体験を重視した設計なので、わかりやすく使いやすいことが期待されます。
そのため、外部設計書には画面のイメージ図や操作手順が書かれていることが多く、技術的な細かい部分はあまり含みません。
ユーザーが快適に使えるかどうかを最優先に考える段階です。
概要設計の詳細とは?システム全体の仕組みを固める
概要設計では、外部設計で決まった内容をもとに、システム全体の構成や機能の大まかな設計を行います。
ここでは、どの部分がどんな機能を担当するか、どのようにデータが流れるか、システム間の連携はどうするかなど、技術者の視点で考えます。
具体的には、
- システム構成図
- 主要な機能一覧
- データベースの設計概要
- 外部設計の仕様を実現するための方法論
概要設計で具体的なプログラミングはまだ行いませんが、どの機能をどのように実装するかの指針が詳しく決まります。
つまり、外部設計の"お客さんの要求"を、システムでどう実現するか技術的な形に落とし込むのが概要設計の役割です。
外部設計と概要設計の違いを比較表で確認!
このように外部設計と概要設計は役割も対象も異なり、互いに補い合う関係にあります。
システム開発ではどちらも丁寧に行うことで、ユーザーにとってよいシステムが作れます。
まとめ:違いを理解し、効率的なシステム開発を目指そう
今回は外部設計と概要設計の違いについて解説しました。
外部設計はユーザーの視点で「何をどう使うか」を決め、
概要設計は技術者の視点で「どうやって作るか」を決める設計段階です。
両者の違いを理解するとシステム開発の流れがよくわかり、それぞれの作業のポイントも押さえやすくなります。
そして、しっかりとした外部設計と概要設計があることで、無駄なく早く質の高いシステムができあがります。
これからシステム開発に携わる方は、まずこの違いをマスターしておきましょう!
「外部設計」と聞くと、ただ画面の設計だけと思いがちですが、実はユーザーの操作感や入力のルールなども含まれています。たとえば、どんな順番で操作するのか、どのボタンを押すとどんな動作になるのかまで詳しく考えます。
一方で概要設計は、こうした外部設計の内容を技術的にどう実現するかを決める場面なので、外部設計の「お客様の要望」を具体的なプログラムの骨組みに落とし込む役割があります。
つまり外部設計は“お客様の願いを聞く魔法の杖”、概要設計は“その魔法を実際に実現する魔法書”のような関係で、どちらもなくてはならないものなんです。
前の記事: « 「仕様変更」と「要件変更」の違いとは?初心者でもわかる完全ガイド





















