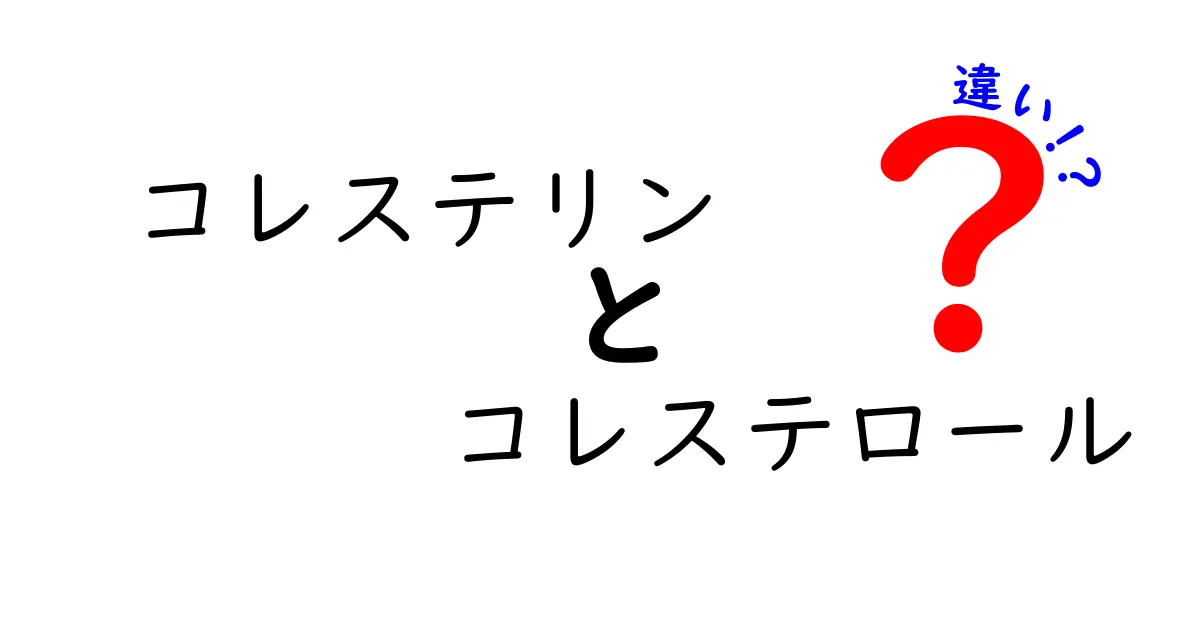

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
コレステリンとコレステロールは何が違うの?基本からわかりやすく解説します
みなさんは「コレステリン」と「コレステロール」という言葉を聞いたことがありますか?どちらも体の中でとても大切なものですが、名前が似ているのでよく混同してしまいます。
実は「コレステリン」と「コレステロール」は同じものを指す言葉であり、正しくは『コレステロール』が正しい呼び名です。「コレステリン」という言葉は、実際には存在せず、間違った言い方として使われることが多いのです。
それでは、なぜこのように間違いやすいのか、コレステロールの正しい意味と役割をくわしく見ていきましょう。
まずはコレステロールとは何かから説明します。コレステロールは、体の細胞を作る大切な脂質(ししつ)の一種です。脂質は油のようなもので、エネルギーや細胞膜の材料となります。コレステロールは特に、細胞膜の強さや柔らかさを調整したり、体の中でホルモンやビタミンDを作るための材料になっています。
私たちの体は肝臓でコレステロールを作り出すことができるので、食べ物からの cholesterol 摂取も含めて、必要な量を調整しています。
健康診断でよく聞く「LDLコレステロール」「HDLコレステロール」は、血液に含まれるコレステロールが運ばれるときの種類を指しています。LDLは悪玉コレステロールと言われ、血管に悪影響を与えることがあります。HDLは善玉コレステロールで、余分なコレステロールを回収して体の外に運び出す役割があります。
「コレステリン」と言われることが多いのはなぜか?間違いやすい名前の理由
先ほども説明した通り、「コレステリン」という言葉は正しい名称ではありません。
この混乱の原因は、昔から使われている日本語の発音やカタカナ表記のゆれにあります。
英語の "cholesterol" をカタカナに変換するとき、“-sterol”の部分が聞き取りにくくて「コレステリン」と間違えられやすかったのです。
また、語尾が「-リン」で終わる言葉は科学の用語で多いので、そのまま馴染みやすい言葉の音を当ててしまう傾向も関係しています。
しかし、健康や医学の正式な場では必ず「コレステロール」を使うことが決まっています。
「コレステリン」という言い方は誤った呼称のため、正しくは使わないようにしましょう。
次に、コレステロールが私たちの体にどんな影響を与えるのか、注意したいポイントを解説します。
コレステロールの役割と健康への影響。良い面と悪い面を理解しましょう
コレステロールは体にとって「なくてはならない大切な物質」ですが、増えすぎると問題になります。
まず、コレステロールは細胞の構造を支えたり、ホルモンやビタミンDの材料になる良い役割があります。体の正常な働きに欠かせません。
しかし、血液中のLDLコレステロールが多くなり過ぎると血管の壁にたまりやすくなり、動脈硬化を起こすリスクが高まります。動脈硬化になると心臓や脳の病気につながることがあります。
一方でHDLコレステロールは血管から余分なコレステロールを運び出し、体を守る働きがあります。
だから、コレステロールの量をチェックするときはLDLとHDLのバランスが大切なのです。
健康的な生活を心がけてバランスよく維持することが、心臓病や脳卒中などの予防につながります。
コレステロールのことを正しく理解し、間違った名称の「コレステリン」を使わないことも、健康知識の基本です。
コレステリンとコレステロール 違いまとめ表
| 呼び名 | 意味 | 使用の正確さ | 備考 |
|---|---|---|---|
| コレステロール | 脂質の一種で体に必須。細胞膜やホルモン材料。 | 正しい | 医学や健康の正式名称 |
| コレステリン | 誤った呼び方で実際の物質は存在しない。 | 誤り | 聞き間違いや発音のゆれから生まれた言葉 |
まとめると、「コレステリン」という言葉は間違いで、正しく使うなら「コレステロール」と言うこと。健康のためにはコレステロールの量とバランスをチェックし、正しく理解することが大切です。
この知識を持って、健康診断や日常生活での会話に役立ててくださいね。
「コレステロール」という言葉はよく耳にしますが、実は「コレステリン」という言い方は間違いなんです。面白いのは、この間違いは英語の"cholesterol"の発音が聞き取りにくいことや、カタカナの音の変化が原因という点です。たしかに"-sterol"の部分は日本語にするとちょっと言いにくくて、「コレステリン」と聞こえやすいんですよね。でも、健康の話をするときは必ず「コレステロール」と正しく呼ぶことが大切です!この小さな違いを知るだけで、ちょっと賢く見えちゃいますね。
前の記事: « 解放と開放の違いとは?意味や使い方をわかりやすく解説!





















