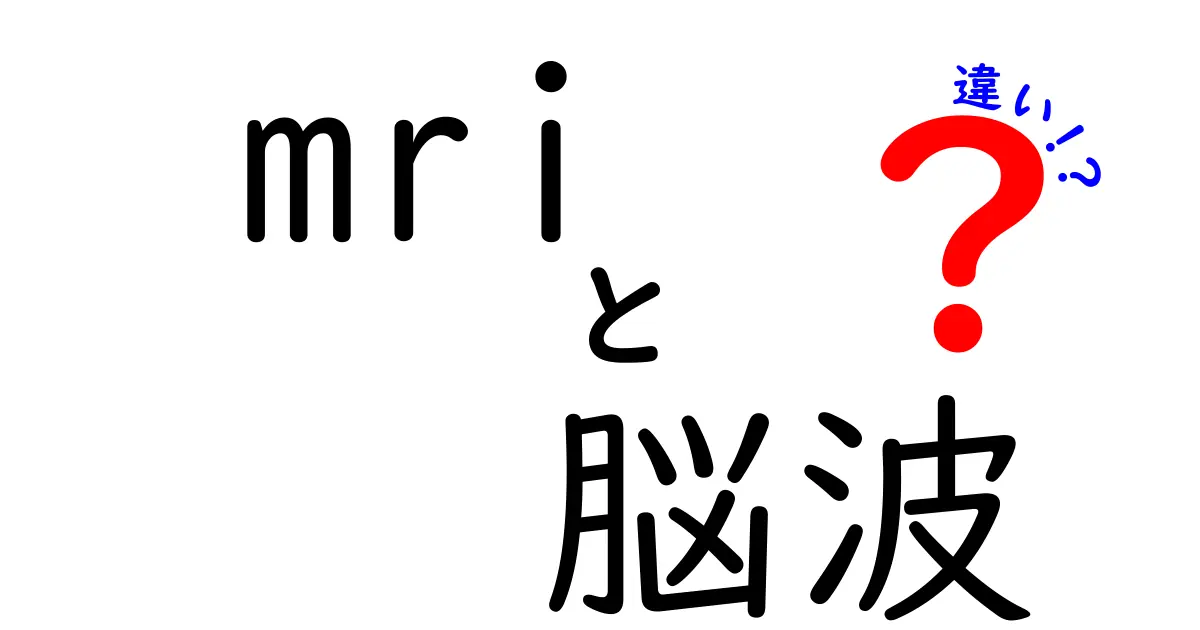

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
MRIと脳波とは何か?それぞれの特徴を知ろう
まずはMRI(エムアールアイ)と脳波(のうは)がどんな検査かを説明します。
MRIは、磁気と電波を使って体の中の断面を詳しく撮影する検査です。特に脳の構造や異常をはっきりと映し出せます。例えば脳の腫瘍や出血、脳の変形などを調べるのに使われます。
一方、脳波は脳の神経が発する微弱な電気信号を頭に取り付けたセンサーで測る検査です。脳の活動の状態や異常な電気のパターンを記録し、てんかん発作や睡眠障害の診断に役立ちます。
このように、MRIは脳の形や状態を画像で見るのに対し、脳波は脳の電気活動を記録して脳の働きを見ます。
MRIと脳波の違いを詳しく比較!
それぞれのメリット・デメリットは?
ここからはMRIと脳波の違いをいくつかのポイントで比較します。表も合わせて見てください。特徴 MRI 脳波 検査方法 磁気と電波を使い体の画像を撮影 頭に電極をつけて脳の電気信号を測定 わかること 脳の形や腫瘍、出血、障害 神経の電気活動、てんかんや異常脳活動 検査時間 30分~1時間程度 20分~1時間程度 痛みやリスク 基本的に痛みなし。ただし閉所恐怖症の人は難しい場合あり 痛みなし。非侵襲的で安全な検査 使用目的 主に構造の診断 主に機能の診断
このように、MRIは脳の構造を画像化する検査、脳波は脳の電気活動を計測し機能や異常を調べる検査だと覚えましょう。
検査の目的により使い分けられますが、時には両方行ってより正確な診断を目指すこともあります。
MRIと脳波はどんな時に使う?実際の利用シーンを紹介
MRIと脳波は病気の種類や診断の目的によって使い分けられます。
・MRIが使われるのは、頭を強く打った後の脳内の出血確認や、脳腫瘍の位置・大きさの把握、脳梗塞の有無を調べる時です。
・脳波は、てんかんや発作の診断、睡眠障害の調査などに利用されます。また、脳の働きの程度を評価したり、脳死判定の一部にも使われることがあります。
このようにMRIは脳の形を見るのに適していて、脳波は脳の電気的な活動や働きを見るのに適しているのです。
どちらも痛みはなく安全な検査ですが、MRIは閉所恐怖症の人にはつらいことがあるため、状況に応じて医師が検査方法を選びます。
MRIと脳波の違いって聞くと難しそうに感じますよね。でも、実はMRIは脳の“形”をはっきり見せる写真のようなもの。脳波は“脳の動き”を電気で記録する音楽の楽譜のようなものなんです。だから、MRIは脳の怪我や腫瘍を探すときに使われ、脳波はてんかんみたいに脳の電気のリズムが変わる病気の診断に役立ちます。どちらも脳を知る大事なツールなんですよ。





















