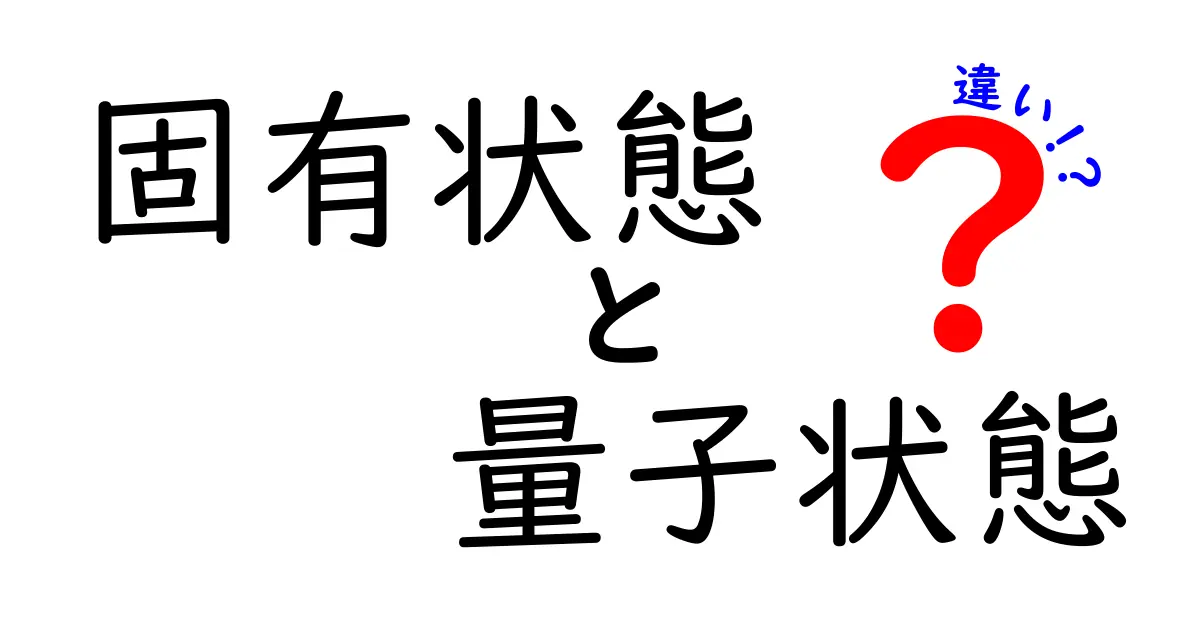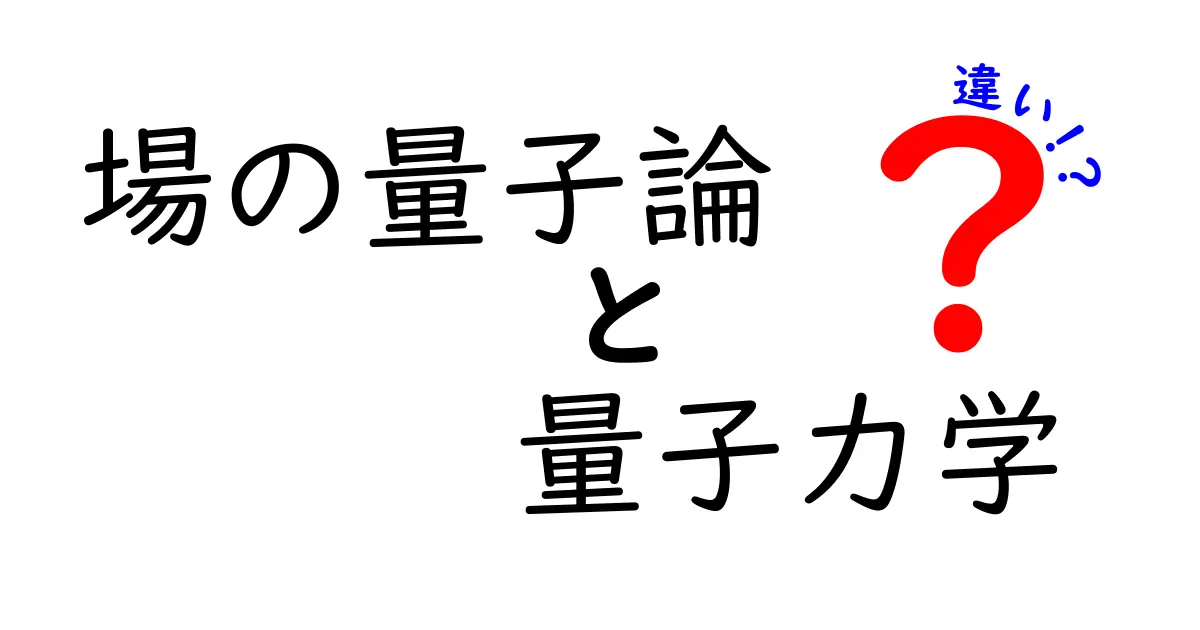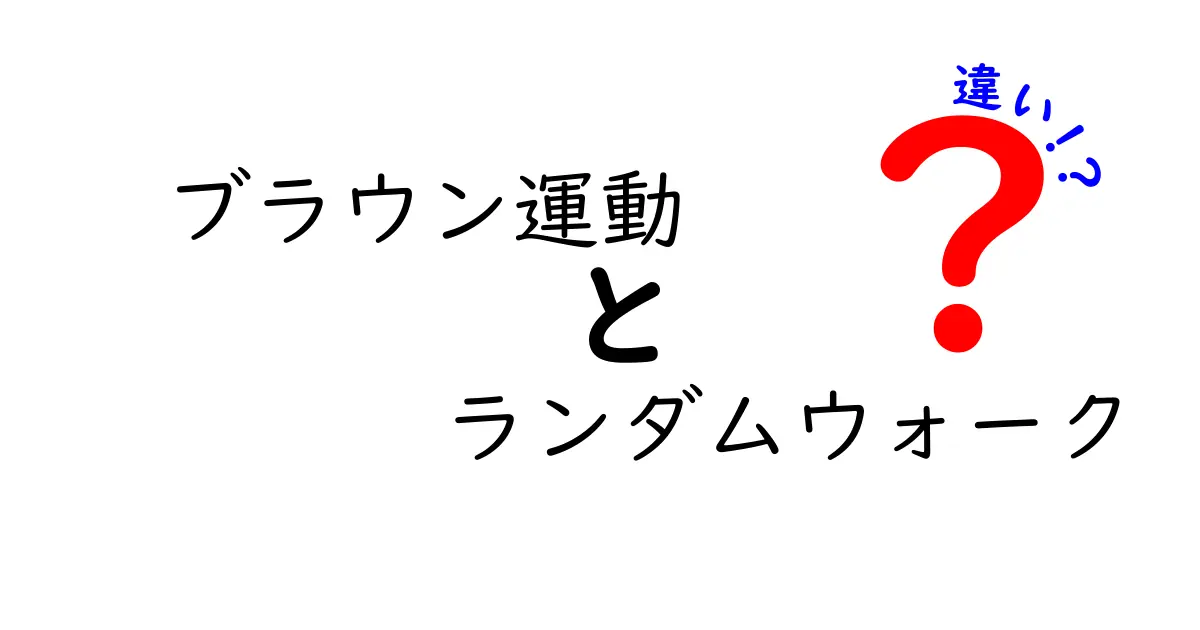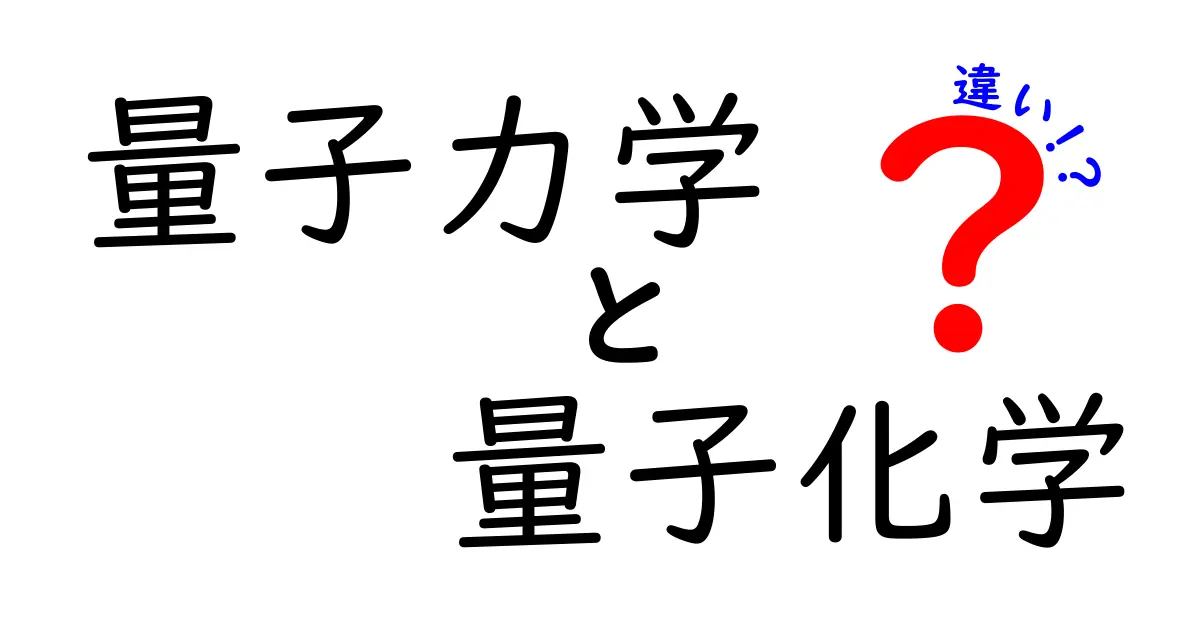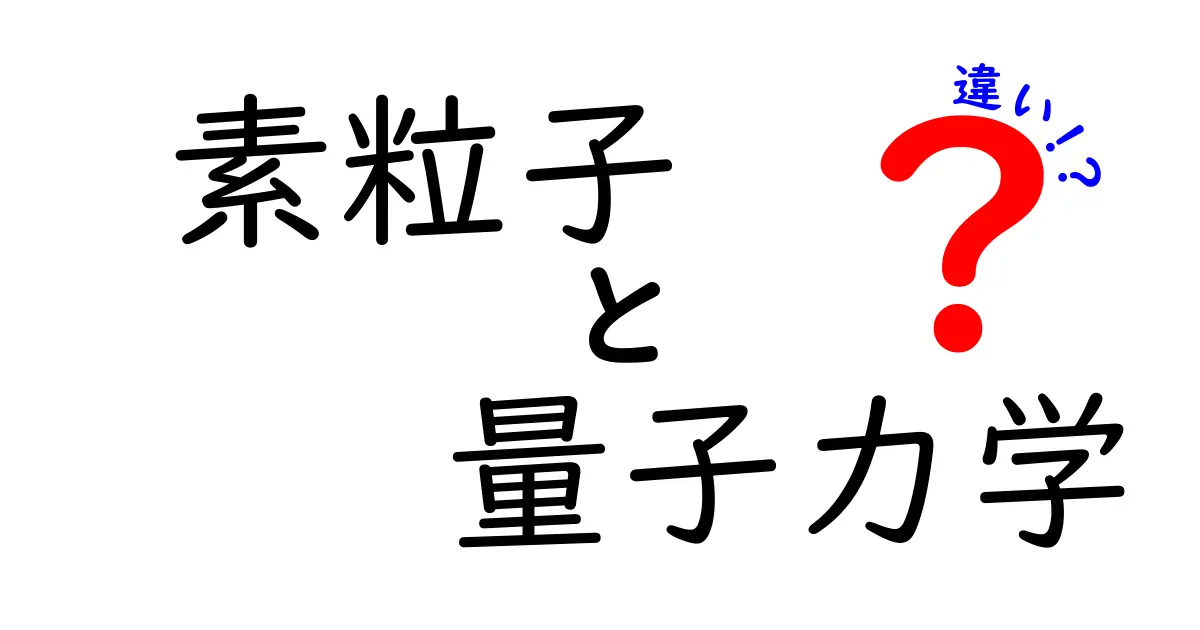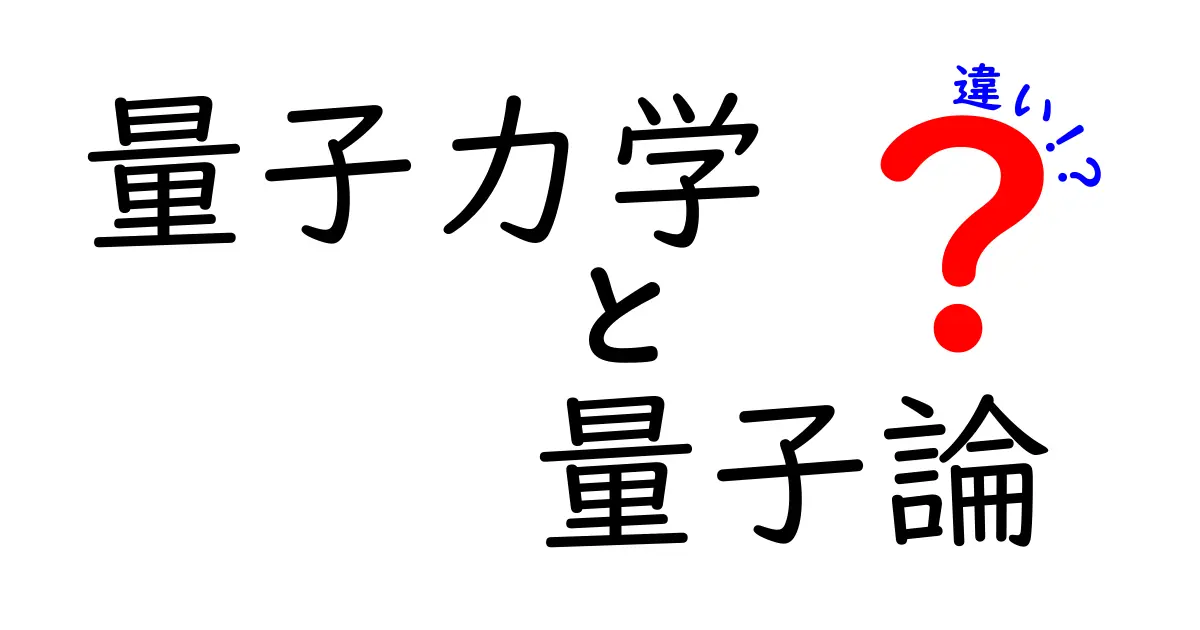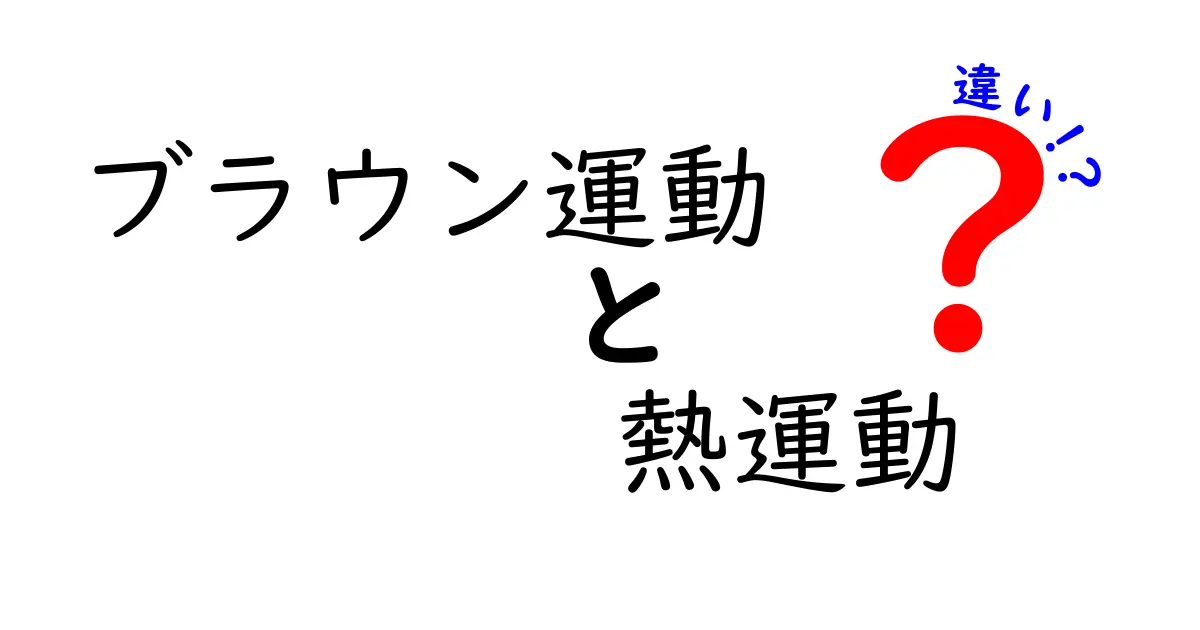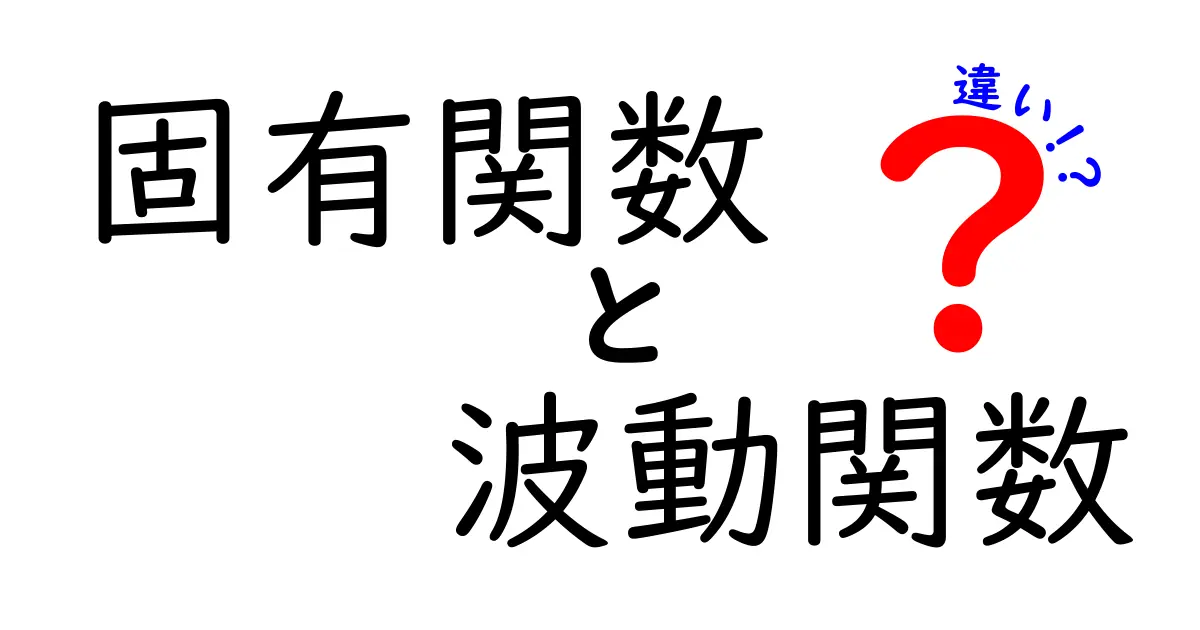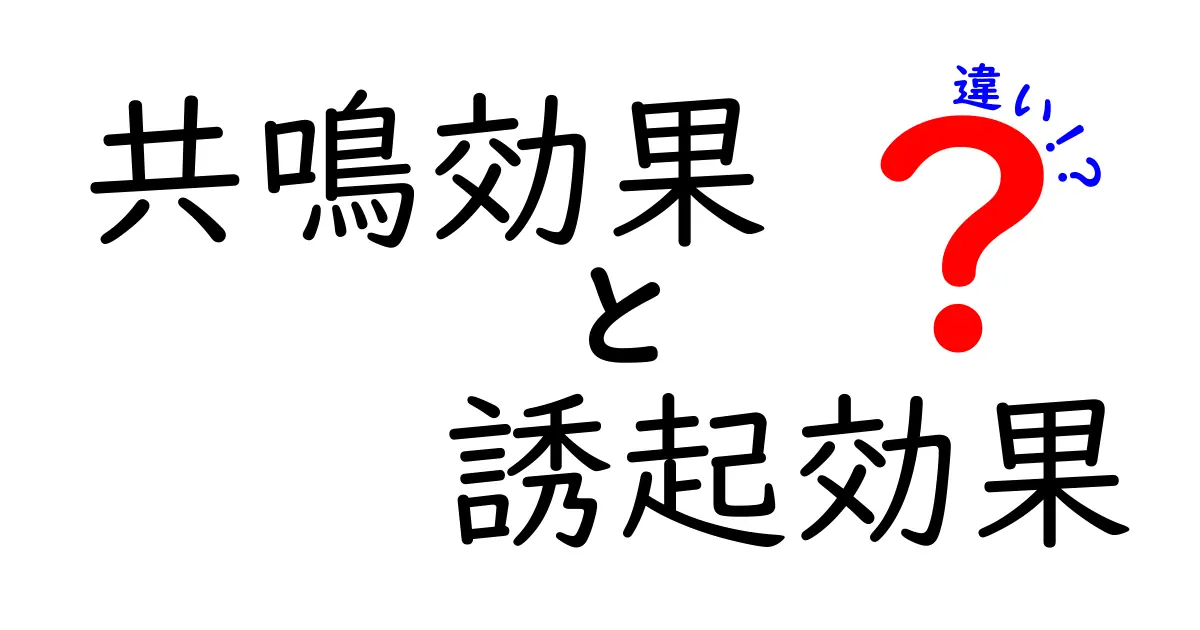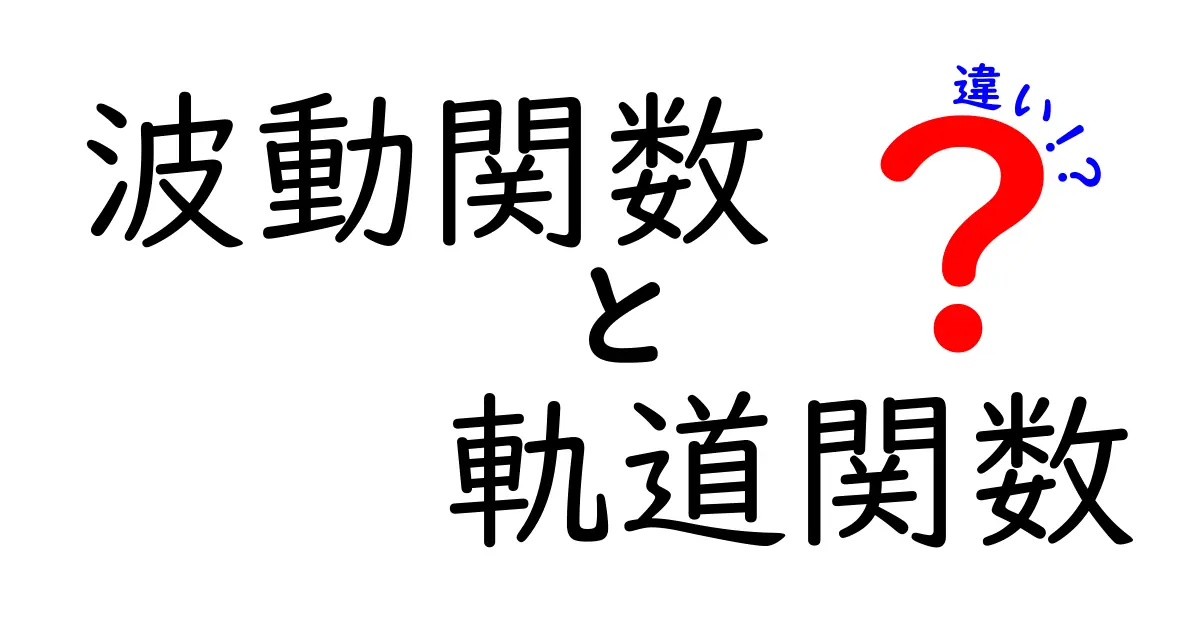

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
波動関数とは何か?
まずは波動関数について説明しましょう。波動関数は、量子力学で使われる非常に重要な概念です。簡単に言うと、原子や分子の中にいる電子の状態を数学的に表したものです。波動関数は、電子が「どこにいるのか」「どんなエネルギー状態にあるのか」を示す情報が詰まっています。
波動関数は、複雑な数値で表される関数で、これだけでは直接「電子の場所」を教えてくれるわけではありません。しかし、この関数を使って「電子がある場所にいる確率」を計算することができるのです。
たとえば、波動関数を自分で描くと、電子が見つかる場所の可能性の高い部分と低い部分がわかります。これは、私たちが量子力学で電子のふるまいを理解する基礎になります。
波動関数は物理の数学的な背景を持つため少し難しい言葉が多いですが、電子を確率的に説明するツールと覚えておくと良いでしょう。
軌道関数とは何か?
次に軌道関数について説明します。軌道関数は、波動関数の中でも特に単純化されたもの、つまり「一つの電子がいる特定の状態」を表す波動関数のことです。
私たちが中学校や高校で学ぶ電子の「軌道」は、この軌道関数によって説明されます。軌道は、電子がいる可能性の高い空間の形としてイメージされていて、s軌道やp軌道、d軌道などがよく知られています。これらは原子の電子配置を理解するためにとても役立ちます。
軌道関数は波動関数の一種であり、特定のエネルギー状態と形を持つ電子の波動関数と言えます。つまり、波動関数全体はさらにたくさんの軌道関数の組み合わせでできているイメージです。
このように軌道関数は、複数の電子系の波動関数をわかりやすく表現したものとも言うことができます。
波動関数と軌道関数の違いを表で比較!
まとめ:違いを知ることの重要性
波動関数は量子力学の基本的な概念で、電子などの微小な粒子の状態を数学的に表現します。一方で軌道関数は、波動関数の中の分類の一つで、特定の電子の状態をわかりやすくしたものです。
科学を学ぶときにはこうした用語の違いを理解することが大切で、特に量子力学の基礎を学ぶときに役立ちます。波動関数と軌道関数の違いを知ることで、原子や分子のふるまいを深く理解できるようになります。
ぜひこの違いを押さえて、さらに量子の世界の勉強を進めてみましょう!
「軌道関数」という言葉を聞くと、ただの波動関数の一部のように感じるかもしれません。ただ、軌道関数は特に電子がどの空間にいる可能性が高いかを具体的に示すため、化学でも大活躍しています。面白いのは、軌道関数の形がs軌道やp軌道のように球やダンベルの形をしていることで、これはまさに電子の“住んでいるお部屋”を表しているんです。
中学生の頃、理科の授業で「電子の軌道は丸い形」と習ったことがあるかもしれませんが、それは軌道関数の形を簡単にした説明です。実はこれらは数学的には波動関数の特定のタイプで、電子の“確率の分布図”を意味しています。理科好きの人は、こういう深掘りをするとさらに面白くなりますよ!
前の記事: « 【初心者向け】固有状態と量子状態の違いをわかりやすく解説!