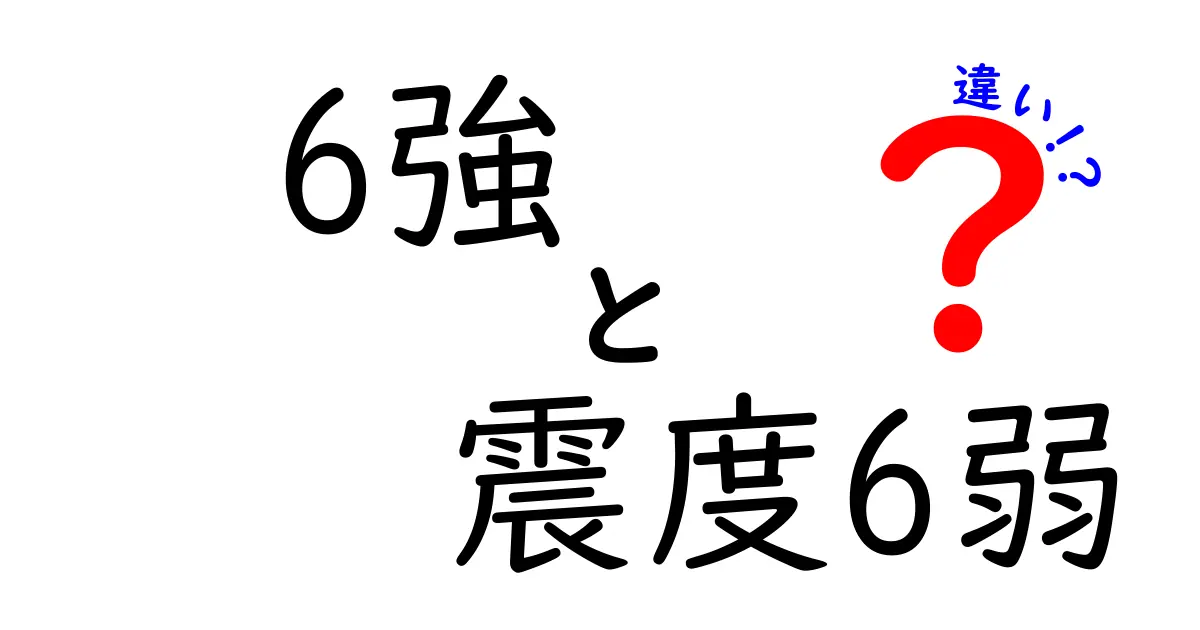

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
震度6強と震度6弱の違いとは?基本的な理解を深めよう
<まず、震度とは日本で使われている地震の揺れの強さを示す指標の一つです。震度は0から7まで分かれており、数字が大きくなるほど揺れが強くなります。
震度6弱と震度6強は、どちらも非常に強い揺れを表しますが、揺れの激しさや被害の度合いに違いがあります。
震度6弱では建物の壁や窓にひび割れが起きることがあり、耐震性の低い建物では倒壊の危険性も高まります。一方、震度6強ではほとんどの建物で激しい揺れを感じ、多くの建物で倒壊や大きな損壊が発生する可能性が高くなります。
つまり、震度6強は震度6弱に比べてかなりの差があり、被害の予測や対策も変わってきます。中学生の皆さんでも、揺れの強さが数字で分かれていることを理解しておくと、地震に備える意識が高まります。
震度6弱と震度6強の揺れの違いを表で詳しく見る
<| 震度 | 揺れの特徴 | 建物や人への影響 | 被害の例 |
|---|---|---|---|
| 震度6弱 | 非常に強い揺れで体のバランスがとりにくい | 耐震性の低い建物で一部損壊やひび割れが起こりやすい 人は立っているのが困難 | 家具の転倒や壁のひび割れ |
| 震度6強 | 激しい揺れでほとんどの人が動けなくなる | 多くの建物で大きな損壊や倒壊の危険性があり 日常生活は大きく乱れる | 建物の倒壊、道路や橋の破損 |





















