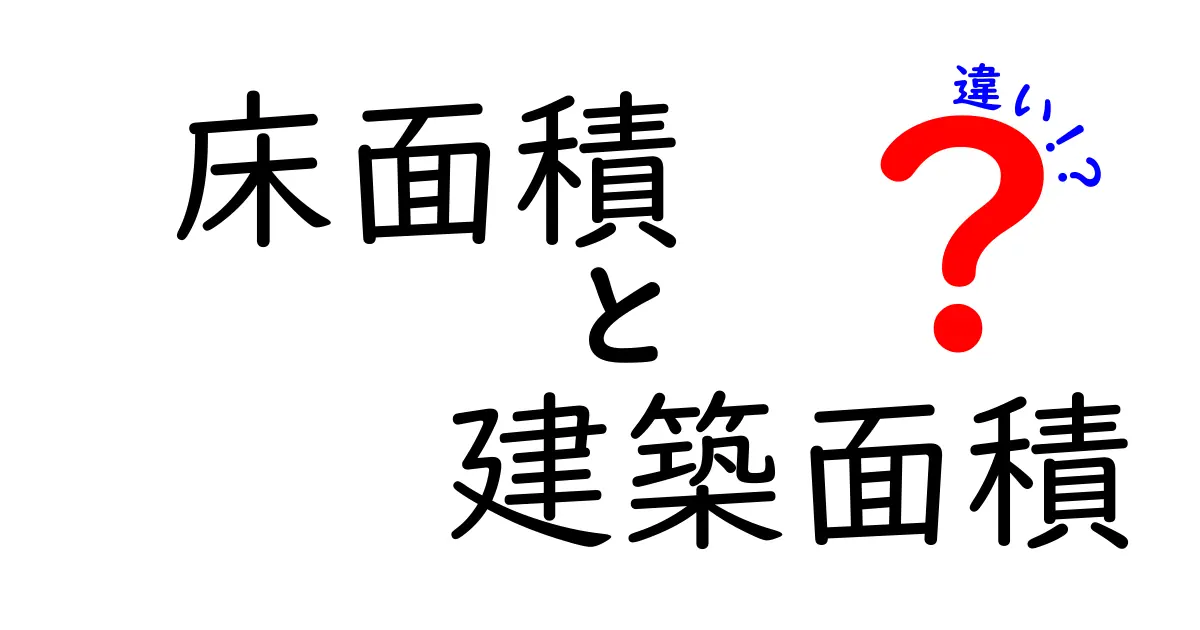

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
床面積と建築面積、そもそも何が違う?
住宅や建物の面積を表す言葉として、よく「床面積」と「建築面積」という言葉を耳にします。
でも、この二つは似ているようで実は全く違うものなのです。
混乱しやすいので、まずは基本からしっかり理解しましょう。
床面積とは、家や建物の各階の内部の床の面積を合計したものです。
つまり、1階、2階、3階といった階ごとの床面積を全部足した値を指します。
住む場所や使う場所としてのスペースの広さを表しているんです。
一方、建築面積とは、建物を真上から見たときに地面に接している部分の面積のこと。
建物がどれくらいの土地を占めているか、つまり敷地に対する影響の大きさを示します。
高さや階数は関係なく、その建物の footprint(フットプリント)とも言えます。
このように、床面積は建物の中の使える空間の広さを示し、建築面積は建物が土地にどれくらいの面積で建っているかを示しています。
床面積と建築面積をわかりやすく比較してみよう
この二つの違いをもう少しわかりやすくするため、実際のイメージで比べてみましょう。
例えば三階建ての家の場合、1階が50平方メートル、2階も50平方メートル、3階も50平方メートルだとします。
床面積は、1階+2階+3階の全部の床面積を足すので、
50+50+50=150平方メートルとなります。
一方、建築面積は建物の敷地に接している部分、つまり1階の床面積とほぼ同じで50平方メートルです。
2階や3階の面積は建築面積には影響しません。
このことからわかるのは、床面積は使える床の合計の広さ、建築面積は土地に建っている大きさであるということです。
建築基準法や用途地域の規制では、この建築面積に基づいて敷地の利用制限が決められる場合が多いです。
わかりやすくまとめると以下の表のようになります。
| 項目 | 床面積 | 建築面積 |
|---|---|---|
| 意味 | 建物の各階の床の広さの合計 | 建物が敷地に接している面積 |
| 計算方法 | 階ごとの床面積を全て足し合わせる | 建物の水平投影面積(真上からの敷地に接している部分) |
| 関係する規制 | 延床面積制限など | 建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合) |
| 利用イメージ | 使える床の面積全体 | 敷地に占める建物の大きさ |
なぜ違いを知ることが重要なの?
床面積と建築面積はどちらも建築や不動産で重要な指標ですが、意味が違うため正しく理解しないとトラブルのもとになります。
例えば、建ぺい率は敷地面積の何パーセントまで建物を建ててよいかを規制したものです。
その計算に使われるのは建築面積です。
ですので、建築面積が大きい建物は敷地に対して占める割合が高く、建てられる面積の上限に近づきやすいのです。
一方で、床面積は住宅の使いやすさや快適さ、さらに固定資産税の額にも影響します。
大きい床面積はたくさんの部屋や広い空間を意味しますが、その分税金も高くなる場合があります。
こうした理由から、設計段階から両方の面積の意味をちゃんと押さえておくことが大事です。
業者との話でも混同せずに正しく伝えることで、理想の家づくりやトラブル回避につながります。
このように「床面積」と「建築面積」という似た言葉ですが、その違いがわかると建物の全体像や使い勝手、土地利用のルールを正しく理解できるようになります。
ぜひ、覚えておきたい重要ポイントです。
建築面積という言葉、実は土地にどれくらい面積を取るかを表すだけで、建物の高さや階数は関係ないんです。
だから、3階建てでも1階部分の建築面積が小さければ、その建物の建築面積は小さいまま。
でも床面積は全部の階の広さを足すため、3階建てならかなり大きな数値になります。
この差を知らずにいると、土地の規制や税金計算で戸惑うことも。
建築面積は敷地の利用ルールを決める大切な指標、と覚えておくと便利ですよ!





















