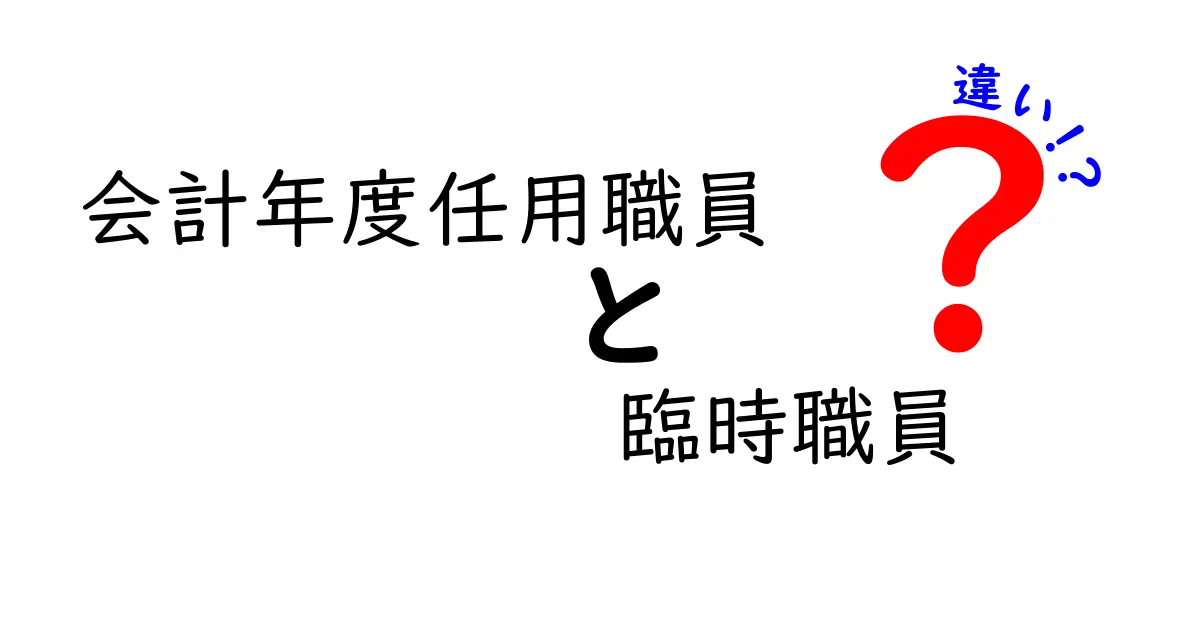

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
会計年度任用職員と臨時職員の基本的な違いとは?
公務員の働き方にはさまざまな種類がありますが、中でも会計年度任用職員と臨時職員という言葉をよく聞きます。両者は似ているようで実は働き方や身分、契約内容に違いがあります。
まず会計年度任用職員は、国や自治体などで1年間の会計年度ごとに契約が結ばれる職員のことです。2020年度から新たに設けられた制度で、より安定的な雇用を目指しています。
一方、臨時職員は、期間が特に決まっていないことも多く、限られた期間や特定の仕事のために雇われる職員です。例えば、季節限定のイベントや急に手が足りない時の補助的な役割をこなします。
このように会計年度任用職員は1年間の契約を基本とし、雇用の安定を重視しているのに対し、臨時職員はより短期的・臨時的な性質を持っています。
雇用期間や給料制度の違いをわかりやすく表で比較
両者の特徴を具体的に掴むために、雇用期間、給与体系、労働条件の違いを表にまとめました。
| ポイント | 会計年度任用職員 | 臨時職員 |
|---|---|---|
| 契約期間 | 1会計年度(通常4月~翌年3月)単位で契約 | 数日~数ヶ月など短期的な契約が多い |
| 給与体系 | 時給制が基本だが、地域や自治体により異なる | 時給制や日給制で不定期なことが多い |
| 福利厚生 | 社会保険加入あり。一定の福利厚生利用が可能 | 加入対象外となる場合が多い |
| 雇用の安定性 | 比較的安定。継続契約の可能性あり | 不安定で、必要なときだけ雇用される |
| 仕事内容 | 一定期間の行政補助や事務作業など固定された仕事が中心 | イベント補助や急な人手不足の補助が多い |
なぜ制度変更があったのか?背景とメリット・デメリット
実は2018年まで臨時職員制度が多くの自治体で使われてきましたが、働き方改革や雇用の安定化を目指して2020年から会計年度任用職員制度が導入されました。
メリットとしては、会計年度任用職員は契約更新がしやすく安心して働ける点です。加えて社会保険も適用されるので生活の安定につながります。
ただし、行政手続きが増えることや人件費の増加で自治体の負担が大きくなるデメリットもあります。一方で臨時職員は手軽に雇用できるため急なニーズには対応しやすいのが特徴です。
制度変更の背景には、非正規雇用の労働環境の改善と公務の質の維持向上があると言えます。
「会計年度任用職員」という言葉、なんだか堅苦しく聞こえますよね。実はこれ、以前の臨時職員制度の改善バージョンなんです。特徴は、1年単位で契約が結ばれるので、前よりも雇用が安定しているんですよ。社会保険にも入れるので、安心して働けるのが大きなポイントです。ちょっとしたことですが、こうした制度の違いは働く人の生活に影響を及ぼすので、知っておくと役に立ちますよ!
前の記事: « 事務職員と教員の違いとは?仕事内容・役割・やりがいを徹底解説!





















