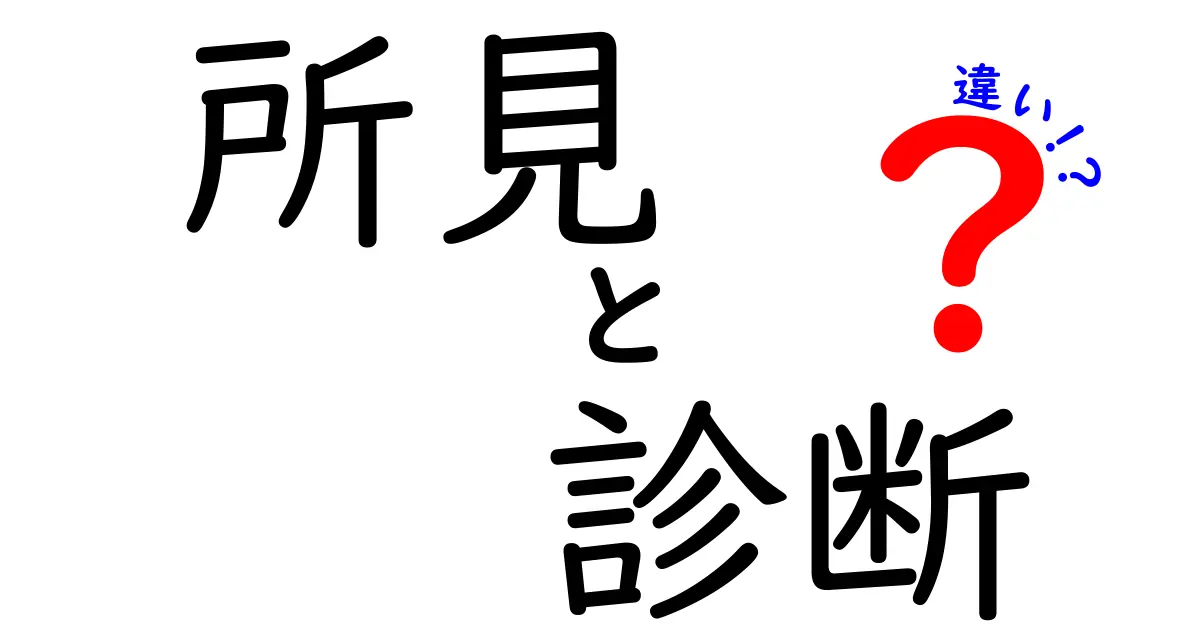

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに
皆さんは「所見」と「診断」という言葉を聞いたことがありますか?
医療の現場や健康について調べていると、これらの言葉がよく出てきますが、実は意味がかなり違うんです。
この記事では、中学生でも理解できるように、所見と診断の違いをわかりやすく解説していきます。
どちらも病気や体の状態を調べるときに使われますが、その役割や内容は違うので、しっかり覚えておきましょう。
所見とは何か?
まずは所見の意味について説明します。
所見とは、医師や看護師が患者さんの体を調べたときに見つけられる観察結果のことです。
例えば、体温を測った結果や、皮膚の色、心臓や肺の音など、身体の様子を調べて分かったことが所見です。
これは検査や触診、聴診(音を聞くこと)などで得られる情報で、患者さんの体の状態を客観的に記録したものと言えます。
所見が大事なのは、医療スタッフが患者さんの状態を理解し、適切な治療や判断に役立てるためです。
つまり、診断をするための「材料」となるデータですね。
病気の有無を判断する前の、最初の段階の情報です。
わかりやすく言うと、所見は「体からのサイン」のようなものです。医師はこのサインをもとに考えをまとめ、診断へ進んでいきます。
診断とは何か?
次に診断について説明します。
診断とは、所見や検査結果をもとに医師が出す病名や症状の名前、病気の状態についての判断をいいます。
つまり、診断は「何の病気か」「どんな問題があるのか」を判断することです。
例えば、熱があって咳が出るという所見をもとに、医師は「かぜ(風邪)」という診断をするかもしれません。
または血液検査や画像検査などの結果を総合して、最も合う病名を決める作業でもあります。
診断は、正しい治療を選ぶための重要なステップです。
診断が間違っていると、治療もうまくいきません。だから医師は慎重にいくつもの所見や検査をもとに判断します。
つまり、診断は病気や問題を特定するための「最終的な結論」と考えていいでしょう。
所見と診断の違いを表で比較!
| 項目 | 所見 | 診断 |
|---|---|---|
| 意味 | 患者の体の状態や異常を観察した結果 | 所見や検査結果をもとに病気や症状を特定する判断 |
| 内容 | 体温、心音、皮膚の状態など具体的な身体の情報 | 病名や症状の名前、病気の種類 |
| 役割 | 診断のもとになる情報 | 治療方針を決めるための結論 |
| 担当者 | 主に医療従事者が観察・記録 | 医師が総合的に判断 |
まとめ
まとめると、所見と診断は似ているようで大きく違う役割があります。
所見は患者の体の状態を客観的にみて記録した観察結果で、診断はそれらの所見や検査をもとにした病気や問題の特定です。
どちらも医療の現場でとても重要な情報ですが、所見はあくまで材料・データで、診断はその材料から導き出された答えと言えます。
この違いを理解しておくと、病院での説明や健康情報に接したときに混乱しにくくなります。また家族や友人の体調を心配するときも役立ちますよ。
ぜひ覚えておいてくださいね。
今回は「所見」について少し掘り下げてみましょう。
医療の現場では、所見は体からのたくさんの“サイン”を集めたもの。
例えば皮膚の色や腫れ、聴診器で聞こえる音。これらは異常があるかどうかを判断する最初のヒントなんです。
でも、実は医師によって所見の捉え方や記録の仕方が少しずつ違うこともあります。
だからこそ、正確な所見を集めるためには時間をかけて丁寧に観察することが大切。
所見は病気の答えではなく、答えを導くためのキーなんですね。
前の記事: « 感想文と鑑賞文の違いとは?わかりやすくポイントを解説!





















