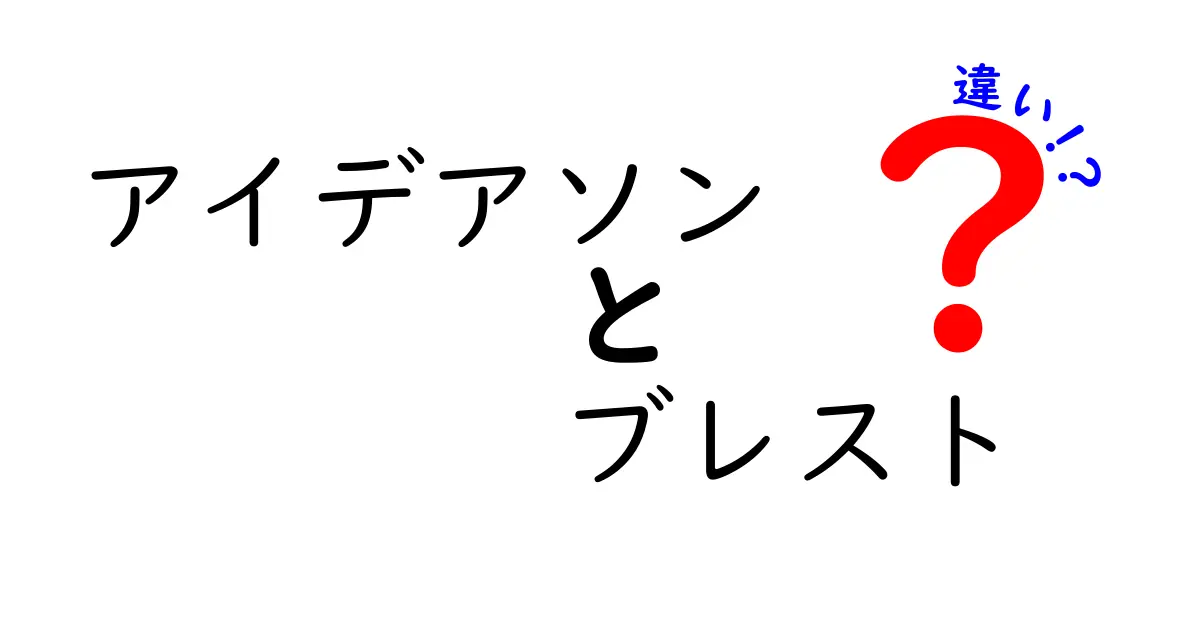

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
アイデアソンとブレストの違いを徹底解説!いつ使うべきかを徹底比較
アイデアソンとブレストは、どちらも新しい発想を生む場ですが、目的や進め方が大きく異なります。まず大事なのはゴールの設定と成果物の形です。アイデアソンは、課題を設定し解決策を具体化することを目的に、複数の視点を集めて実行可能性を検討します。ブレストは、発言の自由さと量を重視し、数多くのアイデアを出すこと自体を楽しむ場です。これだけを見ても、二つは別物だとわかりますね。
ブレストの良さは気楽さと創造性の解放にあります。
人は初めは緊張しますが、ルールで safe な雰囲気を作れば、誰でも思いつきを言いやすくなります。たとえば学校の課題や部活動の新しい活動案を出すときに向いています。
ただしアイデアを数だけ追いかけすぎると、後で整理するのが大変になることもあるので、結果の活用を忘れずにしておくことが大切です。
一方アイデアソンは、特定の課題を解決する具体的な案を短時間で作る作業です。ファシリテーターが進行を管理し、案の数よりも質と実行の見通しを重視します。ここでの成果物は、実行可能性の高いアイデアの羅列から、実行計画へとつなぐロードマップへと昇華されます。参加者は専門性が異なる人が集まり、
多様な視点がぶつかり合うことで新しい気づきを得るのが特徴です。
実際の現場では、アイデアソンは新規事業の種探しやサービス設計の初期段階に適しています。ブレストは、問題設定が曖昧な時や、まずはアイデアの量を集めてから分析したい時に有効です。どちらを選ぶかは、解決したい課題の性質と組織の状況次第です。
大事なのは、場の雰囲気を壊さないことと、成果物の活用を前提に計画することです。もし時間が限られているなら、アイデアソンの短縮版を試してみるのも良いでしょう。
アイデアソンの特徴と流れ
アイデアソンは、前準備として課題と評価基準を決め、参加者を役割別に配置します。開始時にはアイスブレイクを行い、課題の背景とゴールを共有します。次にブレインストーミングのセッションを複数回行い、アイデアの質を高めるための視点の切替を取り入れます。アイデアはすべて受け入れる雰囲気で進行し、
後半にはアイデアを絞り込み、評価軸に基づいて優先順位をつけます。最後に実行可能なロードマップを作成し、誰が何をいつまでに行うかを明記します。これにより、成果物は単なるアイデア集ではなく、行動へと結実します。
ブレストの特徴と流れ
ブレストは、まずルールを共有します。批判を避け、自由な発想を受け入れる雰囲気づくりが第一歩です。次に発想を促す技法を使い、連想の連鎖を広げることを意識します。アイデアは量を重視するので、
初期段階では奇抜な発想も歓迎されます。評価は後回しにしがちですが、適度な段階で「このアイデアはどう使えるか」を考えると良いでしょう。ブレストの場では、発言者と聴く側の関係性が重要で、全員が平等に発言できる環境を作ることが成功の鍵です。
現場での使い分けと実例
実務での使い分けとしては、サービスの新設計にはアイデアソン、日常的な改善の発想にはブレストが適しています。例えば教育現場では、新しい学習ツールのアイデアを出す場合はアイデアソン、授業の改善案を出すときにはブレストを選ぶと効率的です。企業では、戦略の大方向が決まっていない段階でアイデアソンを実施し、特定の分野のアイデアを深掘りする際にはブレストを使います。なお、成果物としてのロードマップや提案書を作成すると、会議の後の実行性が高まります。
双方の手法には共通点も多く、チームの信頼感と共通言語を育てる点が大切です。
表で見る違いと使い分けのポイント
アイデアソンとブレストの違いは、表だけでは伝えきれないニュアンスも多いですが、ここでは要点をまとめます。主なポイントは、目的の違い、成果物の形、参加者の役割、時間の使い方です。アイデアソンは実行可能性の検討まで含み、ブレストは発想の量を優先します。現場での使い分けは、課題の性質と組織の成熟度に左右され、どちらか一方を単独で使うよりも、二つの手法を組み合わせる方が安全で効果的です。
また、ファシリテーションの工夫次第で、発言の偏りを減らし、全員のアイデアを拾える基盤を作れます。
まとめと実践のコツ
アイデアソンとブレストは、共に新しい発想を生む強力な道具ですが、使い方次第で成果は大きく変わります。
覚えておきたいのは、ゴールとルールを最初に決めること、参加者の役割を明確にすること、そして<成果物をすぐに活用できる形で残すことです。これらを意識すれば、学校の課題や部活、企業の新規事業開発など、さまざまな場面で役立つはずです。
アイデアソンの場では、自由な発言が雁字搦めにならない工夫が大切です。初対面同士でも、ルールを守ることで、誰もが意見を出しやすくなります。私は以前、先生が進行役だったアイデアソンで、最初は沈黙が続きましたが、時間制限と批判禁止のルールを徹底した瞬間から雰囲気が変わり、多くのアイデアが飛び交うようになりました。最終的に生まれた案の中には、学習ツールの新しい使い方があり、実際の授業で試してみたところ、生徒の興味関心が高まり学習効果も上がりました。





















