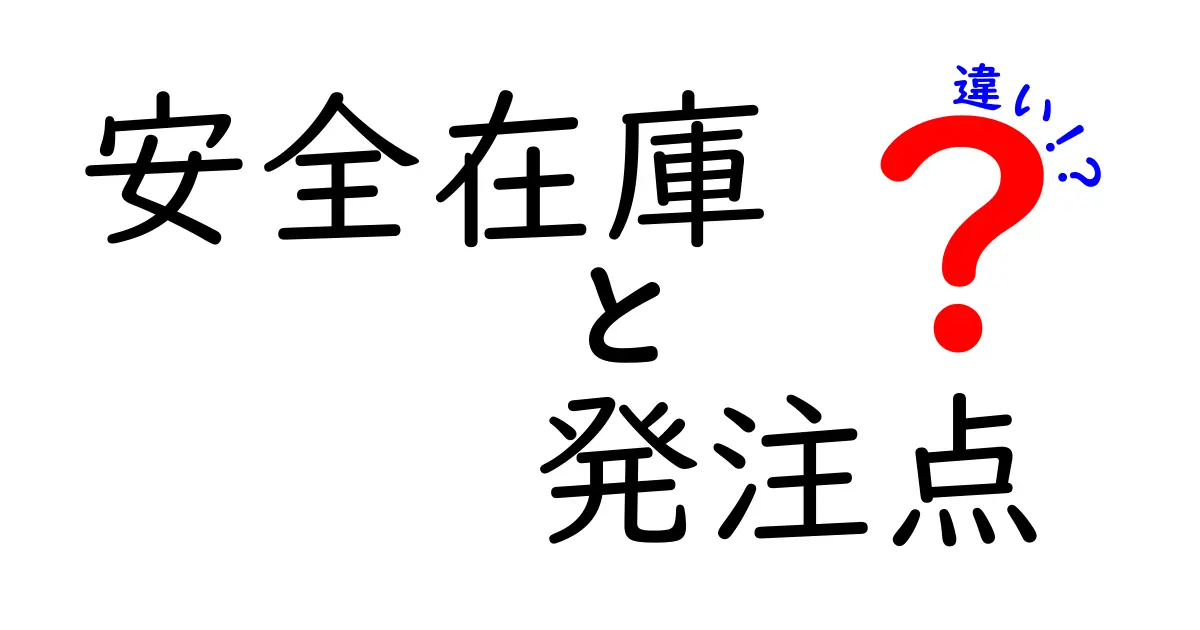

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
安全在庫と発注点の違いを徹底解説:中学生にもわかる実務のポイント
この話のポイントは「安全在庫」と「発注点」が別物であり、同時に使うことで欠品を減らし、過剰在庫を抑えるという点です。安全在庫は「欠品を避けるために常に手元に確保しておく最小の数量」、一方の発注点は「この数量になったら発注を起こす」というトリガーのことです。混乱しやちなのは、両者が同じ目的(欠品防止)に向かいながら、計算の根拠となる指標や影響範囲が異なる点です。リードタイム(仕入れにかかる時間)や需要の変動性をどう考えるかで、必要な安全在庫の量は変わります。
このテキストでは、具体例と数字を用いながら、中学生でも理解できるように「何をどう計算すれば良いか」を順番に紹介します。
まずは用語を定義し、その後に実務での使い分け、最後にミスしがちなポイントと改善のコツを紹介します。
安全在庫とは何か
安全在庫は在庫を過不足なく保つために設定する「予備の在庫」
。需要が予想より多くなる時や、供給が遅れた場合にも対応できるようにするための仕組みです。例えば、今日は日常の需要が1日あたり10個、納品にかかるリードタイムが3日だとします。
この場合、通常の平均在庫が30個程度で足りますが、急な需要増や遅延を見越して安全在庫を追加します。安全在庫の量は、過去のデータから「どれくらいの変動があるか」を見て決めることが多く、需要の季節性やサプライヤーの納期遅延リスクなどを考慮します。
つまり、安全在庫は外部の変動から在庫を守るクッションのような存在です。
この考え方を正しく使えば、欠品リスクを下げつつ、過剰在庫を抑えるバランスが取りやすくなります。
発注点とは何か
発注点は「この数量になったら発注を出す」という"きっかけ"を作る基準です。
発注点は通常、安全在庫と実際の需要・供給の動きから計算されます。計算にはよく使われる式があり、基本形は「発注点=安全在庫+需要の予想分+リードタイム中の欠品リスク分」などです。
ここで重要なのは「発注点の設定を動的に変えられるかどうか」です。需要が増えたときは発注点を上げ、供給が安定しているときは下げることで、在庫コストと欠品の両方をコントロールできます。
また、リードタイムが長い場合は発注点を高く設定するなど、現場の実感とデータを組み合わせることが重要です。
違いを実務でどう使い分けるか
実務では、安全在庫と発注点は別々の役割を持ちながら、互いに補完します。
例を挙げると、週単位での需要が安定している場合は安全在庫を低めに設定し、発注点のラインを小刻みに調整するだけで済むことがあります。一方、季節変動が大きく、納期遅延のリスクが高い場合には、安全在庫を増やして欠品リスクを下げつつ、発注点を早めに設定してタイムラグを減らす工夫が必要です。
また、データの活用も大切で、過去の販売数、リードタイム、欠品件数を集計して需要予測の精度を上げると、両方の値をより適切に決められるようになります。
このように、安全在庫と発注点は適切なバランスを保つことが成功の鍵です。
安全在庫と発注点の比較例
ある日の放課後、友達とチャイムの音を聞きながら在庫の話をしていた。僕は机の上の在庫カードを指して“安全在庫って体の保険みたいなものだよね。必要以上に持つとコストが上がる、でも足りなくなると困る。だから過去のデータとリードタイムを合わせて“いくら確保すれば安心か”を計算するんだ。”と話す。友達は頷き、「発注点はその安全在庫を超えた時に発注を出す合図みたいなものだね」と返す。私たちは学校行事の準備品の話にも置き換えて、需要の波や遅延リスクを想像してみる。データが示す“傾向”を見ながら、現場の工夫で在庫とコストのバランスを取る。そんな雑談の中で、在庫管理の考え方が少しずつ身についていくのを感じた。





















