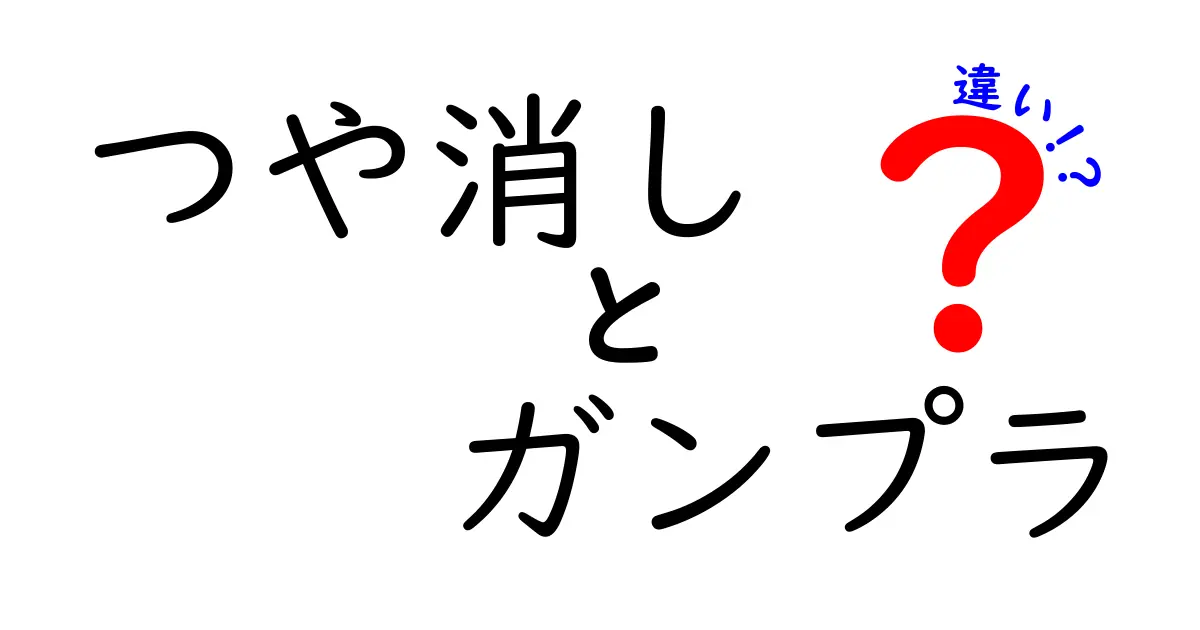

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
つや消しの基本とガンプラでの使い方
つや消しとは、塗装表面の光沢を抑え、マットな質感に見せる仕上げのことです。ガンプラの世界では、戦闘機の金属感や戦跡の雰囲気を再現する際に使われます。
つや消しだけでなく、半つや・光沢など、仕上げの種類を理解することが大切です。
本稿では、つや消しの基本、作例、注意点、そして表ごとの比較を通じて、初心者にも分かりやすく解説します。
まず知っておきたいのは、つや消しは「塗装の仕上がりを落ち着かせる」役割であり、ウェザリングやディテールの視認性を整えるのに適しているという点です。
実際のガンプラ製作では、塗装前に「下地→ベースカラー→クリアコート(光沢)→ウェザリング→つや消しクリアコート」という流れを取ることが多いです。
ここで理解しておくべきポイントは以下の3つです。まず第一に、つや消しは「表面の平滑さだけでなく、光の拡散を変えて陰影を自然に見せる」効果があります。第二に、塗装方法にはエアブラシとスプレー缶の二つの選択肢があり、それぞれに適した溶剤・希釈・乾燥時間があります。第三に、ウェザリングを行う場合は、つや消しの前に光沢のコートを一枚挟むと、汚れのにじみや色の入り方がきれいに出ます。
つや消しの塗装を成功させるコツのひとつは、薄く均一な膜を何度も重ねることです。厚塗りを急ぐと、気泡やホワイトミストの原因になり、仕上がりが白っぽくなることがあります。特にガンプラは細部が多く、厚みのムラがディテールを邪魔します。乾燥時間も重要で、冬場は乾燥に時間がかかるため、日光の当たる風通しの良い場所で、十分に乾燥させてから次の作業に移ることが推奨されます。
実際の作例として、写真写りを意識したマット仕上げの戦車風ガンプラを作るとき、下地のベースカラーを均一に塗ることと、クリアコート後のウェザリングの組み合わせが肝になります。ウェザリングを行う前に、クリアコートを吹いて保護しておくと、汚れがはみ出さず、作業後の修正が容易になります。さらに、マット同士の段差を減らしたい場合は、最後に微細な粒子のつや消しトップコートを軽く重ねる方法も有効です。
仕上がりの雰囲気を見極めるには、撮影環境も大切です。自然光での写真は影の入り方が重要で、マットの質感が分かりやすくなります。ライトを複数用意して角度を変え、陰影の出方を確認しましょう。
まとめとして、ガンプラのつや消しは「目的に合わせた膜の厚みとコートの順序」を理解することが成功の鍵です。原理を知り、手順を守り、細部まで観察することで、キットの魅力を最大限に引き出せます。実践の中で、 小さな実験を繰り返し、テストピースで感覚を覚えると、失敗を減らせます。これらのポイントを頭に入れておけば、初心者でも美しいマット仕上げを作ることができます。
つや消しの種類と違い、選び方と実践例
つや消しにはいくつかのタイプがあり、それぞれの特性に合わせて使い分けることが大切です。水性と溶剤系、完全マットと半つや、そして吹き方のコツなど、選ぶ際には目的をはっきりさせることが重要です。水性は取り扱いが楽で初めての人にも向いており、においも控えめです。溶剤系は耐久性が高く、厚みのある膜を作りやすい反面、取り扱いには換気と適切な保護具が必要です。
また、乾燥時間や粒子の細かさも仕上がりに大きく影響します。粒子が細かいと表面が滑らかになり、粗い粒子は表面の質感を強く出します。目的に応じて、細かな粒子のものを選ぶとウェザリングの表現が美しく決まります。
実践例として、ガンプラで具体的なマット感を得るには、まずベースカラーを整え、下地として光沢クリアを一枚挟んでおくと、後のウェザリングの乗りが安定します。次に、つや消しを薄く吹いて陰影を整え、必要に応じて半つやを混ぜることで、写真映えするテクスチャを作り出します。ウェザリングを多用する場合は、最終的にもう一度つや消しを吹くと、汚れのにじみが自然に見えやすくなります。
購入時のコツとしては、テストピースを用意して、薄く吹いたときの乾燥時間と仕上がりを必ず確認することです。経験を積むほど、微妙な厚みの調整ができ、作品ごとに最適な膜厚を掴めるようになります。
ここまで理解すれば、つや消しは単なる「塗装の仕上げ」ではなく、作品の雰囲気を決定づける重要な要素であることが分かります。強調したいのは、薄く・均一に・何度も重ねるという基本と、作品ごとに適切な膜厚を探る探究心です。これらを守れば、初心者でも質感の高いガンプラを作ることができ、写真映えする完成品へと近づきます。
ねえ、つや消しって実は「仕上がりの雰囲気を決める最後のひと手間」くらいの感覚で使うと、失敗が少なくなるんだ。僕がガンプラを作っていて気づいたのは、同じキットでも、つや消しを吹くかどうかで陰影の見え方が全然違うこと。つや消しを正しく使えばウェザリングの汚れや塗膜の傷が自然に映え、写真映えも良くなる。逆に、厚く吹きすぎると表面が白っぽくなることがあるから、薄く何度も重ねるのがコツ。ウェザリング前には必ずクリアコートを挟み、後から汚れを乗せても修正しやすくしておくと安心。初めての人は、まずテストピースで感覚を掴み、完成版の前に小さな部品で練習してから本番へ進むと良いよ。
次の記事: バフと研磨の違いを徹底解説|仕上がりと作業手順をわかりやすく比較 »





















