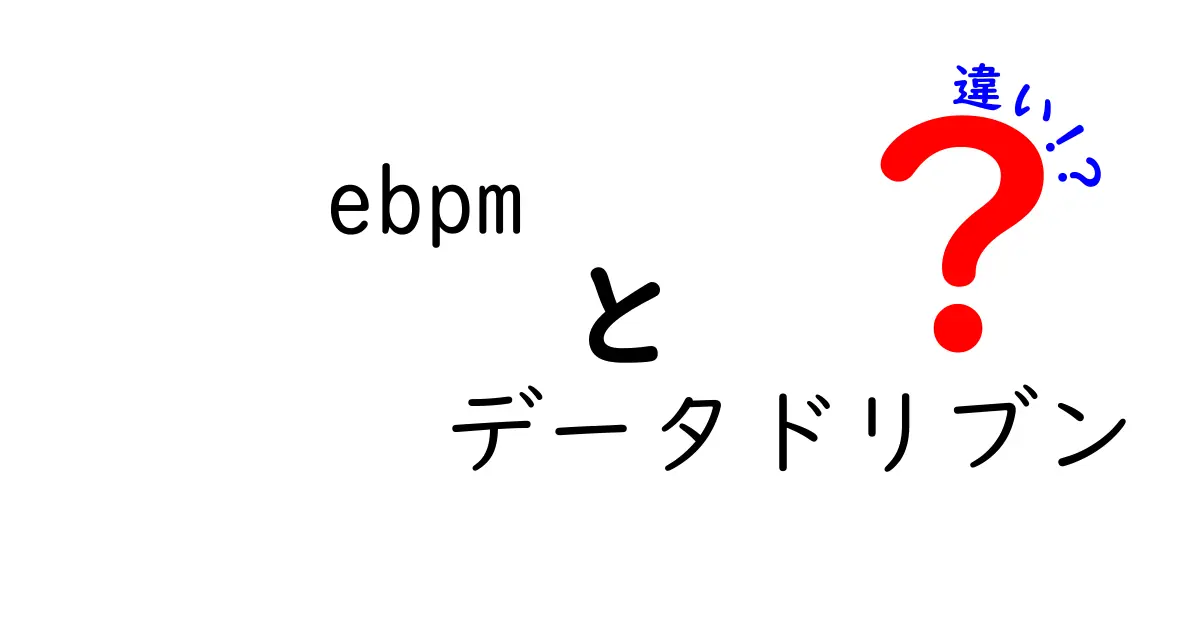

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ebpmとは何か?基礎を固めよう
EBPM とは Evidence-Based Policy/Management の略称で、エビデンス(証拠) を根拠に意思決定を行う考え方です。医療や行政、教育、ビジネスの現場でも使われ、データや研究結果をそのまま「結論」にするのではなく、信頼できる証拠の質、適用の前提条件、リスク、不確実性を整理して、具体的な行動へと翻訳します。
例えば、学校で新しいカリキュラムを導入する際、まず過去の研究から効果の大きい要素を見つけ出し、小規模な試験を行い、データを分析してから本格導入を決めます。EBPMは「データを集めればすぐ答えが出る」という安易な考えを避け、データの質と解釈の正確さを重視します。ここで重要なのは、意思決定の責任者が誰か、どの程度の不確実性を許容するのか、結果をどう検証するかを明確にすることです。
データドリブンとは?データを活かす考え方
データドリブンは「データに基づいて意思決定をする」アプローチです。数字・傾向・指標を中心に、日常的な業務にも適用します。データは単なる記録ではなく、行動の指針として使われます。A/B テスト、ダッシュボード、KPI管理などが具体例です。組織文化としてデータリテラシーを高め、誰でもデータを読み解ける環境を作ることが大切です。
データを活用する際には、データの品質(正確さ・完全さ・最新性)、収集の方法、分析の透明性を確保します。データは現場の感覚を否定するものではなく、感覚と組み合わせて「なぜそうなるのか」を説明する手がかりです。例えば売上が伸び悩んだ理由を、訪問数・購入率・リピート率といった指標で追跡すると、原因の仮説を立てやすくなり、改善案を具体化しやすくなります。
ebpmとデータドリブンの違いと使い分け
両者は「データを活用する」という点で共通しますが、出発点と重視する問いが異なります。EBPMは「証拠の質と適用条件」を最優先にし、長期的な影響と不確実性の評価を重視します。対して、データドリブンは現場の実践で生まれるデータを用いて、日々の意思決定を素早く改善することを目指します。以下の表は違いのポイントを簡潔に示します。
また、実務での使い分けとしては、戦略の大枠を決める場面ではebpmを活用し、日常の運用や改善案の検証にはデータドリブンを使うのが効果的です。
両者は互いを補完する関係であり、どちらか一方に偏りすぎないことが成功の鍵です。
友だちとコーヒーを飲みながら、ebpmとデータドリブンの話を深掘りしてみたんだ。結論から言うと、どちらもデータの力を活かして判断を良くする点では同じだけれど、出発点が違う。EBPMは証拠の質と適用の前提を丁寧に評価する考え方、データドリブンは日々の現場のデータを使ってすぐに改善を積み重ねる考え方。だから、学校の新しい授業を決めるときは、まずデータの傾向を調べ、次に研究の証拠を照合して判断するのがベスト。そうすることで現場の声と科学的根拠の両方を照らし合わせることができ、説得力のある決定につながる。





















