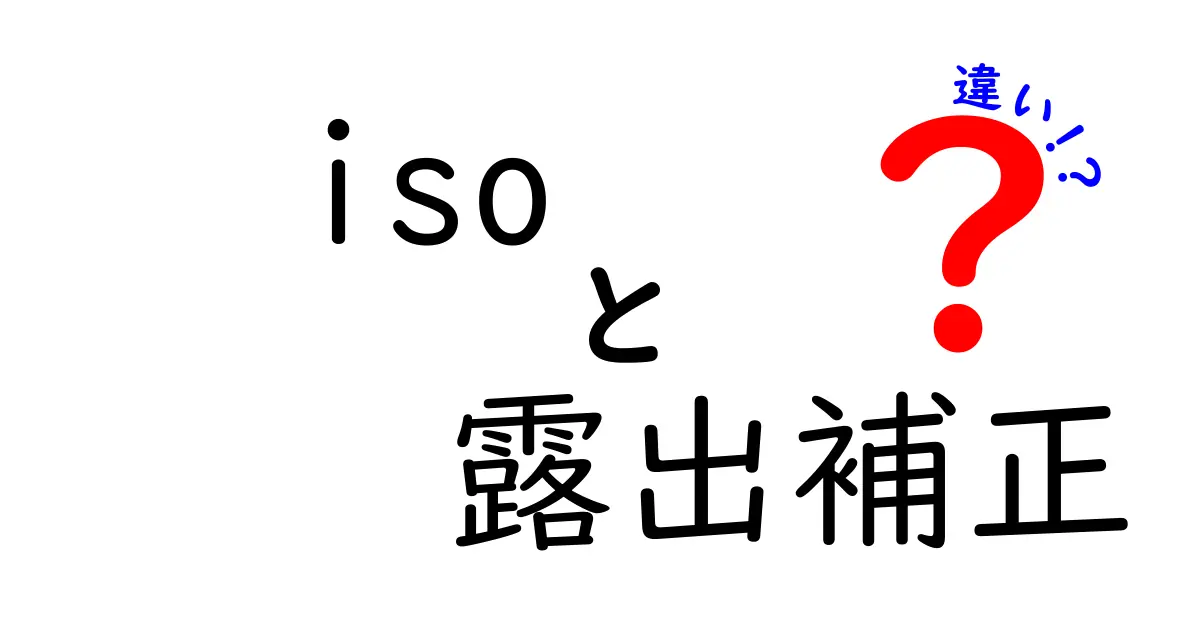

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
結論から知ろう:ISOと露出補正の違いとは?
現代の写真は、暗い場所でも明るく写したいときが多いですね。そのときよく混同されがちなのが「ISO」と「露出補正」です。これらは名前こそ似ているものの、写真を作り出す仕組みはまったく別物です。
ISOはカメラのセンサーの敏感さを表す数値で、上げれば明るくはなりますがノイズという粒子のようなざらつきが増えます。
露出補正は、写真を撮るときの“基準となる露出の判断”をカメラに指示する機能です。たとえば逆光の場面で、露出を少しだけ上げて全体を明るくするなど、設定を変えずに見た目の印象を変えることができます。
この二つを正しく使い分けると、暗い場所でも白飛びすぎない写真や、逆光の中でも被写体の表情をきちんと出す写真を撮ることができます。以下では、それぞれの基本を丁寧に解説し、最後に日常のシーンでの使い分けのコツを、具体的な数字の目安とともに紹介します。まずは「ISOとは何か」を抑え、次に「露出補正とは何か」を理解しましょう。
写真を楽しむためには、用語の意味を知ることよりも、実際に試してみる体験が大切です。
さあ、実践の扉を開けていきましょう。
ISOについての基本
ISOはセンサーの感度を表す数字です。小さいほど光をあまり取り込みませんが、ノイズは少なく、階調表現が滑らかになります。大きいほど光を拾いやすく、暗い場所でもシャッター速度を速く保てることが多いですが、粒々のノイズが出やすくなります。
実際の運用では、日中の風景写真などでISOを低めに保ち、被写体が動くときや室内・夜景のように暗い場面でISOを上げるのが一般的です。
また、現代の多くのカメラは「自動ISO」機能を搭載しており、シャッター速度と絞り値を保ちつつISOを自動調整してくれます。使い方次第で画質と露出のバランスを大きく変えることができます。
露出補正とは何か
露出補正は、カメラの測光が決めた露出を「人間の目で見た明るさ」に近づけるための機能です。露出を+1.0段にすると写真全体が明るくなり、-1.0段にすると暗くなります。
露出補正は、特に被写体が周囲より明るいか暗いかで見た目が大きく変わるときに便利です。逆光の風景では露出補正を+補正して被写体の表情を保つ、などの使い方がよく行われます。
重要なのは、露出補正は“画づくりの調整”であって、設定そのものを変えるわけではない点です。撮影後に編集で補正しなおすこともできますが、現場での判断と補正の良さを活かすと、効率よく美しい写真が得られます。
実務での使い分け
日常のシーンでは、ISOと露出補正の組み合わせを意識する場面が多くあります。室内の撮影では、ISOを最適化しつつ、露出補正で実際の被写体の明るさを整えます。晴れた日中はISOを低く抑えつつ、露出補正を必要に応じて微調整します。
夜景の場合は、シャッター速度を落とさずに被写体を明るくするためにISOを少し上げ、露出補正で画全体の印象を整えることが多いです。これらの使い分けを理解しておくと、写真の仕上がりを大きくコントロールできます。
実例1:夜景と室内の撮影
夜景や室内では光が少なくなりがちなため、ISOを適切に上げることが多くなります。例えば街の夜景を撮るときは、ISOを400〜1600程度に設定し、シャッター速度が速すぎると写真が暗く、遅すぎると手ブレが起きやすくなります。露出補正は、被写体の明るさが全体のトーンを決める場合に使います。夜景では、空の明るさと街灯の光のバランスを見て、+-1.0段程度の補正を試してみると自然な印象を得られやすいです。
このように、ISOと露出補正はそれぞれ役割が違います。ISOは画質と感度、露出補正は画づくりの指示と考えると理解しやすいでしょう。
実例2:逆光の場面
逆光の場面は、被写体が暗く写りがちですが、露出補正を使うと被写体の表情やディテールを守りやすくなります。例えば人が日陰に立っているとき、露出補正を+0.7〜+1.3段程度に設定して被写体を明るく保つと、背景の明るさを保ちつつ顔の表情をくっきり出せます。ISOは状況に応じて最小限に抑えることが多く、遮光の強い場所なら1,000程度まで上げてもノイズはそれほど目立ちません。
このように、露出補正を使い分けることで、与えられた光の条件の中で最も見せたい情報を引き出すことができます。
まとめとコツ
- ISOと露出補正は別物。 ISOは感度、露出補正は露出の判断の補正
- 実際の撮影では、状況に応じて両方を使い分けるのがコツです。光が強い場所ではISOを低く、光が少ない場所ではISOを上げる。逆光では露出補正を使って被写体を明るく保つのが有効です。
- カメラの自動設定をうまく活用することも重要です。自動ISOと露出補正を組み合わせると、手早くきれいな写真を多数撮ることができます。
友人と写真の談義をしていたある日、私はISOと露出補正の違いを丁寧に説明してみた。ISOは“どれだけ光を敏感にするか”の設計図で、上げれば夜の画は明るくなるがノイズが増える。露出補正は“この写真の明るさの雰囲気をどう見せたいか”という演出指示で、設定そのものを変えずに結果だけを調整できる。友人は「なるほど、露出補正は写真の演出の道具なんだね」と納得。私たちは実際にカメラのダイヤルを回し、夜景で露出補正を+0.7、室内でISOを400程度に設定して撮影してみた。瞬間的に画づくりの感覚がつかめ、同じ場所でも違う表情の写真が生まれることを体感した。写真は技術と感覚の両方が要ると改めて感じた。
次の記事: 小論文と説明文の違いを徹底解説|中学生にもわかる比較ガイド »





















