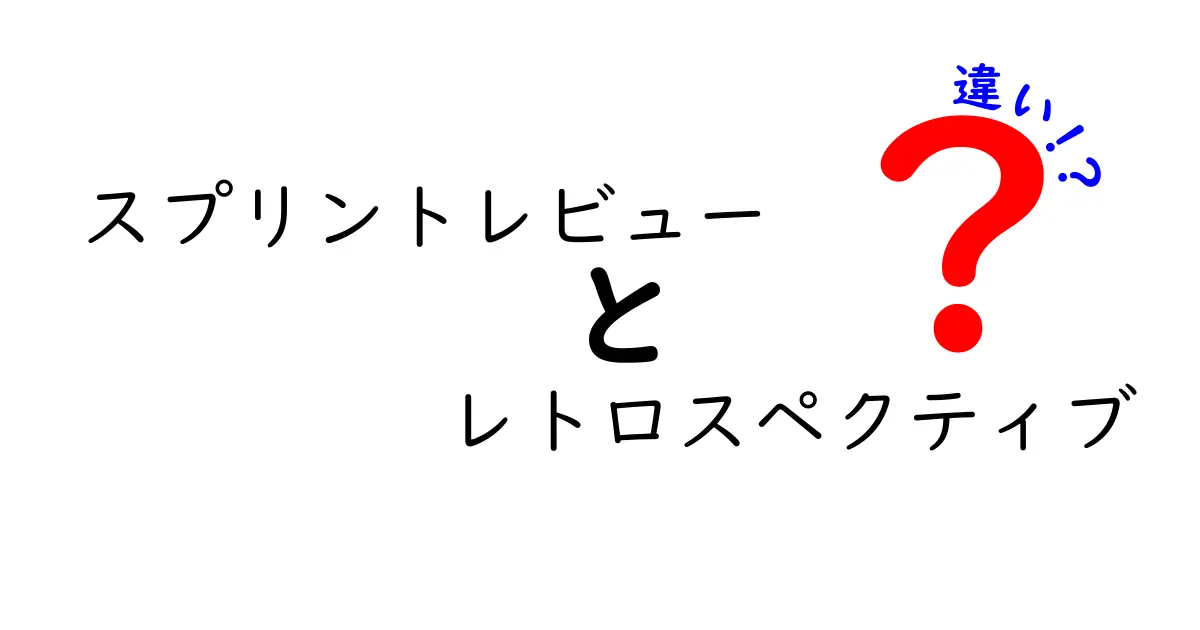

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
スプリントレビューとレトロスペクティブの基本を押さえる
スプリントレビューとレトロスペクティブは、アジャイル開発の中でよく出てくる二つのイベントです。
似ているようで役割が違い、使う場面も目的も異なります。
この違いを理解しておくと、プロジェクトの透明性が高まり、チームの改善スピードも上がります。
スプリントは通常2週間から4週間程度の期間で計画されます。
スプリントレビューはこの期間の終わりに行われ、完成した機能を実際に動く状態でステークホルダーに見せる場です。
一方、レトロスペクティブは同じ期間の終わりに行われる別の会議で、プロセスやチームの働き方を振り返る場です。
この二つは同じタイミングに連続して開かれることが多いのですが、焦点が違います。
ここで大事なポイントは、スプリントレビューが「何を作ったのか」を示す場であるのに対し、レトロスペクティブは「どう作ったのか」を改善する場だという点です。
どちらも透明性を高め、学習を促しますが、出てくるアウトプットが違います。
スプリントレビューのアウトプットは主にインクリメントの評価と次の計画へのヒント、レトロスペクティブのアウトプットは次回以降の行動計画や改善アイデアです。
スプリントレビューの目的と特徴
スプリントレビューの主な目的は、完成した機能を実際にデモして、ステークホルダーと共有することです。
この場では「どの機能が完成したのか」「どのくらいの品質で動くのか」を説明します。
参加者は開発チームに加え、プロダクトオーナー、スクラムマスター、場合によっては顧客や外部の利害関係者も含まれます。
このセッションのアウトプットには、次スプリントの方向性を示すアップデートされたバックログや、実際に提供できるインクリメントの確認が含まれます。
このイベントは透明性と信頼の確立を目的としています。
レビューの進行はデモ中心で、質問やフィードバックは歓迎されますが、過度な批判ではなく建設的な意見交換を心掛けることが重要です。
レトロスペクティブの目的と特徴
レトロスペクティブは、開発チームのプロセスや協働の仕方を改善する場です。
参加者は基本的に開発チーム全員で、ファシリテーターが進行をリードします。
このセッションのアウトプットは、次のスプリントで実行する具体的な改善アクションです。
レトロスペクティブでは「何がうまくいったか」「何を改善すべきか」「次からどう変えるか」を三つの問いで整理するのが定番です。
安全な雰囲気と心理的安全性が鍵になります。批判ではなく学習と成長に焦点を当て、遅れや失敗を共有しやすい環境を作ることが大切です。
両者の違いをどう使い分けるか具体例
具体的には、スプリントレビューは「完成して公開する成果物の場」です。
デモを通じてユーザー視点の評価を得て、次の機能追加の方向性を決めます。
対してレトロスペクティブは「作る過程の改善を決定する場」です。
この違いを理解していると、会議中に話す内容が分かれ、時間の使い方も変わります。
例えば、前回のスプリントでのデリバリーに問題があれば、次回のレトロスペクティブで原因を分析し、具体的な対策を立てます。
実務では、この二つを連携させるのが成果を最大化するコツです。
デモの情報でプロダクトの改善点を掘り下げ、改善案を次のスプリントへ繋げます。
実務での注意点とよくある誤解
実務での注意点としては、時間を厳密に区切ること、ファシリテーションを適切に行うこと、そしてアウトプットを明確に文書化することが挙げられます。
誤解の一つは「スプリントレビューは全員参加で完結するべき」という考えです。
実際には関係者の参加度や決定権の有無で、適切な参加者を選ぶことが大切です。
また「レトロスペクティブは批判の場だ」という誤解もあります。
実際には心理的安全性を守りつつ、改善点を具体的な行動に落とすことが目的です。
強調したいのは、継続的な改善を前提に、時間をかけずに小さな改善を繰り返すことが効果を生むという点です。
最後に、両方のイベントを形式的な作法として捉えず、実際の成果につなげる努力を続けることが重要です。
ねえ、スプリントレビューとレトロスペクティブの違いって、なんとなくは分かるけど、実際にはどう活かせばいいの?って思うこと、あるよね。僕も最初は混乱した。スプリントレビューは完成した“もの”をみんなに見せて、こういう機能はこう使える、こんな課題は解決します、という“結果の場”なんだ。対してレトロスペクティブは、作り方そのものを良くするための“仕組みの場”。その場で出た改善案を次のスプリントの計画に落とし込み、実際に行動に移す――これが大切。つまり、表面的に何ができたかだけを見るスプリントレビューと、どう作るかを見直すレトロスペクティブ。このふたつをセットで使うと、プロダクトはどんどん良くなるはず。実務では、デモを温かく観察してもらい、改善案を具体的なアクションに落とすことを忘れずに。時には意見がぶつかることもあるけれど、建設的な雰囲気を保つことが最初の一歩だよ。
前の記事: « の文脈違いを徹底解説:日本語の『の』が示す意味の幅と使い分け





















