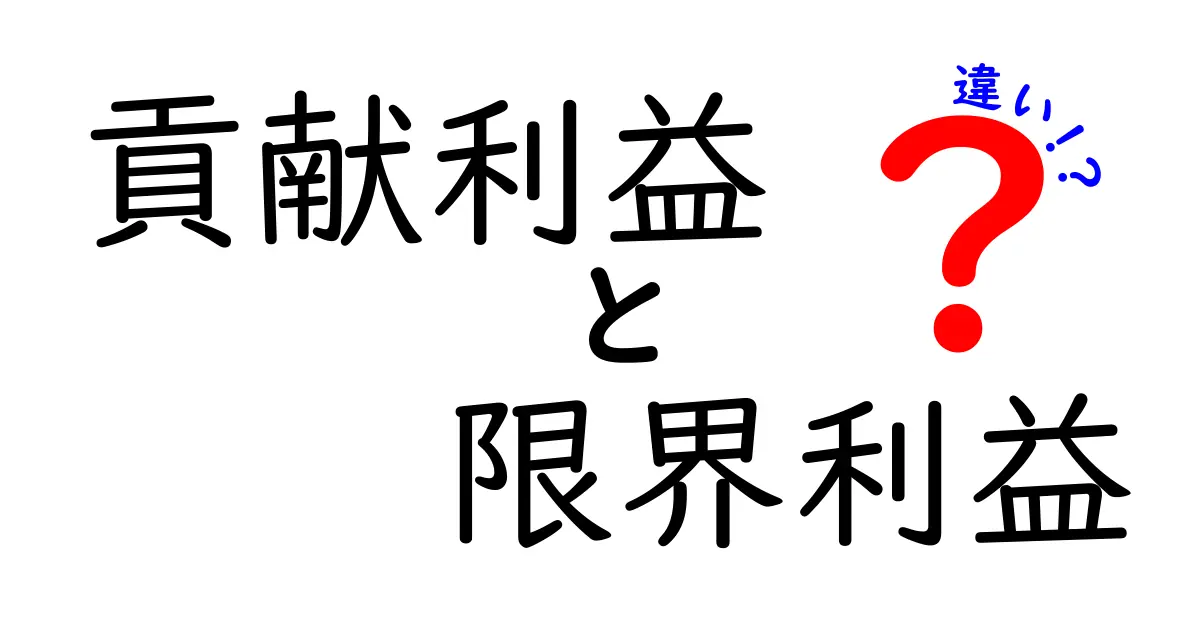

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
貢献利益と限界利益の違いを徹底解説|利益の仕組みを正しく理解して戦略を立てよう
はじめに:貢献利益と限界利益の基礎を押さえる
この二つの利益指標は、経営を回すうえでとても基本的な考え方です。貢献利益と限界利益は、似ているようで意味が少し異なり、使い分け方を間違えると意思決定を誤ることがあります。特に、商品開発や価格設定、どの製品を増やすべきかを決めるときには、この違いを正しく理解しているかどうかが結果を大きく左右します。
この記事では、中学生にもわかる言葉で、具体的な計算方法や日常のビジネスシーンでの活かし方を丁寧に解説します。
まずは用語の前提をそろえましょう。変動費と固定費という言葉を知っておくと、貢献利益の意味がつかみやすくなります。変動費は売上の量に応じて変わる費用、例えば原材料費や外注費、配送料などです。固定費は売上の量とは関係なく発生する費用で、家賃や人件費の一部などが該当します。貢献利益は売上高から変動費を引いた額であり、固定費をカバーする力を示します。
貢献利益とは何か?定義と計算方法
貢献利益は、企業がどれだけ売上から変動費を支払った後に残る“貢献できる利益”を表す指標です。 数式で書くと、貢献利益 = 売上高 - 変動費、貢献利益率 = 貢献利益 / 売上高、となります。この指標は、製品別やサービス別の利益構造を比較するのにとても役立ちます。
例えば、ある商品を100,000円で売り、変動費が40,000円かかったとします。すると貢献利益は60,000円になります。これが固定費をカバーする力の“床”となり、床を超えれば利益が出ます。ここでのポイントは、貢献利益が大きいほど固定費を迅速にカバーでき、利益が出る余地が増えるということです。
貢献利益は、複数の商品がある場合の比較にも使えます。商品Aと商品Bの貢献利益率を比較すれば、どちらの商品の販売が会社全体の利益を押し上げやすいかを判断しやすくなります。ここで重要な点は、貢献利益は“全体の利益の入り口”であり、最終利益は別に固定費の分だけ差し引かれることです。
限界利益とは何か?定義と計算方法
限界利益は、追加の売上から追加の変動費を差し引いた額です。 つまり、追加で1単位を売ったときに得られる利益を指します。用語としては、追加の売上高 minus 追加の変動費、または「追加利潤」とも呼ばれます。実務では、数量を増やすかどうか、あるいは価格を調整するかという意思決定を行うときの判断材料になります。
追加の1杯売るときの例を考えましょう。コーヒー(関連記事:アマゾンの【コーヒー】のセール情報まとめ!【毎日更新中】)1杯の価格が500円、材料費が180円、その他の追加変動費が20円だとします。この場合、限界利益は500 - 180 - 20 = 300円となります。注意点は、限界利益は追加の売上と追加の費用の差であり、固定費の増減を直接含まない点です。
限界利益が正の値であるなら、新しい注文や増産は全体の利益を押し上げる可能性があります。ただし、追加の注文が固定費を回収できるかどうかは別問題です。売上が増えても、固定費が大きくのしかかっていると、限界利益だけでは十分でないことがあります。この点を理解しておくと、季節商品や特別注文の判断がずいぶん楽になります。
違いを実務でどう使い分けるか
実務では、貢献利益は製品ラインの全体的なパフォーマンスを評価するのに適しています。どの製品を増やすべきか、どの組み合わせが会社の総合的な利益を押し上げるかを検討する際に活用します。例えば、高い貢献利益率の製品を中心にラインナップを調整する、などの戦略が考えられます。
一方、限界利益は追加の取引や受注を検討する場面で強力な判断材料になります。特別注文や季節限定商品を受けるべきか、という“追加の売上を追求するかどうか”の議論で、限界利益が黒字であるかどうかを確認します。このときの肝は、追加売上が固定費の増加を超えるかどうかを見極めることです。
ケーススタディ:架空のカフェの例
架空のカフェを例に、貢献利益と限界利益をどう見るかを考えてみましょう。朝のブレンドコーヒーを100杯販売し、1杯あたりの売上が600円、変動費が200円、固定費は月額40万円だとします。貢献利益は100杯×(600-200)=40,000円となります。これは月の固定費40万円をカバーする力の小ささを示しています。
次に、限界利益の観点で追加の注文を考えるとします。追加で50杯を扱う場合、追加の売上は50×600=30,000円、追加の変動費は50×200=10,000円です。限界利益は20,000円であり、追加の50杯が固定費の不足を補えるかがポイントになります。もし他の時間帯の人手を増やすことでコストが大きく増える場合、限界利益だけでは黒字化が難しいかもしれません。
このケースでの結論は、貢献利益と限界利益の両方を見て初めて正しい意思決定ができる、ということです。売上を上げるだけでなく、変動費の削減や効率化を進めることで貢献利益を高め、追加の注文を受けるときは限界利益がプラスになるかを再確認します。 項目 金額の目安 1日売上 40,000円 追加売上(50杯) 20,000円
まとめ:覚えておくべきポイント
貢献利益は売上高から変動費を引いた額、固定費を賄う力を示します。
限界利益は追加の売上から追加の変動費を差し引いた額で、追加の注文が利得を生むかどうかの目安になります。
実務では、これらを組み合わせて意思決定をします。貢献利益を高める工夫(価格設定・コスト削減・商品ミックスの最適化)と、限界利益を意識した追加取引の検討を同時に行うことで、より安定した利益を獲得できるようになります。
補足:表と例の活用
理解を深めるためには、数値の表や実践ケースが有効です。表を使うと、異なる製品の貢献利益率を一度に比較できます。実務で活かせるポイントは、「追加の売上が固定費の増加を超えるか」を意識することと、「変動費を抑える工夫で貢献利益を増やす」ことです。これらを組み合わせると、日常の意思決定がぐっと見通しやすくなります。
友達とカフェの話をしていて、限界利益の話題が自然と出てきた。今あるメニューを増やすべきか、それとも新しい商品を投入すべきか迷う場面で、限界利益は“追加の一品”が店にもたらす純粋な利得を教えてくれる。たとえば新しいスイーツを導入する前に、追加の売上が材料費や包装費などの追加費用を上回るかどうかを計算する。限界利益が正なら試してみる価値があるが、費用が増えすぎれば結局黒字にはならない。こうした判断は、日々の選択を左右する大事なツールになる。
次の記事: 発送と返送の違いを徹底解説|これを知れば困らない! »





















