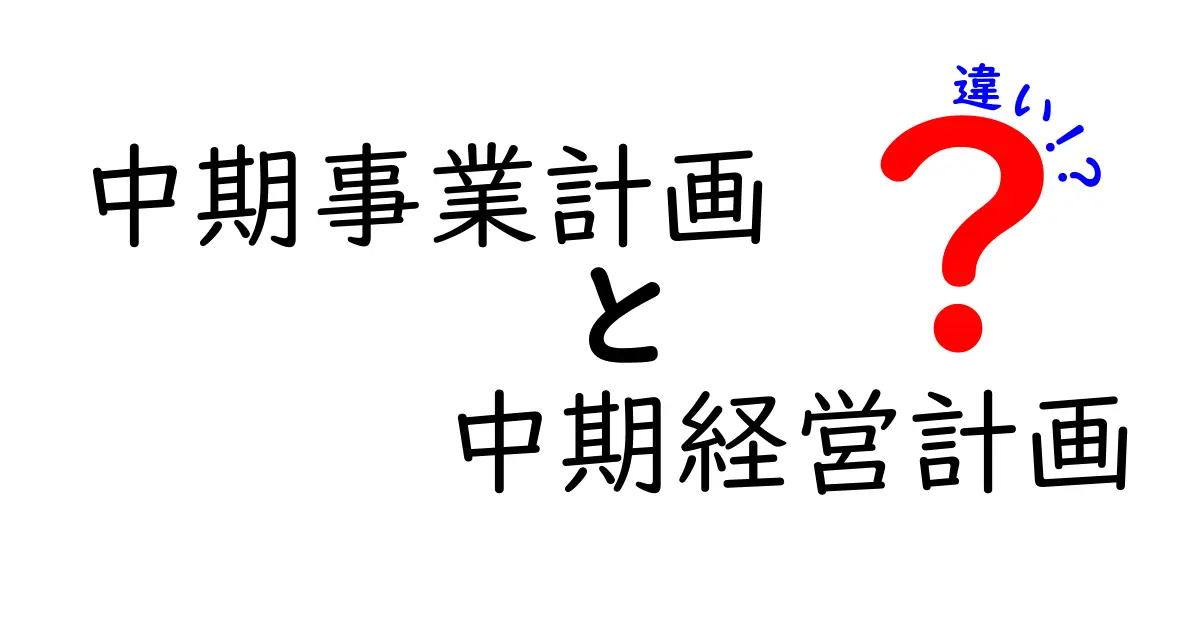

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
中期事業計画と中期経営計画の違いを徹底解説
中期事業計画と中期経営計画は、企業が数年先を見据えて動くときの道しるべのようなものです。中期という言葉はおおむね3年から5年程度を指すことが多く、日々の営業活動をどう組み合わせていくかを決めるときに使われます。まず大事なのは、両者の役割が完全に別物ではなく、むしろ互いを補い合う関係にあるという点です。中期事業計画は、具体的な商品やサービス、顧客セグメント、販路の拡大、供給体制、コストの削減といった現場に直結する活動を描くものです。新製品の開発ラインを増やすのか、既存の製品をどう改良するのか、どの市場を重点的に攻めるのか、どのくらいの売上と利益を狙うのか、こうした具体的な施策と数字を示します。これに対して中期経営計画は、企業全体の方向性や組織の運営体制、リスク管理、財務の健全性、ガバナンス、そして人材戦略といった組織をどう動かすかという視点をとらえたものです。つまり中期経営計画は誰が何をどう動くべきかという人と組織の計画を前面に出します。
この二つは別々の書き方をしますが、実務では同じ時期に作成され、相互に連携して機能します。中期事業計画で得た機会やリスクは中期経営計画の意思決定材料となり、逆に組織体制や資金計画の前提が事業計画の実現性を左右します。中学生にも分かる言葉でいうと、事業計画はこの店がどんな商品を出すかという話、経営計画はこの店を誰がどう運営していくかという話、そして両方を同時に整えるのが3年から5年先を見据えた会社の設計図です。
定義と範囲の違い
定義の違いは対象となる領域と焦点の置き方にあります。中期事業計画はこの期間にどんな商品をどう市場に提供するかという現場寄りの設計を指し、製品ラインアップ、価格戦略、販路開拓、供給の安定性といった要素が中心になります。対して中期経営計画は組織全体の方向性を決める視点で、組織の構造、役割分担、財務の健全性、リスク管理、社内の人材育成と評価の仕組みといった要素が中心になります。
この違いを理解するには、誰が決定権を持つのか、どうやって判断するのかを考えるといいです。現場の行動計画と経営層の意思決定が噛み合うと、実現性の高い戦略が生まれます。
要点は期間の共有と役割分担の明確さです。期間は同じでも焦点が異なるため、両方を一緒に見直す場を作ることが大切です。
作成の目的と対象者
作成の目的は主に三つです。第一に部門を超えた共通理解を作ること、第二に意思決定の前提をそろえること、第三に次の決算期までの実行を確実に回すことです。対象者は経営陣だけでなく、部門のマネージャーや現場のリーダー、時には全従業員まで広がります。中期事業計画は現場の動きを具体的に示すため、現場レベルの行動指針として機能します。中期経営計画は組織のルールや資金配分、リスク管理といった枠組みを整える役割を持ちます。両方を適切に連携させると、無理のない目標設定ができ、資源を適切に割り当てることができます。
主な要素と比較ポイント
主な要素としては戦略の軸、数値の設定、進捗の評価方法、リスク対応、資源配分、ガバナンスなどが挙げられます。
比較ポイントとしては対象範囲や意思決定の主体、時間軸と指標の違い、そして実務での連携方法が挙げられます。実務では事業計画で描いた機会を経営計画の予算で裏づけ、予算の見直しを通じて前提を修正します。
この二つを同じ指針のもとで定期的に見直すことが重要です。ポイントは、両方の文書を年次の会議で一緒にレビューし、次年度の目標へ結びつけることです。
実務での活用例と表現
実務での活用例として、仮にA社のケースを想像します。中期事業計画で市場機会を整理し、製品拡張の道筋を示します。中期経営計画では投資額や人員配置、財務上のリスクを見積もり、承認プロセスと進捗の評価を定義します。こうして両方を同時に進めると、現場の創意工夫と経営陣の資源配分が噛み合い、目標達成までの道のりが具体的になります。実務では、毎年の予算と実績を対比し、必要に応じて計画の前提を修正します。中学生にも伝わる言い方をすると、作る計画と動く仕組みを同じ時間軸で見ている感覚です。
まとめと注意点
中期事業計画と中期経営計画は別物ですが、実務では互いを補完し合う設計図です。現場の施策と組織のルールがずれないよう、定量的な指標で進捗を測ること、過度な楽観を避けること、関係者の承認ステップをあらかじめ決めておくこと、そして定期的な見直しを怠らないことが大切です。数字は物語の根拠です。読み手が理解できる言葉で書くこと、難解な専門用語を必要最小限に留めることも重要です。これらを守れば、変化が激しい時代にも柔軟に対応しつつ、長期目標へ着実に近づくことができるでしょう。
今日は中期事業計画についての雑談風の深掘りをしてみるね。友だちとカフェで話している感じで、専門用語を噛み砕いていくよ。中期というのは3年後くらいまでの計画を指す言い方だよね。中期事業計画は現場の動き、つまり商品をどう作るか、誰に売るか、どんな価格で売るかといった具体的な施策を描く設計図。これに対して中期経営計画は組織や資金の動き、つまり誰がどんな役割で動くのか、財務の安定性をどう保つのかという“動かす仕組み”を決める設計図だ。だから、作る計画と動く仕組みの両方が揃って初めて、現場のアイデアが現実の成果に変わるんだ。学校の課題に例えると、前者は科目別のレポートの設計、後者は学級委員会の運営ルールの整備みたいな感じ。僕は難しい言葉をそのまま使わず、家族や友だちが納得できる言葉で説明することを心がけている。もし新商品を出すとき、まず市場の声を集めてから試作を回し、販売ルートを確保して投資を決める――そんな順序が、現場と経営の両方を動かすコツだと思う。





















