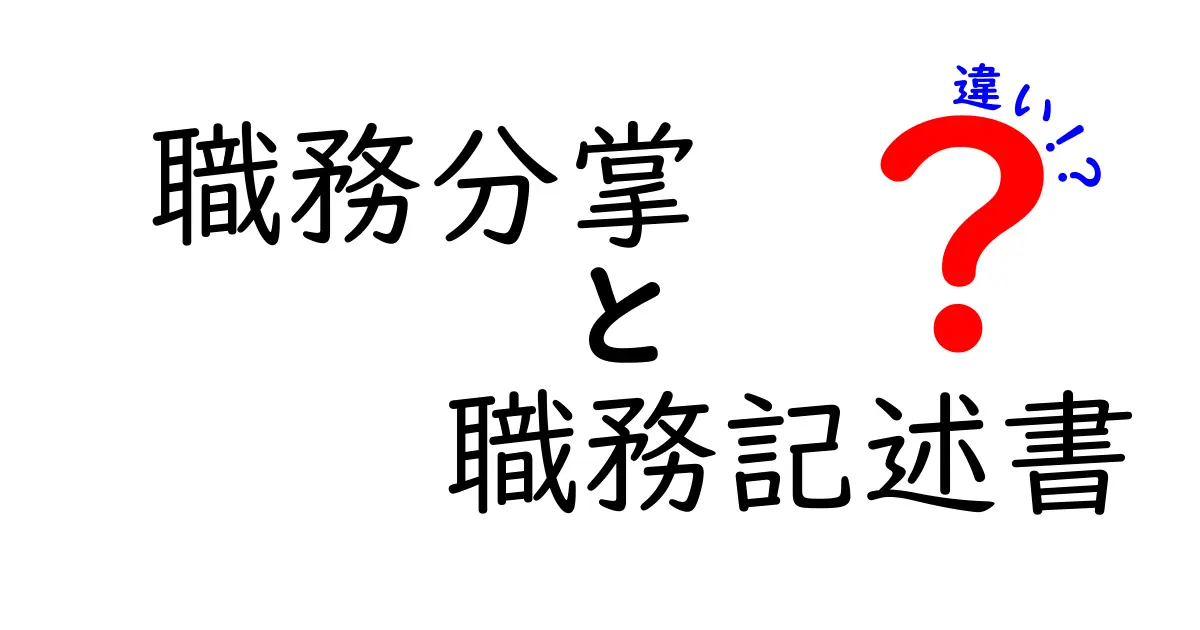

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに
現代の多くの組織では、誰が何をするのかをきっちり決めることが成果に直結します。特に「職務分掌」と「職務記述書」は、似た言葉ながら目的や活用範囲が異なるため、混同すると業務の抜け漏れや責任の所在があいまいになりがちです。本記事は、そんな誤解を解くためのガイドです。中学生にもわかるように、基本的な定義、作成の目的、現場での使い分け方、そして実務での活用例を順を追って紹介します。まずは大前提として、それぞれの「何を、誰が、どのように決めるのか」という点を押さえ、次に「現場でどんな場面でどちらを用いるべきか」を具体的に検討します。最後には、実務でのポイントとよくある誤解をまとめ、表と例を交えて理解を深めます。そうすることで、あなたの組織がよりスムーズに動くヒントを見つけてください。
職務分掌とは何か?
職務分掌とは、組織の中で「誰が何を担当するのか」を決める仕組みのことを指します。これには部門ごとの権限、責任範囲、意思決定の経路などが含まれ、組織内の混乱を減らし、業務の流れをスムーズにする目的があります。例えば、学校の部活動を想像してみましょう。顧問教師は「指導方針の決定・対外連絡」を担い、部長は「練習計画の作成・部員管理」を担当します。このように“誰が何を決め、誰が実行するのか”をはっきりさせることが職務分掌の要点です。職務分掌は通常、組織の階層ごと、あるいは職種ごとに整理され、組織図と紐づけて文書化されます。ここで重要なのは、権限と責任の分担をセットで定義することです。権限が大きすぎて実行が難しくなると現場の動きが止まってしまいますし、反対に権限が小さすぎれば意思決定が遅くなり、現場の判断が遅延します。したがって、適切な範囲を見極めることが求められます。
職務記述書とは何か?
職務記述書は、特定の職務に関する「具体的な業務内容・成果・評価基準・必要なスキル・勤務条件」などを詳しく記述した文書です。言い換えれば、個人の仕事の道筋を描く設計図のようなものです。例として、営業職の職務記述書には「新規顧客の獲得数」「月間の商談件数」「顧客満足度の向上」「提案資料の作成スピード」などが列挙され、これらを達成するための具体的な手段や評価方法が明記されます。職務記述書は、雇用時の採用要件や評価・昇進の基準、教育訓練の対象を決める際の重要なガイドラインになります。なお、職務分掌が「組織全体の責任と権限の枠組み」を示すのに対して、職務記述書は「個人の業務遂行の具体的手順と成果指標」を示す点が大きな違いです。
違いを整理して正しく使い分けるコツ
違いを正しく理解するコツは、目的と対象を明確に分けることから始まります。まず、組織全体の枠組みを決めたいときは職務分掌を作成・見直します。部門ごとの責任範囲、意思決定の権限、横断的な連携の仕方などを整理し、誰がどの場面で決定を行うのかを決めておくと、業務の進みにくさを減らせます。次に、個々の仕事レベルで「何をどう評価するか」を決めたい場合には職務記述書を作成します。どの業務がどの成果指標に結びつくのか、今どんなスキルが必要か、評価はどのように行うかを具体化します。ここでのポイントは、両者を相互補完的につなぐことです。実務上は、職務分掌の権限が変われば職務記述書の業務範囲も見直す必要がありますし、逆に新しい職務記述書を作ると、対応する権限の再配置が必要になることがあります。表を使って違いを視覚化すると理解が進みやすいので、以下に簡易表を用意します。
続いて、以下の比較表も参考にしてください。
| 要素 | 職務記述書 | 違いのポイント |
|---|---|---|
| 対象 | 個人の業務内容 | 個人の業務を具体化する |
| 目的 | 評価・育成の基準作成 | 成果指標とスキル要件を明確化 |
| 期間 | 更新は必要時 | 状況に応じて定期的更新 |
このように、両者は別々の機能を持ちながら、現場の運用を円滑にするために互いを補完します。実務では、まず職務分掌を見直して権限と責任を整理し、そのうえで個々の職務記述書を整備すると、責任の所在と業務の手順が整った状態を作れます。最後に、「更新サイクルを決めること」と 「文書の共有・アクセス権を管理すること」を忘れずに行いましょう。そうすることで、現場の混乱を減らし、評価の透明性を高めることができます。
実務での活用例
実務での活用は多岐にわたります。例えば、部門の新しいプロジェクトを開始するとき、最初に職務分掌を確認して誰が意思決定を行うかを決めます。次に、プロジェクトメンバーそれぞれの職務記述書を参照して、どの業務を誰が担当するかを割り当て、成果指標を設定します。よくあるケースとして、組織変更や人材の異動時にはこの2つの文書を同時に見直すことが望ましいです。これにより、引継ぎがスムーズになり、引継ぎ漏れや責任の二重化を防ぐことができます。実務では、会議の際にこの2つの文書を参照して議論を進めると、話がずれなくなり、合意形成が早まる傾向があります。以上の実務例は、学校、自治体、企業など、幅広い組織で適用可能です。表や図を使って視覚的に整理することも効果的です。課題としては、頻繁な人事異動や組織再編時の更新作業が負担になる点です。ここを自動化や運用ルールで軽減する工夫を取り入れると、実務の負担を減らせます。
職務分掌は組織全体の権限と責任の枠組みを決める設計図です。現場の動きを左右するポイントは“誰が最終判断を下すのか”を明確にすること。日常の場面で権限が曖昧だと提案が遅れ、責任が不明確だと引き継ぎが難しくなります。だからこそ、職務分掌と職務記述書はお互いを補完する関係。双方を併用して整えれば、意思決定の速度と業務の質が同時に向上します。
次の記事: 洞察力と考察力の違いを徹底解説!日常で使える見分け方と使い方 »





















