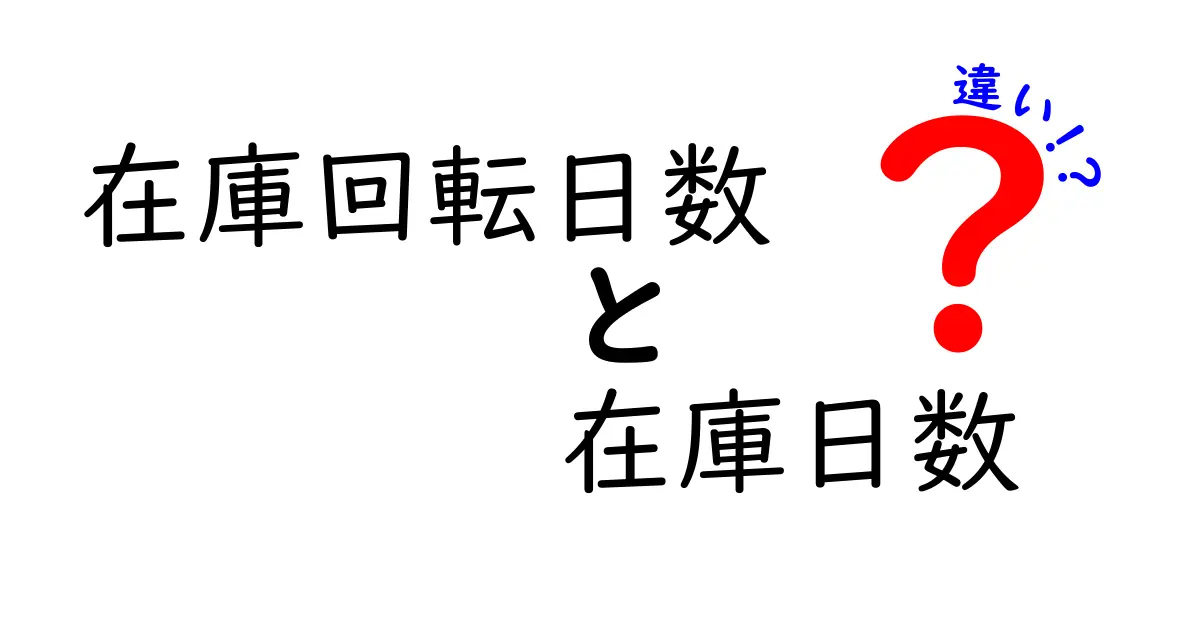

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
在庫回転日数とは何か
在庫回転日数は、在庫を「何日でひと回転させられるか」を表す基本的な指標です。日数が短いほど回転が速く、資金が効率よく動いている状態を意味します。実務でこの指標を使うときは、売上原価(COGS)と在庫の平均高を組み合わせて計算します。一般的には、在庫回転日数 = 365日 ÷ 在庫回転率の式で求めます。ここでの在庫回転率は、売上原価 ÷ 平均在庫高で算出します。つまり、この二つの数字を組み合わせると、在庫が何日でひと回転するのかが見えてきます。
例えば、ある企業の年次売上原価が3,000万円、平均在庫高が1,000万円なら、在庫回転日数は365 ÷ (3,000 ÷ 1,000) = 365 ÷ 3 = 約121日となります。
この結果は「在庫を一年に何回回せるか」という観点ではなく「在庫が一回転するのに何日かかるか」という時間の感覚を示します。
在庫回転日数の計算には注意点もあります。データの期間設定によって数値が大きく変わるため、年度ベースか月次ベースか、またどの在庫データを平均在庫として使うかを統一しておくことが重要です。
さらに、商品の性質や販売チャネルの違いによっても適切な基準値は異なります。季節商品は季節によって回転日数が大きく変動しますし、ECと実店舗で在庫の回転が異なることもあります。
このような状況を理解したうえで、目標値を設定し、定期的に比較することが重要です。
在庫日数とは何か
在庫日数は、現在の在庫が市場へ出ていくまでの「日数の目安」を示す指標です。在庫日数は在庫がどれくらいの期間棚に残っているかを直感で知るための指標として使われます。数学的には、在庫回転日数と近い関係にあり、実務的には同じ意味で使われることも多いのですが、運用の場面では「今の在庫水準がいつ売れるかの感覚」を重視することが多いです。
算出には、平均在庫高と期間中の売上原価または売上高を使います。月間データを用いる場合は、月間の売上原価や売上高と平均在庫高を組み合わせて日数に換算します。これにより、現状の在庫バランスが適切かどうかを判断できます。
在庫日数が長い場合は「売上機会の損失」や「資金の滞留」が発生している可能性があり、逆に短すぎる場合は「欠品リスク」や「過小発注の懸念」が生じます。
したがって、在庫日数は必ず他の指標と組み合わせて解釈することが重要です。
在庫回転日数と在庫日数の違いと実務での使い分け
在庫回転日数と在庫日数は、同じ現象を別の切り口で表す指標として扱われることが多いですが、現場での捉え方には違いがあります。在庫回転日数は“回転の速度”を重視し、どれだけ早く在庫が売れて現金に化されるかを評価します。一方で在庫日数は“在庫の滞留日数”を重視し、現在の在庫水準がどの程度の時間市場に出ていくかの感覚を把握します。この二つを使い分けることで、資金の循環と供給の安定の両方をコントロールできます。
実務での使い分けのコツは以下のとおりです。
- 新規商品や季節商品は在庫日数の感覚が重要です。売れ残りを防ぐため、現状の在庫水準をこまめに見直します。
- 安定した売上の定番商品は在庫回転日数でパフォーマンスを評価します。回転が悪い場合は仕入れ量の調整や販促を検討します。
- 両方の指標をセットで監視し、日次・週次・月次の報告に組み込むと、資金の滞留と欠品のリスクを同時に抑えやすくなります。
以下は、簡易な比較表です。
このように、在庫回転日数と在庫日数は互いに補完的な関係にあります。二つの指標を同時に見ることで、資金繰りと供給の安定の両方を最適化するヒントが得られます。最終的には、企業の規模や業態、商品特性に合わせて、計算式の分母となるデータの取り方を統一することが成功のカギになります。
放課後、友達のミカと雑談していた。彼女は在庫回転日数って言葉を耳にして“在庫が何日で回るの?”と尋ねた。僕は「そう、つまり在庫が早く売れて現金に変わるスピードを測る指標だよ」と答えた。ミカは「でも在庫日数ってのは何?」とさらに質問。僕は「在庫日数は今この水準の在庫が何日分の売上に相当するか、日数の感覚として測るもの。回転日数と似ているけど、現状の在庫の“滞留感”を直感で見るツールだと思えばいい」と説明した。話は続き、二人で色んな商品を思い浮かべながら、季節商品や定番商品の動き、欠品リスクと過剰在庫のバランスについて意見を交換した。結局、二人は「指標は一つだけで判断せず、複数のデータを組み合わせるべき」という結論に達した。





















