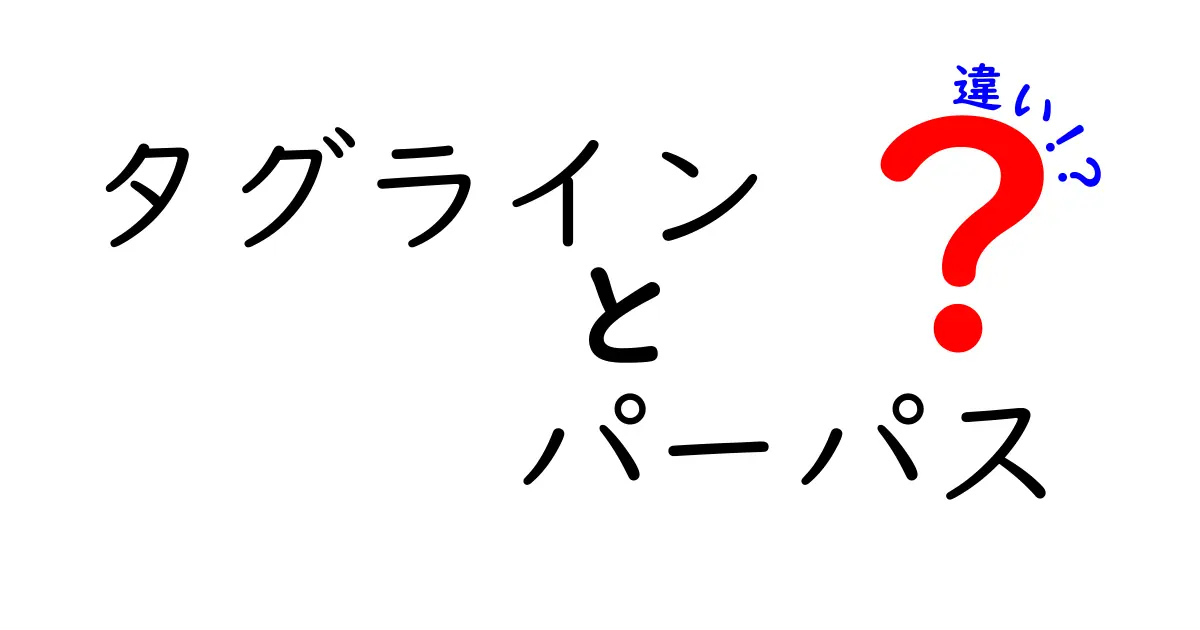

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
タグラインとパーパスの違いを正しく理解する
ブランドや組織が成長するとき、伝える言葉の選び方がとても大切です。タグラインは短く覚えやすい言葉を使う入口で、顧客の心に刻まれる印象を作ります。一方、パーパスは企業が社会の中で何のために存在するのかを示す根幹の信念です。タグラインは瞬間的な印象を作る入口、パーパスは長期的な指針として機能します。この二つは別物ですが、上手に組み合わせると信頼性の高いブランドが生まれます。
もしタグラインだけで戦うと、表面的な印象にとどまりやすく、パーパスがなければ長期的な信頼を築くのが難しくなります。逆にパーパスだけでは、日々の行動が抽象的で伝わりにくくなります。
本記事では、「タグラインとは何か」「パーパスとは何か」「違いをどう使い分けるか」を、中学生にも分かる言葉で丁寧に解説します。読む人の心に残る言葉の使い方を、一緒に考えていきましょう。
具体的な場面を想定して考えると、学校行事や部活動、地域イベント、企業のマーケティングなど、さまざまな場面で役立つヒントが見つかります。
最後まで読めば、タグラインとパーパスを正しく使い分けるコツがつかめ、伝えたいことをより強く、より深く伝えられるようになります。
タグラインとは何か?
タグラインとは、ブランド名や商品名とセットで使われる、短く覚えやすい“入口の言葉”のことです。一文か二文程度の短さが特徴で、聴いた人の心に残るリズムや響きを重視します。広告や販促、イベントの開始時など、瞬間的な印象づくりの役割を担います。「誰に・何を・どう感じてほしいのか」を三つの要素としてギュッと凝縮する作業が求められます。長すぎると覚えにくく、曖昧になる恐れがあり、逆に短すぎても伝わらないことがあります。タグラインは、ブランドの第一印象を作る“看板のひとこと”として働き、顧客が口に出したくなるリズムを意識することが大切です。具体例を挙げると、パン屋さんの「焼きたての温もりを、毎朝あなたに」は、温かさと新鮮さを伝え、朝の来店動機を喚起します。
このように、タグラインは短く、具体的で、記憶に残る表現が基本です。ブランドの雰囲気づくりにも影響しますので、商品特性と顧客の感情を結ぶ橋渡し役として機能します。
パーパスとは何か?
パーパスは、企業や組織が「なぜ存在するのか」を示す根本的な存在意義の説明です。これは単なる目標や利益追求を超え、倫理観や信念、社会に対する責任感を含みます。パーパスを掲げると、社員は日々の業務で何を優先すべきか、どのような decision を下すべきかを判断する指針を得られます。例として、教育系企業が「すべての子どもに等しく学ぶ機会を届ける」というパーパスを掲げると、商品開発・採用・パートナー選びに一貫性が生まれ、外部の圧力にもぶれにくくなります。パーパスは組織の長期的な信頼を築く土台ですが、具体的な行動計画と結びつかないと伝わりにくい点にも注意が必要です。船の羅針盤のように、パーパスは方向性を示す軸であり、タグラインは旗印のように視覚と感情へ直接働きかけます。
両者の違いを日常の場面でどう使い分けるか
日常の場面を想定して、タグラインとパーパスをどのように使い分けるかを考えてみましょう。学校の文化祭を例にとると、タグラインは来場者の関心を引く短い一言として機能します。例えば「今年の文化祭、笑顔が主役!」のような表現は、来場者の気分を動かし、イベントへ足を運ばせる力があります。一方、パーパスは「誰もが楽しみながら創造できる場を提供する」という価値観を示し、実行委員の方針決定や企画の優先順位を統一します。ビジネスの場面でも同様です。新製品のローンチを準備する場合、タグラインは購買意欲を喚起する一言として働き、パーパスはその製品が社会にどう貢献するかを説明します。これらを組み合わせると、表面的な魅力と長期的な信頼の両方を得ることができます。
要するに、タグラインは瞬間の印象を作る入口、パーパスは長く続く信念や価値観を示す羅針盤です。両方を意識して使い分ける練習をすると、伝えたいことが明確になり、受け手に伝わる力も強くなります。
実例と表で比較
実際のブランドの例を使って、タグラインとパーパスの違いを比べてみましょう。A社は“安全・便利・迅速”というタグラインで製品の価値を直感的に伝え、同時に“誰でも使える車をつくる”というパーパスで長期的な信念を示します。B社は“あなたの日常をちょっと特別に”というタグラインを使い、パーパスを“人とつながる喜びを創出する”と掲げています。以下の表に、要素ごとの違いを整理します。
このような整理は、企画の初期段階で“何を伝えたいか”と“どう行動させたいか”を一致させる作業に役立ちます。
このような表は、チームで話を進める際に「何を優先するか」を可視化するのに役立ちます。短い言葉を磨く作業と、存在意義を深掘りする作業を同時に進めると、ブランドの核がぶれずに成長していくのです。
今日は、タグラインとパーパスの違いを小さな会話風に掘り下げてみよう。友だちが「この部活の意味って何だろう?」と聞いたとき、私たちはまず軽く刺さる一言、つまりタグラインを投げかけるかもしれない。「みんなで創る、楽しい日常へ」。でも本当の意味を伝えるには、パーパスを語る必要がある。私たちは“誰もが参加できる場を作る”という存在意義を胸に、日々の練習・活動・イベント運営をその信念に沿って進める。タグラインは入口、パーパスは道しるべ。二つが揃えば、仲間も外部の人にも、何を目指しているのかが伝わりやすくなる。部活をはじめたばかりの頃、私はこの二つを同時に意識することで、仲間との協力が増え、練習の意味もはっきりしたと感じた。今では、短くても心に刺さるタグラインと、長期的な存在意義を示すパーパスの組み合わせが、私たちの活動を前へ進める推進力だと思う。





















