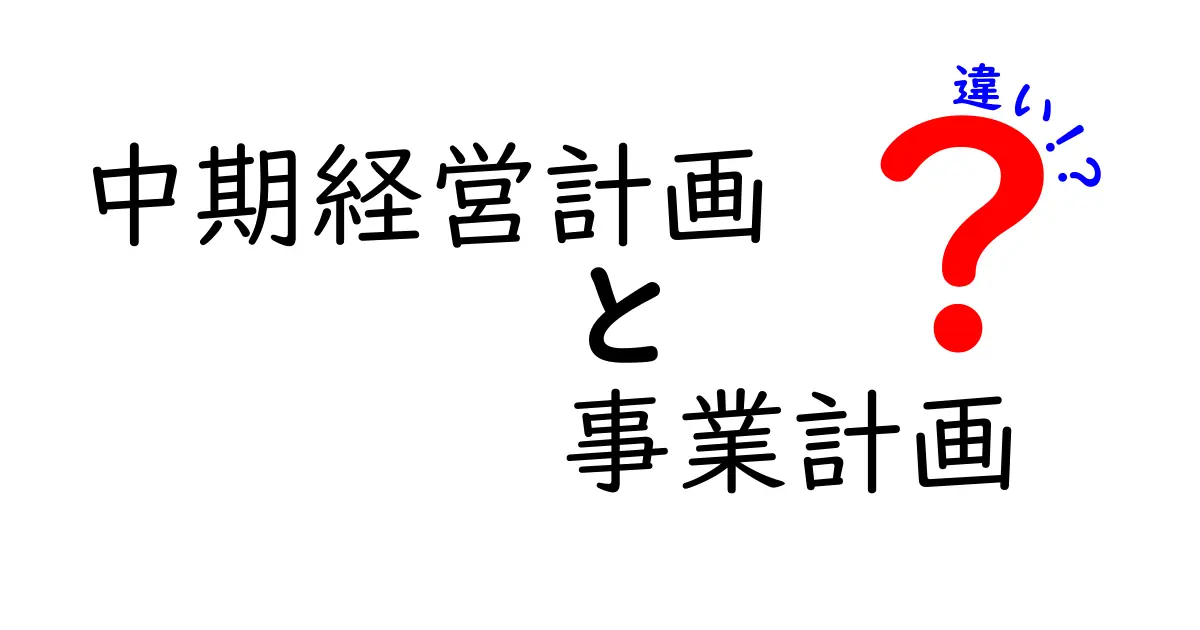

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
中期経営計画と事業計画の基本的な違いを理解する
中期経営計画と事業計画は、似ている言葉ですが役割が違います。まず中期経営計画は企業全体の方向性を決める長期の道筋です。資源の配分、組織の体制、財務の目標など、会社が何をどう達成するかを広い視点で示します。対して事業計画は個別の事業や製品の実行計画です。売上目標、コスト、開発スケジュール、リスク対策などを具体的に落とし込み、日常の意思決定を支える道具になります。双方は密接に連携しますが、焦点が違います。中期経営計画が「何をどう動かすかの設計図」であるのに対し、事業計画が「実際に動く手順と数値」を示す地図です。
この違いを理解することは新入社員にも重要です。なぜなら、上司が提示する数字の意味を正しく解釈し、日々の業務が全体戦略のどこに位置づけられるのかを把握することで、行動に一貫性が生まれるからです。
本記事では、まず両者の基本的な性質を並べて説明し、次に実務での作成時のポイント、最後に実務上の注意点と誤解を解くヒントを紹介します。
実務における使い分けと作成のコツ
長期の視点と日常の実行をつなぐには、両者の連携が重要です。まずは企業のビジョンとミッションを全社員が共有している状態を作ります。ビジョンは抽象的で伝わりにくいこともあるため、数値目標だけでなく物語の形で説明します。次に中期経営計画で資源配分の枠組みを決め、その枠組みの中で事業計画を作成します。事業計画は現実的な売上・費用・人員・開発リリース日を設定します。現場の担当者は、この二つの計画を同時に参照し、いま自分の業務がどの目標に貢献しているのかを確認します。
作成のコツとしては、期間をまたぐトピックを整理すること、前提条件が変わったときの「代替案」を用意すること、そしてデータの透明性を保つことです。データの出所を明確にし、誰が何をいつまでに決定するのかを文書化します。
また、関係者の関与を促すために、レビュー会議を定期的に設け、フィードバックを反映させるループを作ることが重要です。これらを守れば、現場と経営が噛み合い、改善サイクルが回り続けます。
- 現状分析と前提の共有
- 長期目標と短期目標の整合性確認
- リスクと代替案の用意
- 進捗の可視化と定期レビュー
よくある誤解と現場の現実
よくある誤解は「中期経営計画は固定されるべきであり変更すべきでない」というものです。実際には環境が変われば見直しが必要です。変更可能性を前提にすることが現実的な運用です。もうひとつは「事業計画は厳密すぎて現場の自由度を奪う」という考えです。適切に作成された事業計画は現場の判断を縛るのではなく、判断材料を増やします。重要なのは、計画の背後にある仮説を全員が理解しておくことです。仮説検証を織り込んだ運用をすれば、数字が変動しても目的は崩れません。最後に、計画が机上のものになりがちという指摘にも注意が必要です。実際には現場の行動ログや顧客の声を取り入れて反映させることが成功につながります。
このような現実を踏まえ、読者には、計画を「未来の地図」として見るのではなく、「現実の道案内」として活用してほしいのです。
中期経営計画の話題を友人と雑談していたときのこと。私は「中期経営計画は3〜5年先の道筋を描く設計図で、財務や人材配置の大枠を決めるもの」と説明しました。友人は「具体的な日付や作業はどうなるの?」と聞きました。私は「具体化は事業計画で行い、実行の現場は毎月の進捗と市場の動きを見ながら調整します」と答え、道具としての使い分けを強調しました。





















