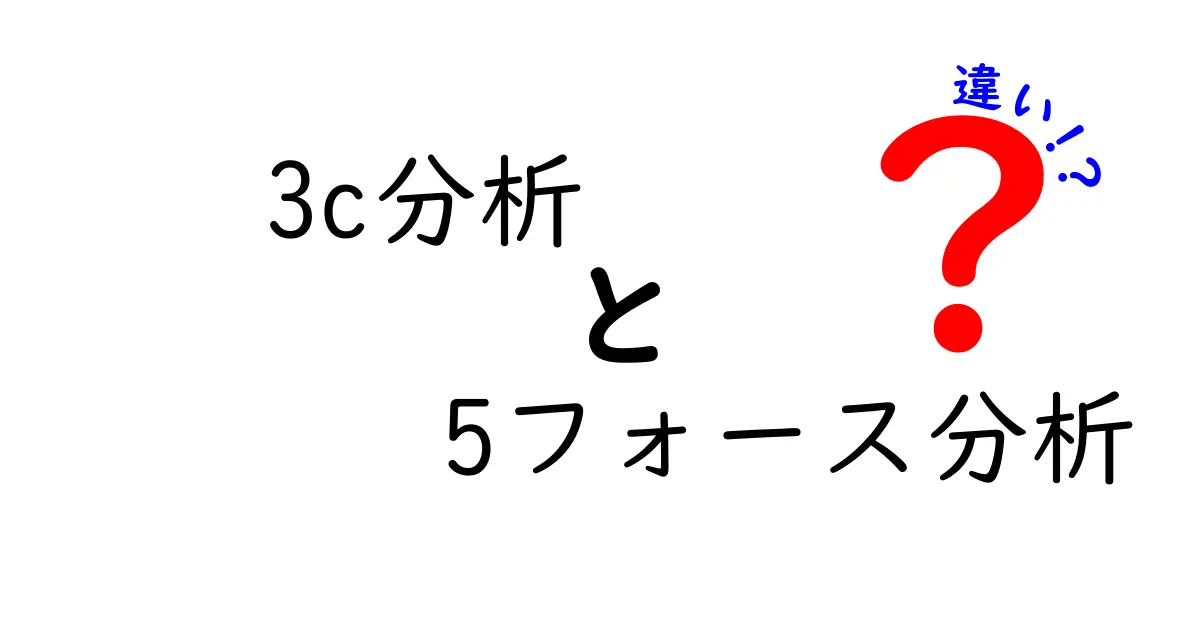

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
3C分析と5フォース分析の違いを徹底理解
「3C分析」と「5フォース分析」は、ビジネスの戦略を考えるときに役立つ代表的な分析手法です。まずはそれぞれの基本を押さえましょう。
3C分析はCustomer(顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの視点から市場や自社の立ち位置を整理します。ここでの狙いは、顧客のニーズと自社の強み・弱みを結びつけ、どう差別化していくかの方向性を見つけ出すことです。次に、5フォース分析はPorterの五力分析と呼ばれ、Industry(産業)内の競争力を構造的に捉えます。新規参入の脅威、供給業者の交渉力、買い手の交渉力、代替品の脅威、既存企業間の競争の激しさという5つの力が、産業の収益性を左右します。これらは似ているようで、着目点が違います。3Cは「誰に、何をどう売るか」を決めるための地図作成ツール、5フォースは「この市場の利益を左右する力の源泉を見極める」ための天秤です。これらをセットで使うと、機会とリスクを同時に検討でき、現実的な戦略を立てやすくなります。
結論としての違いを一言でまとめると、3Cは顧客・競合・自社という「内側と外側の接点」を探る設計図、5フォースは産業構造そのものがどう利益を生み出すかを測る「外部の力」の分析です。実務ではこの両輪を組み合わせて、どの市場でどう勝つかを具体化します。
続けて、次のセクションでは実務での使い分け方と、実際に役立つ比較表を紹介します。この記事を読んで、3C分析と5フォース分析の違いを理解し、戦略立案の場面で自信を持って選択・組み合わせできるようになることを目指します。具体的な使い方を知ると、初めての新規事業の企画や市場調査の報告資料作成もぐっと楽になります。差別化ポイントを明確にし、業界の構造を理解することで、説得力の高いストーリーを作れるようになります。
この章での要点は、3Cが市場と自社の接点を描く地図、5フォースが市場の力関係を描く風景という二つの視点を覚えること、そして実践ではこの二つを連携させて具体的な施策案へと落とすことです。これができれば、プレゼン資料や提案書で「なぜこの戦略なのか」が自然と伝わるようになります。
実務での使い分けと表による比較
現場での活用を前提に、3C分析と5フォース分析をどう使い分けるかを整理します。まず3C分析は、新規市場や新商品を検討する際に誰に対して何を提供するのかを明確化する作業に向いています。顧客のニーズをセグメント化し、競合の強み・弱みとの比較、そして自社の資源・技術・ブランド力を棚卸しすることで、差別化の軸を決めます。次に5フォース分析は、産業全体の収益性を評価するのに適しています。市場の規模感、参入条件、替代品の動向、取引条件の変化などを把握することで「この産業で長期的に利益を出せるのか」を判断します。これらを組み合わせると、機会と脅威、強みと弱みを同時に見渡して施策を設計できます。 友だちとカフェで雑談していたとき、3C分析と5フォース分析について話題になりました。私が最初に「3C分析はお客さんと競合と自分の3つの視点を一枚の地図に描く作業だよ」と言うと、友だちは「なるほど、ネコの目のように細かく市場を観察する感じだね」と返してきました。そこで私は「5フォース分析は産業の中でどんな風が吹いているかを測る天秤みたいなもの」と説明しました。結局、3Cで誰に何を届けるかを決め、5フォースでその市場が長期にわたって安定して儲かるかを判断する。この組み合わせが、企画書を作るときの“いかに説得力をつけるか”というコツにつながるんだよと話すと、友だちは感心していました。 前の記事:
« 3C分析と4P分析の違いを完全解説|初心者にも分かる比較ガイド 次の記事:
脅威分析と脆弱性分析の違いを正しく理解するための完全ガイド »
使い分けの具体例を挙げると以下のとおりです。新規事業の検討段階では、まず3Cでターゲット顧客と自社の適合性を確認します。続いて5フォースで市場の競争環境と参入障壁を評価し、収益性の高い領域を特定します。次に、ターゲット市場が決まったら、3Cの視点で具体的な商品設計・価格設定・販路戦略を立案します。そして5フォースの分析結果を踏まえて、パートナーの取り方やサプライチェーンの強化、代替品対策を検討します。これを資料に落とすと、上司やクライアントに「現実的で説得力のある戦略である」と納得してもらいやすくなります。以下の表は、3C分析と5フォース分析の基本的な比較を一目で分かるよう整理したものです。要素 3C分析 5フォース分析 分析対象 顧客のニーズ・競合の動向・自社資源 産業の構造・競争力の源泉 目的 差別化の軸と市場機会の特定 産業の収益性と長期的な環境認識 主なアウトプット ターゲット市場・価値 proposition・資源配分 参入の可否・競争力の源泉・脅威の要因 使いどころ 新規事業・商品開発・マーケ戦略 業界分析・ポジショニング・戦略的提携
以上のように、3C分析と5フォース分析は互いを補完する関係にあります。実務では、まず3Cで「何を売るか」を決め、次に5フォースで「この市場でどう守るか・どう攻めるか」を検討するのがコツです。これにより、実際のビジネスプランが筋道立ち、説得力のある提案が作れるようになります。
ビジネスの人気記事
新着記事
ビジネスの関連記事





















