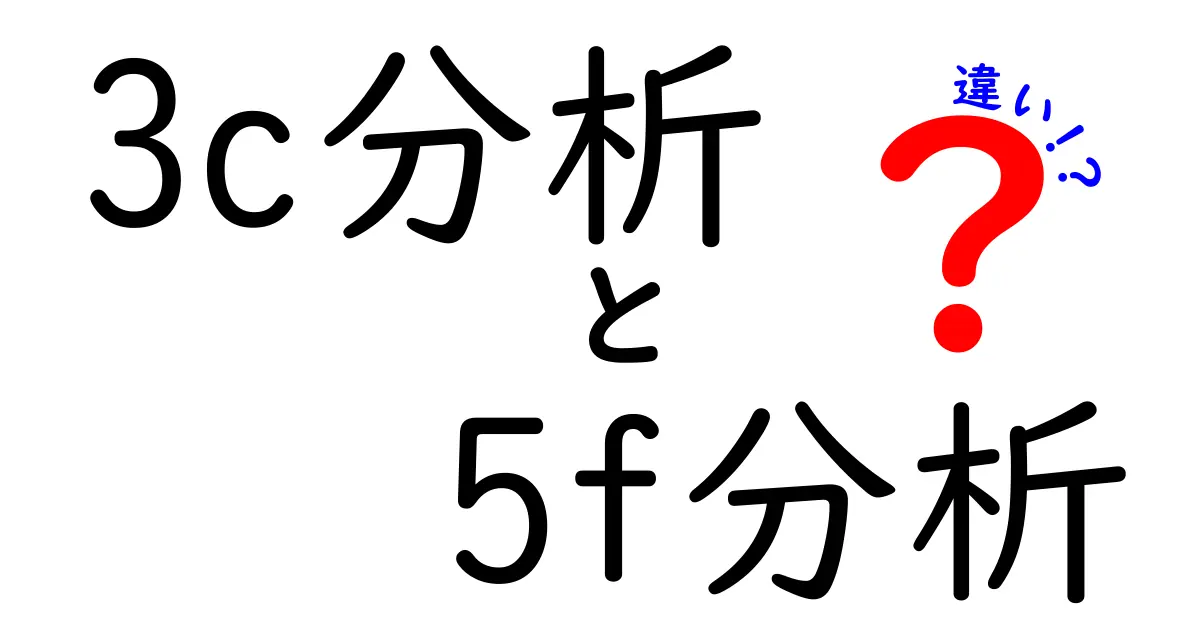

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
3C分析と5F分析の違いを体系的に解説するガイド
3C分析と5F分析は、ビジネスの現状を把握して戦略を決めるときの重要な道具です。3C分析は主に自社(Company)・顧客(Customer)・競合(Competitor)の3つの視点から市場環境を整理します。ここでは自社の強みや弱み、顧客のニーズ、競合の動きを横並びに見ることができ、具体的な戦略の方向性を見つけやすいのが特徴です。
一方、5F分析は「業界の構造を形づくる5つの力」に着目します。具体的には参入の脅威、代替品の脅威、顧客の交渉力、供給者の交渉力、既存競合の競争激化を分析し、業界全体の魅力度を評価します。
このふたつは同じ目的――戦略を決めるための情報整理――を目指しますが、焦点が異なります。3C分析は自社と市場の内側の状況を深掘りするのに適し、5F分析は業界構造の外部要因を俯瞰するのに強いという性質があります。
実務では、まず3Cで自社の立ち位置と顧客像を明らかにし、次に5Fで市場の競争環境を把握するという順で使うと、抜け漏れが少なく現実的な戦略を作りやすいです。
さらにデータの出所や信頼性をどう確保するか、分析結果をどう現場に落とし込むかといった実務上の工夫も大切です。
例えば新製品の市場投入を計画する場合、3Cでターゲット顧客と差別化ポイントを特定し、5Fでその市場の参入障壁や価格競争の可能性を評価します。これにより、最初の仮説を現実的な行動計画に落とし込めます。
実務での使い分けのコツと注意点
5F分析は業界の全体像を見るのに有用だが、個別の製品戦略には向かない場合がある。
逆に3C分析は自社の内部資源や顧客ニーズの具体的な洞察に強いが、業界全体の動向を見落としがちになることがある。これを補うためには、両方を併用するのが効果的です。
特に新規事業や新製品の立ち上げ時には、3Cで顧客の潜在的なニーズと自社の優位性を洗い出し、5Fで市場の競争力を確認するという順番が現実的です。分析結果を資料としてまとめる際には、実務の意思決定に直結するアクション項目を必ずセットにしましょう。
総括として、3C分析と5F分析は相補的な道具です。どちらか一方だけに頼るのではなく、組み合わせて使うことで現実のビジネス判断を強化できます。強みを伸ばし、機会をつかむための最適な組み合わせを見つけることが、成功への近道です。
ねえ、今日は3C分析を深掘りする雑談の小ネタを用意したよ。3C分析はCompany・Customer・Competitorの3つのCを縦横に結ぶことで、会社と市場のつながりを立体的に眺める方法なんだ。例えば新しいゲーム機を作るとき、まず自社の技術力と資金力、次に狙う顧客層と彼らの価値観、最後に競合の出方を考える。ここで重要なのは、3Cが与えるのは今の自分たちの位置の把握だよ。ところで5F分析はどう関係するかというと、業界全体の力関係を別の角度から見るツールで、2つを合わせると市場と競争の仕組みが見える。なんて話を友だちとするだけでも、戦略を立てるときの視点が広がるんだ。





















