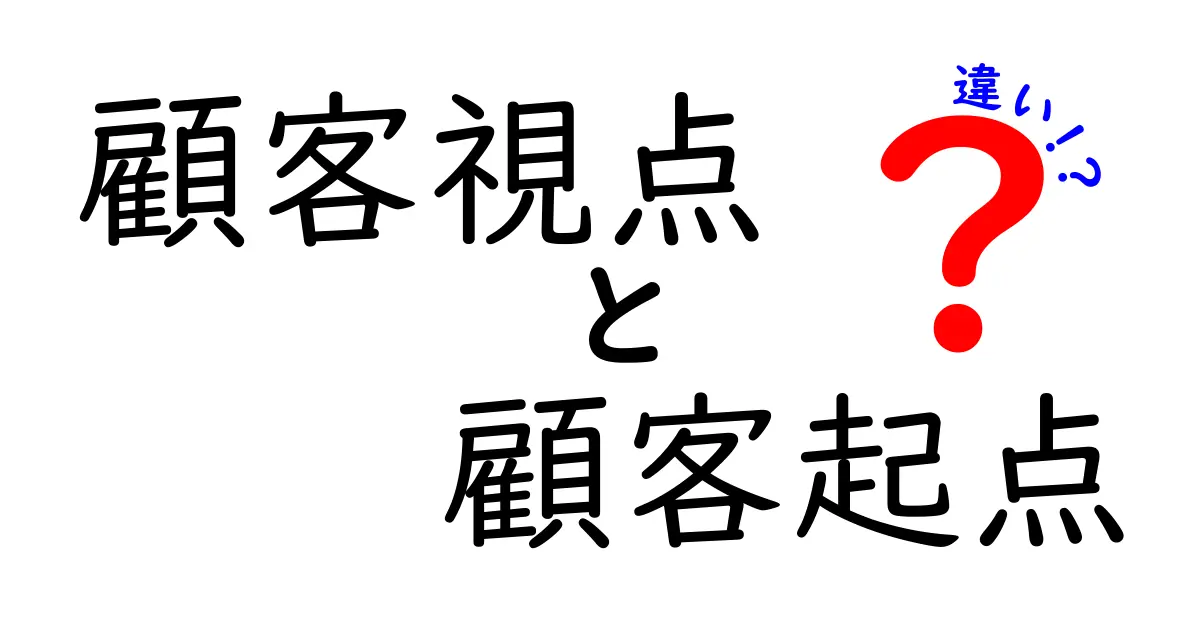

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
顧客視点と顧客起点の基本を押さえる
顧客視点と顧客起点の違いを正しく理解することは、学校の授業だけでなく社会で生きていくときにも役立ちます。二つの言葉は近い意味に見えますが、使う場面や意図が異なるため、混同すると組織の動きがうまくいかなくなることがあります。まず、顧客視点とは「お客さんの立場から世界を見て、彼らが何を感じ、何を望んでいるのかを理解する」ための視点です。現場での話をよく聞き、観察を重ね、体験をデータとして整理します。研究のように難しく考える必要はなく、身近な場面から始めて、どんな場面で困りごとが生まれているのかを具体的に掘り下げることが大切です。
そのうえで、顧客起点は「企業の全体を顧客の視点で設計する」という考え方です。顧客起点では、顧客の長期的な価値を最優先に置き、組織の方針、プロセス、評価の仕組み、さらには人材教育にまで影響を与えます。ここでのポイントは、単なる一時的な改善ではなく、長い時間軸で顧客にとって意味のある変化を生み出すことです。
両者は互いに補完的で、それぞれの良さを活かし合うことで、現場の改善と戦略の整合を図ることができます。エピソードをひとつ挙げれば、ある店が顧客視点だけで接客を改善したとします。確かに接客は良くなり、満足度は上がりますが、次にその店を選ぶ理由が別の店の方が強くなってしまうことがあります。そこで顧客起点を追加すると、長期的な関係性を築く仕組みが生まれ、リピートや紹介が増える可能性が高まります。要するに、顧客視点と顧客起点を別々のものとして扱うのではなく、両方を意識的に組み合わせて使うのが賢い方法です。
日常のビジネス場面での使い分けとメリット
日常の場面で二つの考え方をどう使い分けるかを知ることは、学校の課題にも役立ちます。まず、顧客視点は現場の体験を細かく観察する力を養います。お客さんが店内でどんな動線を辿るのか、どんな場面で困りごとを感じるのか、接客の言い回しや待ち時間のストレスがどこにあるのかを、実際の声やデータを通じて理解します。これにより、具体的な改善案、例えるなら動線の再設計、表示の見やすさ、商品配置の工夫などが生まれやすくなります。一方、顧客起点は組織の考え方を大きく動かします。顧客の長期的な満足を最重要視し、データを横断的に結びつけて全体のサービス設計を見直します。例えば、オンラインと実店舗の情報を統合して案内を一本化したり、配送スピードを一定水準に保つ仕組みを整えたりすることで、長期的な信頼を築くことができます。こうした取り組みは、短期の売上だけでなく、再来訪や紹介といった長い目で見た価値の創出につながります。
現場の改善と組織の変革を同時に進めるには、両方の観点を同時に意識することが大切です。顧客視点は“その場の満足度を高める”ための観察・分析を促します。顧客起点は“長期的な価値を最大化する仕組み”を作る力を与えます。これらをバランスよく使い分けると、組織は柔軟に対応でき、顧客との信頼関係をより強く育てることができます。
表で見る違いと使い分けのコツ
以下の表は、顧客視点と顧客起点の違いをひと目で整理したものです。要するに、どこを見て、どんな指標を重視するか、何を改善のゴールとするのかが違います。要素の観点では、顧客視点は“体験の断片”を丁寧に観察しますが、顧客起点は“全体の仕組みと長期的価値”を見渡します。
指標も異なります。満足度や使い勝手といった一時的な数値だけではなく、解約率、再購入率、顧客生涯価値といった長期的な指標を重視します。実務の現場では、まず顧客視点で痛点を深掘りし、次に顧客起点として組織の制度やプロセスを整えます。こうすることで、個別の改善と組織の変革が同時に進み、結果として顧客との信頼関係が強化されます。くどい説明になりますが、両方を意識的に組み合わせることが理想的です。
実務の進め方
実務でこの二つの考え方を使い分けるには、ステップをはっきり決めることがコツです。まず第一に、顧客視点の観察を行い、現場で起きている具体的な痛点を洗い出します。次に、痛点ごとに解決策を仮説化し、ユーザーテストや観察で検証します。テストの結果を踏まえ、短期の改善と同時に顧客起点の変更が必要な部分を特定します。例えば、予約の流れが複雑なら、UIの簡素化と同時に予約時点でのサポート体制を再設計します。組織の制度面にも手を加え、評価指標を顧客起点の長期指標へ連動させる仕組みを導入します。最後に、改善の成果を共有する透明性を高め、全員が顧客の声を日々の業務の中心に置けるよう仕組みを整えます。
まとめと実務のポイント
顧客視点と顧客起点は、似ているようで別物です。前者は日々の接点での体験を磨くための観察力を強化します。後者は組織全体を顧客のために動かす力をつくる戦略です。現場ではまず顧客視点で痛点を把握し、それを出発点に顧客起点の方針を組織に浸透させる。これを繰り返すと、短期の満足度だけでなく長期的な信頼と価値の創出が実現します。最後に大切なのは、データと人の両方を活用することです。定性的な声と定量的な数字を合わせて読み、新しい施策を試し、結果を共有して学習を続ける。
今日は友だちと雑談風に顧客起点の話をしてみるね。顧客起点って、ただお客さんの声を拾うだけじゃなく、店の仕組み全体をその声に合わせて作り直すことだと思うんだ。具体的には、朝の混雑時でも注文から受け取りまでの流れを滑らかにするには、厨房の動線やスタッフの配置、配送のタイムラインまで見直す。こうして顧客の生活ペースに合わせたサービスを提供すると、客は“また来たい”と思う。これは短期の売上だけじゃなく、長い付き合いを生む土台になるんだよ。
次の記事: 知的財産と知的資源の違いを徹底解説:身近な例で学ぶ基本と活用法 »





















