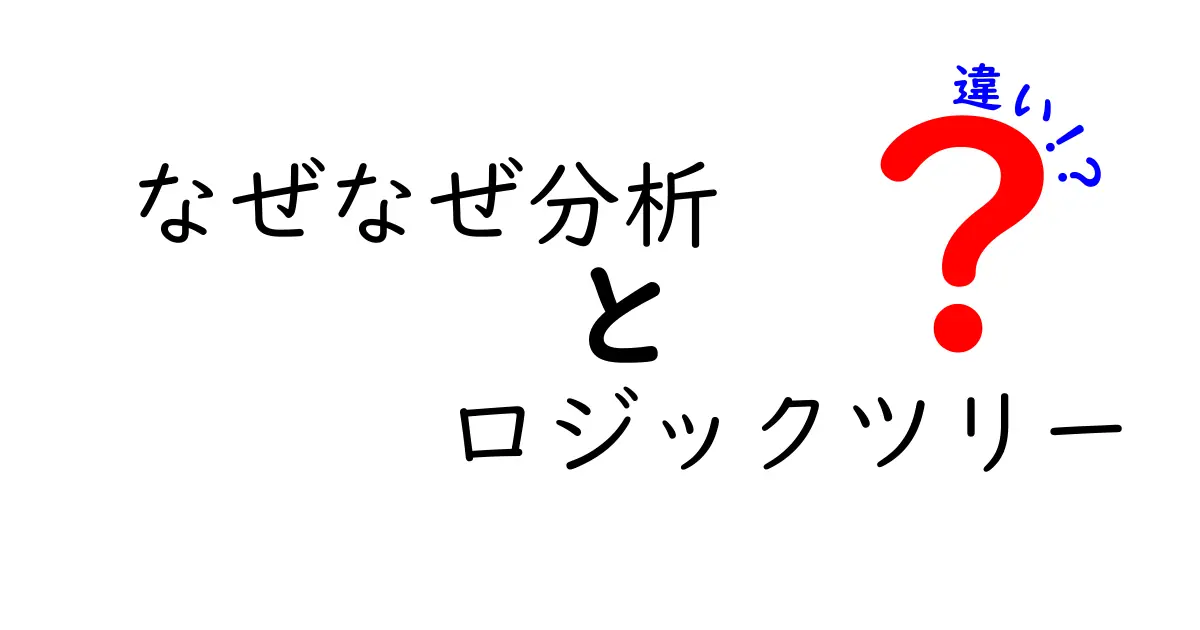

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
なぜなぜ分析とロジックツリーの違いを理解するための基礎
このセクションでは なぜなぜ分析 と ロジックツリー の基本的な性質を比べて、どんな場面でどちらを使うべきかを理解します。まず なぜなぜ分析 とは何かを押さえ、続いて ロジックツリー の考え方を確認します。なぜなぜ分析は問題の原因を深掘るためのシンプルな技法であり、原因と結果の連鎖を追う小さな木のように思える場合が多いです。手順は非常に単純で、問題を切り分けていくとき最初の一歩として有効ですが、同時に 複雑な要因を過不足なく整理するには不向き なこともあります。ロジックツリーは一方で、問題を木の形に階層化して整理する手法です。要因を下位要因まで分解し、結果を説明できるように組み立てます。時間はかかることもありますが、データを伴う分析や複雑な因果関係の可視化には強い力を発揮します。
上手に使うコツは、最初に根本原因を探る際に安易な仮説に走らないことです。なぜなぜ分析はしばしば 仮説の検証不足 に陥りがちなので、データを集め、第三者の視点を取り入れる ことが重要です。一方のロジックツリーは全体像を見渡す力を高めます。木の形に分解していくと、個々の分岐がどの根拠で成立するかが見え、証拠と仮説の結びつき が強まります。実務では、この二つを組み合わせて使うケースが多く、まずなぜなぜ分析で仮説の候補を絞り、次にロジックツリーで構造を整理します。
実務での使い分けのポイントを押さえる
この章では 根本原因と高次の構造 という二つの見方を並べて理解します。なぜなぜ分析は直感的で迅速に着手しやすく、初動の意思決定を支えるのに向いています。反対にロジックツリーは問題を木の形で分解することで、因果関係の全体像を把握しやすく、複雑な課題の整理に強いです。実務では両方を順序立てて使うことで、現場の混乱を抑えつつ根拠を積み上げることができます。さらに具体的な例として、工場の品質問題を取り上げ、まずなぜを五回問う段階で仮説を絞り込み、次に各因子を木の枝として整理する手順を想像してみましょう。仮説はデータや観察から検証されるべきであり、疑問点はすぐに他の人と共有して修正します。ここで重要なのは、仮説を内輪で固めすぎず、外部の視点を取り入れて反証を受け入れる姿勢です。最後に、学習のコツとしては具体的な事例で練習を重ね、結果をチームで共有してフィードバックを受けることです。
ロジックツリーの話をしてて思い出したんだけど、宿題の謎解きっていうのは結局、原因を木の枝のように広げていく作業だよね。友だちと話していると、枝ぶりが複雑になると肝心なことが見えなくなる。そんなとき僕は必ず根っこに戻って、最初の問いを一本化する。ロジックツリーは頭の中の木を実際の紙に落とすと、見落としが減るし、他の人にも伝わりやすい。もちろん時間はかかるけど、根拠のある結論を出すのに役立つから、授業の討論にも強くなるんだよ。





















