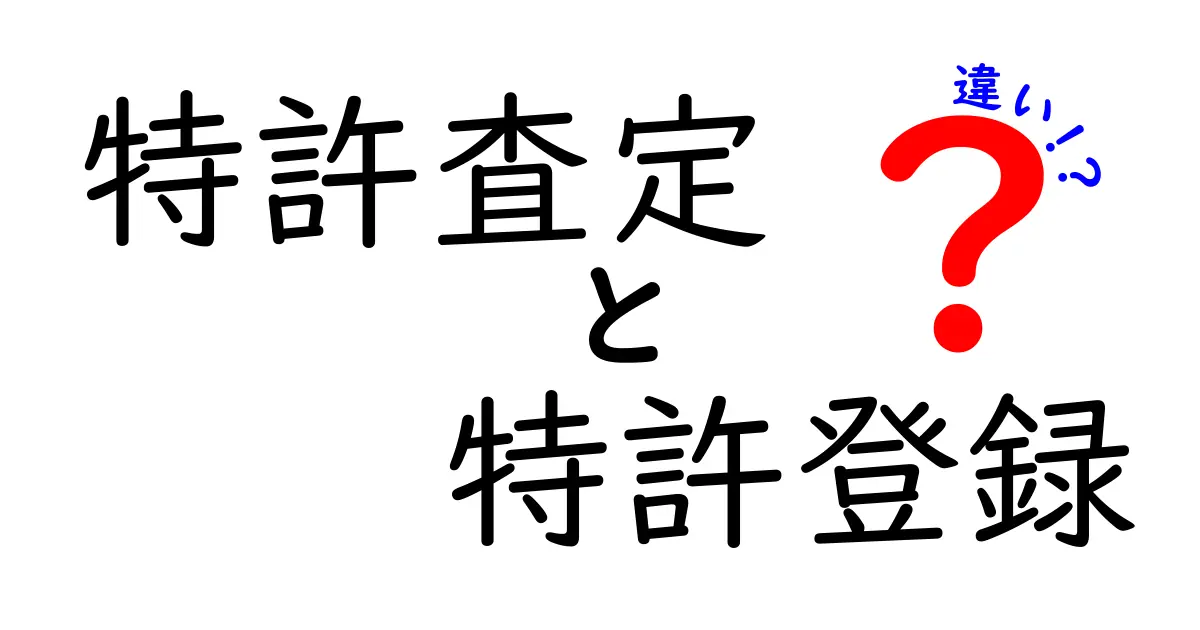

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
特許査定と特許登録の違いを理解しよう
特許を守る仕組みにはいくつかの段階があり、その中でも特許査定と特許登録はとても重要な2つの言葉です。ここでは難しい専門用語をできるだけやさしく解きほぐします。結論から言うと、査定は審査の結果を知らせる通知であり、登録は正式に権利を付与する手続きの完了を意味します。つまり査定は権利の可能性を示す段階、登録は権利が実際に生まれる段階です。これを正しく理解すると、申請の計画を立てやすく、費用や期限を正確に管理できるようになります。本文では、順を追って違いを詳しく解説します。
企業や研究者にとっては、査定と登録の違いを混同しやすい場面が多いですが、実務では手続きの順序や法的効果、費用、期限などを区別することが大切です。読み進めるうちに、あなたが狙う成果がどの段階で得られるのかが自然と見えてくるでしょう。
特許査定とは何か
特許査定は、出願を審査した結果、特許庁がこの発明は新規性や進歩性、実用性の要件を満たしている可能性が高いと判断した段階を指します。ここではまだ正式な権利が確定しているわけではなく、あくまで許可の見込みを知らせる通知です。
この通知を受けても、権利が確定したとは言えませんので、出願人は引き続き次の手続きである登録請求へ進む必要があります。査定が出た瞬間に安心してしまわず、期限や補正の準備を整えることが重要です。査定の段階で指摘された事項を修正することで、最終的な権利化の可能性を高めることができます。
また、査定の通知には発明の技術的特徴や請求項の範囲、引用文献などの検討が含まれ、必要に応じて出願内容の補正が求められることがあります。審査の過程は研究開発の現場にも影響を与え、どの程度の新規性があるかを客観的に見つめ直す良い機会になることもあります。査定の結果を待つ間は、他の知財戦略を並行して準備するのが賢い方法です。
特許登録とは何か
特許登録とは、特許査定の通知を受けた後に、正式に特許権を成立させるための手続きです。登録請求を行い、登録料を支払うことで、発明に対する排他的な権利が発生します。登録の成立が実際に権利を得る瞬間であり、ここから20年程度の有効期間を維持するための年金・維持費の支払いが続きます。
登録が完了すると、特許庁から登録証明書が発行され、権利者は製造・販売・使用に関して他者を排除できる法的権利を得ます。なお、登録請求には期限が設定されており、期限を過ぎると出願が取り下げられるリスクがあります。企業や研究機関にとっては、費用計画と事業戦略の整合性が大切なポイントです。
両者の違いを表で比較
これまでの説明をわかりやすく表にまとめておきます。以下の表は意味や時期、権利の発生、費用の性質、期限の要点などを比較しています。表を見れば、査定と登録が別物である理由が一目でわかります。
表の各項目を理解することで、申請計画を立てやすくなります。特許査定と特許登録はセットで考えるべきですが、権利の発生時点と手続き側の違いを理解することが最初の一歩です。さらに、費用の見積もりや期限管理は、研究開発のスケジュールと緊密に結びついています。
まとめと実務のポイント
要点を簡潔にまとめると、特許査定は審査の結果を示す通知、特許登録は権利を正式に確定させる手続きです。この2つは、手続きの順序が違うだけでなく、権利の発生時期・費用の性質・対応すべきリスクが異なります。研究開発の現場では、査定の結果を待つ間にも、補正の準備や特許性の向上を図る作業が続きます。査定後は、期限内に登録請求を行い、必要な費用を納付することが大切です。もし期限を過ぎてしまうと、出願が取り下げられたり、権利化の機会を失う可能性があります。
実務上のヒントとしては、申請時には明細書の範囲を適切に保ち、クレームの幅を現実的な範囲に設定すること、公知技術の最新動向を把握し、補正の準備を前もって進めること、そして費用や期限の管理をチームで共有することが挙げられます。これらを実践することで、研究成果を確実に守り、他者との競争力を高めることができます。
学校の帰り道、友達と特許の話をしていて、特許査定と特許登録の違いについて深掘りすることになった。査定は審査の結果を知らせる段階であり、まだ権利は確定していない。この段階で重要なのは補正と品質の向上だ。登録はその後の手続きであり、費用を払い権利を正式に得る瞬間だ。私たちは研究成果をどう守るかを考えながら、実際の申請計画を立てる準備をしていた。もし期限を過ぎれば権利化の機会を逃すことになるため、期限管理の大切さも実感した。
前の記事: « 実用新案と意匠の違いを徹底解説!誰でも分かる見分け方と取得のコツ
次の記事: 著作隣接権と複製権の違いが一目でわかる解説|誰が何を許されるのか »





















