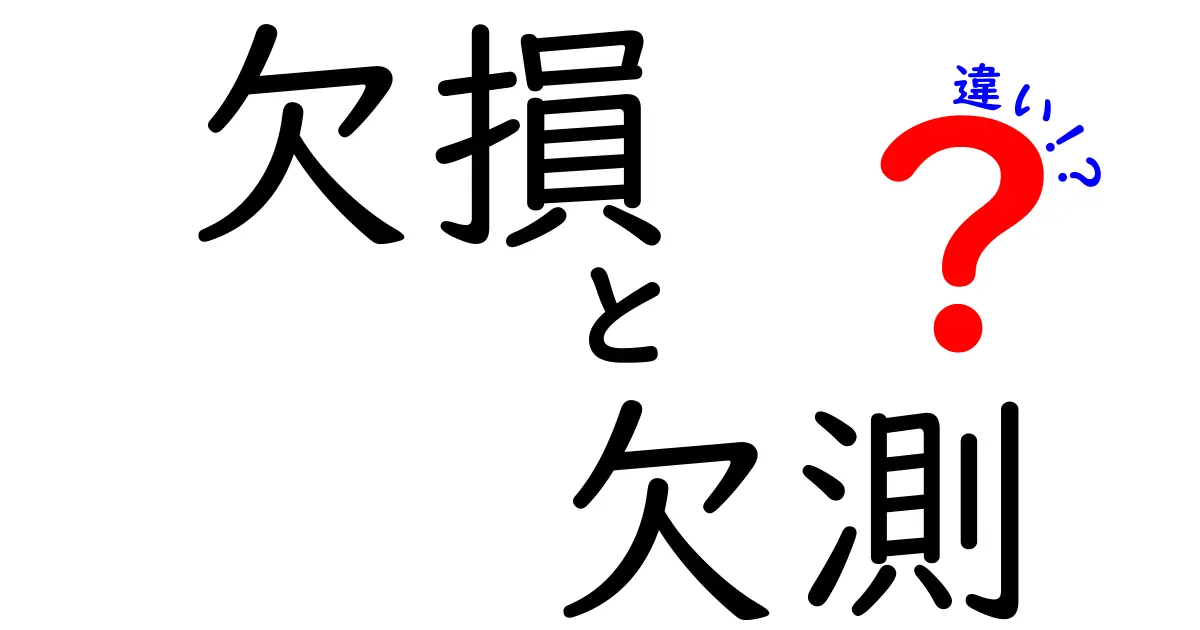

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
欠損と欠測の違いを正しく理解するための全体像
欠損と欠測は似ているようで意味が違います。この二つの用語を正しく使い分けられると、データ分析や報告書の信頼性がぐんと上がります。日常生活では『データが不足している状態』を指すことが多い欠損と、研究や調査の現場で『測定や記録が行われていない・できなかった状態』を指す欠測。ここでは、二つの語の基本的な捉え方、使われ方、そして実務でどう扱うべきかを、身近な例や表を交えて丁寧に解説します。まずは概念の違いを押さえましょう。欠損は“データがそもそも存在しない”ことを強調する言葉として使われがちです。欠測は“測る、記録するという行為自体が抜けている”と理解するとわかりやすいです。分析の現場ではこの差が分析結果の解釈やデータの前処理、モデルの選択に影響します。
ここからは具体的な例と、どう扱うべきかのポイントを順を追って見ていきます。次の節では、欠損と欠測を分けて考える基本の枠組みを紹介します。
欠損とは何か
欠損とは、データ分析でいうと「本来はここに値があるはずなのに、何らかの理由で値がない状態」を指します。たとえばアンケートで年齢の回答が抜けた、学力テストの一部の採点が欠けた、ログデータで一部のエントリが記録されていない、などが該当します。欠損はしばしばデータの分布を歪め、平均値を過大/過小に見せる原因になります。欠損が発生する理由にはさまざまなケースがあり、無作為に起こる場合もあれば、特定のグループに偏ることもあります。この「欠損の原因」を理解することが、適切な補完方法を選ぶ第一歩です。補完方法には欠損の機構を踏まえた選択が求められます。例えば、単純に平均値で埋める「平均補完」はMCARの状況では安易かつ適切である場合がありますが、MARやMNARのケースでは偏りを生む可能性が高いです。データを扱う際には、欠損の程度と分布をまず把握してから意思決定を行いましょう。
欠測とは何か
欠測とは、測定や記録の行為自体が欠けている状態を指します。現場での理由としてはセンサーの故障、調査票の回答が途中で止まった、データ転送の失敗、あるいは倫理的な配慮で特定の情報を収集しなかった等が挙げられます。欠測は「値がない」という状態を表すだけでなく、何がどう欠けているのかを詳しく考える必要があります。欠測が生じる場面を特定することで、データ収集の設計を改善したり、後の分析での前処理方針を決める材料になります。例えば、センサーの欠測は機器の保守スケジュールと連動することが多く、補完の前にデータの品質チェックを厳格に行うべきです。倫理上の問題で欠測が起きる場合は、欠測が発生した背景を説明する透明性が重要です。分析上は欠測自体を単純にデータの“空白”として扱うのではなく、欠測の意味を理解したうえで適切な解析手法を選択することが求められます。
欠損と欠測を混同すると、分析の前提がぶれてしまいます。欠損と欠測は意味の中心が異なるため、何が欠けているのか、どうして欠けているのかを確認する癖をつけることが大切です。理解が深まれば、補完の方法を選ぶ基準が明確になり、データの信頼性を保つ判断が素早くできるようになります。
欠測というキーワードを深掘りする小ネタです。実は欠測には、データを作る仕組みを考えるときの“見え方の差”が隠れています。データが欠ける理由は機器の故障だけでなく、回答者の意図や調査設計の制約にも影響されます。たとえばウェブ調査で長い回答や自由回答の欄が空になるとき、単純な欠測以上のニュアンスが生じます。そのとき私たちは「欠測のパターン」を観察して、どの場面で影響が大きいのかを推測します。これを踏まえると、欠測をただの空欄として扱うのではなく、欠測がどんな情報を伝えようとしているのかを読み解く姿勢が大切です。データ分析の現場では、欠測を説明する短い注記を添えることが、データの透明性と再現性を高めるコツだと感じます。





















