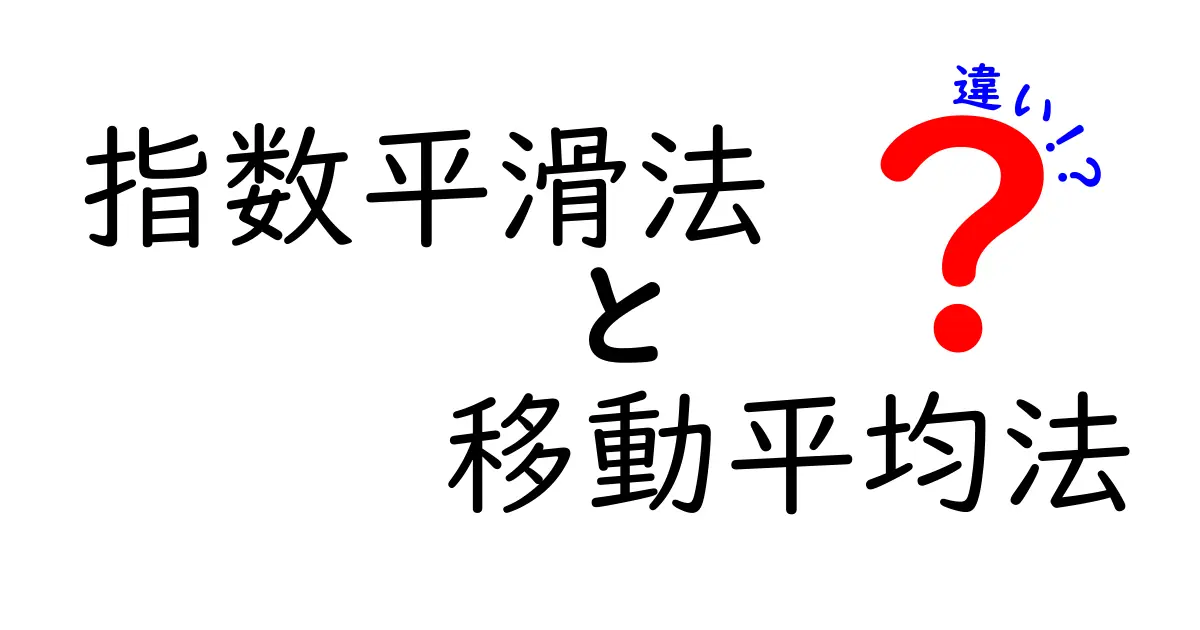

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
指数平滑法と移動平均法の違いをわかりやすく解説
ここでは「指数平滑法」と「移動平均法」の違いを中学生にも理解できるように丁寧に説明します。まず基本の考え方から始めましょう。
「指数平滑法」は最近のデータに重みを多く置くことで新しい情報を早く反映させ、移動平均法は一定期間のデータを平均して取り出すため、変化を滑らかに見せます。
この違いは予測の速さと安定性に直接関係します。
例えば売上の推移を観察すると、急なジャンプには指数平滑法が敏感です。これに対して移動平均法は急な変化を抑え、長期的な傾向を見やすくします。
この性質はデータの性質を見極めるときの重要な手がかりになります。
さらに重要なのは、実装の簡便さと計算コストです。指数平滑法は計算が軽く、1つのパラメータαを決めればすぐに予測値を作れます。一方で移動平均法は窓の幅を設定するだけで使えますが、窓が大きいと遅れが生まれやすい点に注意が必要です。
データの特徴に合わせてαや窓幅を選ぶことが、良い予測へつながります。
この記事ではこの2つの手法の違いを軸に、実務での使い分けのコツを次の段落で詳しく解説します。
具体的な仕組みと使い方のポイント
ここからは実際の数値イメージと基本的な使い方を説明します。指数平滑法の基本は前回の予測値と現在の観測値を組み合わせることです。
例えばαが0.2のとき、次の予測は前回の予測を0.8倍、現在のデータを0.2倍で足し合わせる形になります。
このようにαの値を変えると予測の敏感さが変わります。
移動平均法は窓幅Nを決め、N日間のデータを平均します。
新しいデータが加わるたびに窓を1日分ずらすと最新の情報を反映しつつノイズを減らします。
窓幅が大きいほど平滑化が強くなり、急な変化は見えにくくなります。
実務では誤差指標MAEやRMSEを使ってモデルを評価します。
同じデータセットで複数の手法を試し、指標が小さい方を選ぶのが基本です。
さらにハイブリッド手法として短期と長期の両方を捉える工夫もあります。
友達とデータ分析の宿題をしているとき、指数平滑法と移動平均法の違いが会話のテーマになりました。指数平滑法は最新データを強く反映するためにαという重みを決めるだけで実装でき、計算も軽いのが魅力です。移動平均法は一定期間のデータを平均することでノイズを抑え、全体の形を見やすくします。二つは性格が違う道具なので、どう使い分けるかが勝負の分かれ目です。例えば急な売上の跳ね上がりがあっても、指数平滑法なら即座に反映され、移動平均法なら滑らかに動きます。私はこの違いを友達と実験的に試して、窓幅やαを変えたときのグラフを比べるのが楽しいと気づきました。データをただ追うのではなく、道具の特性を活かして適切な癖づけをすること、それがデータ分析の第一歩だと感じました。





















