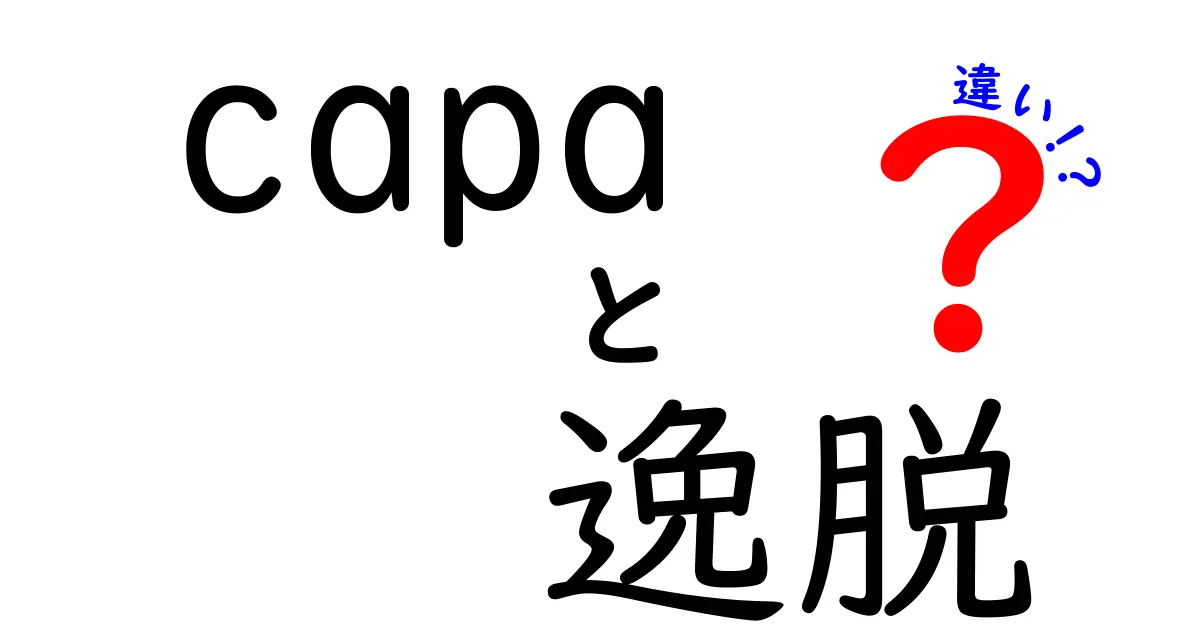

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
CAPAと逸脱の違いを正しく理解する
CAPAと逸脱は日常生活にはあまり馴染みのない言葉かもしれませんが、品質管理の現場では欠かせない考え方です。CAPAは“Corrective and Preventive Action”の略で、発生した問題の原因を深掘りして再発を防ぐための具体的な行動計画を指します。一方、逸脱は「標準・規格・手順から外れた状態」を示す事実の記録です。ここで大切なのは、逸脱が事実を知らせる情報であるのに対し、CAPAはその情報を元に改善を実施するプロセスであるという点です。
この二つを正しく使い分けると、組織の品質を守りやすくなります。
CAPAの基本的な流れは、問題の認識、原因の特定、是正措置の実施、そして予防措置の計画の四つのステップが組み合わさって基本サイクルを成します。逸脱はこのサイクルの出発点として重要で、現場で起きた事象を記録することで、後の分析につなげられます。CAPAと逸脱の関係を一言で言えば、逸脱は「何が起きたかを教えてくれる情報」、CAPAは「その情報をもとにどう直すかを決める行動計画」です。
CAPAとは何か
CAPAは品質マネジメントの中核をなす考え方で、企業が法令や顧客要求に適合するための重要な仕組みです。原因分析、是正措置、予防措置の三つが基本要素です。まず問題が発生した際には、影響を受ける製品、工程、担当者を特定します。次にデータを集め、根本原因を突き止める分析を行います。原因が特定できたら是正措置として具体的な修正を行い、同じ問題が再発しないよう予防措置を設計します。CAPAは一度きりの修正ではなく、組織全体のプロセスを見直す「改善の継続サイクル」です。
実務の現場では、CAPAを「文書化」「責任者の割当」「期限設定」「追跡・検証」という流れで運用します。例えば、製品Aに欠陥が見つかった場合、まずどの工程で欠陥が発生したのかを特定します。次に原因を分析し、是正措置を実施します。最後に、同様の欠陥が起きないかを監視する指標を設定し、定期的に効果を評価します。こうしたステップを守ることで、顧客の信頼を守り、法令遵守にも寄与します。
逸脱とは何か
逸脱は「標準・規格・手順から外れた状態」を指す事実の記録です。現場で起きた出来事を正確に記録することが第一歩です。逸脱は必ずしも悪い結果を意味するわけではなく、問題の早期発見と改善の出発点になります。逸脱が発生すると、責任者へ報告し、影響範囲を評価します。場合によっては規制当局への届出や顧客通知の要件が出てくるため、適切な手順に従うことが求められます。
逸脱には「軽微なもの」と「重大なもの」があり、対処方法は異なります。軽微な逸脱は一時的な修正や追加のトレーニングなどで対応することが多いですが、重大な逸脱は製品の安全や法令遵守に直接関わるため、上位の承認と厳格な対策が必要です。逸脱を単なるミスとして片づけず、原因を深掘りして再発防止策を設計することが重要です。
違いを理解する重要ポイント
ポイントを整理すると、CAPAと逸脱は次のような役割の違いがあります。逸脱は現象の事実を記録するもの、CAPAはその記録を受けて改善を実行するプロセスという組み合わせです。逸脱を正確に記録することが、CAPAの第一歩になります。CAPAは原因分析と対策のセットであり、再発防止の観点から手順の改訂や監視指標の設定を含みます。これらを組み合わせると、品質の安定性が高まり、顧客満足度の向上にもつながります。
以下の表は、両者の違いを見やすくまとめたものです。なお、実務ではこの違いを理解して日常的な改善活動に落とし込むことが重要です。
実務での活用ポイント
最後に、学校の授業や部活、アルバイト先の現場など、日常生活の場面にCAPAの考え方を取り入れるコツを紹介します。まずは「何が起きたのか」を正確に書き出すことから始めましょう。次に「なぜ起きたのか」を想像し、データを集めます。最後に「どう直すか」を具体的な行動として決め、責任の所在と期限を決めます。そうすることで、同じ問題が繰り返し起こるのを防ぐことができます。CAPAは難しい言葉に見えますが、実は日常生活の「原因を探して改善する」考え方そのものです。
- 原因を正しく特定する力がつく
- 再発防止のための具体的な行動が決まる
- チーム全体で問題解決の文化が育つ
今日は友達と部活の話をしていたとき、CAPAと逸脱の話題が出てきました。最初は難しい単語だと思ったけれど、要するに“問題が起こった原因を深掘りして、同じことが起きないようにする仕組み”という点で共通していることに気づきました。逸脱は現場で起きた事実そのもので、CAPAはその事実を受けて改善策を作る行動計画です。部活の道具が壊れたとき、まず逸脱として記録し、原因を分析して、次回は壊れにくい使い方を確立する。そんな一連の考え方が、将来社会で役に立つはずです。だからこそ、日常の小さな失敗も恐れず、丁寧に記録して、改善していこうと思います。





















