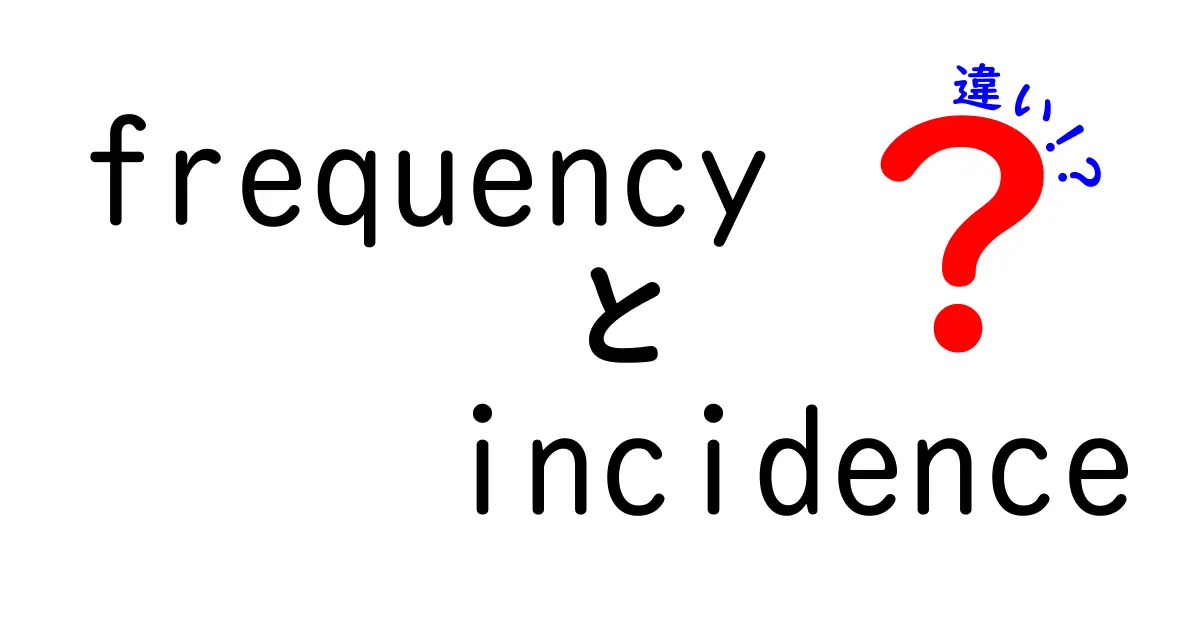

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
frequencyとincidenceの違いを徹底解説!中学生にもわかる読み解きガイド
データの世界には frequency と incidence という似て非なる言葉があり、統計の読み方を大きく左右します。学校の成績データ、部活動の参加者数、地域の病気の流行など、身の回りにはさまざまなデータがあふれていますが、これらを正しく解釈するにはまず用語の意味をはっきりさせることが大切です。
frequency は「ある期間に起こった出来事の総回数」を数える指標であり、観察の期間と対象の人数をそろえることで比較が可能になります。たとえば1学期の間にテストの点数が何回上がったか、あるクラスの出席回数がどう変化したか、といった観察がそれにあたります。ここで大切なのは、頻度はあくまで“総数”を示すものであり、時間や母集団の大きさによって見え方が変わるという点です。
一方の incidence は「新しく起こった事象の発生割合」を指す指標で、特定の期間における新規ケースの生まれやすさを示します。たとえば新しい磁石を配布したとき、何人が初めてその磁石を持つようになったかという新規の発生を追います。ここで大切なのは、発生率を語るときに「母集団の大きさ」や「観察期間」を明示することです。さもなければ、2つのデータを同じように見積ってしまい、誤解の原因になります。学校の授業での出席者数を例にとると、全員が出席した回数の総和が頻度、初日に欠席してから復帰した人の割合を出すと発生率のイメージになります。これらの例から、頻度は「起きた出来事の総数を数える」こと、発生率は「新しく起きた事象の割合を測る」こと、という違いがはっきり見えてきます。
この説明を頭に入れておけば、グラフを読んだとき「なぜこの値が大きいのか」「どちらの指標を使えば比較がしやすいのか」がすぐ分かるようになります。
ねえ、frequencyとincidenceの話、難しく聞こえるかもしれないけど、実は日常の学校生活にも置き換えると分かりやすいんだ。頻度は“この期間に起こった出来事の回数そのもの”だから、例えば体育の時間に何回シュートが決まったか、という“回数”を数えるイメージ。発生率は“新しく起こった事象の割合”を示すから、例えば新しく部に入る人の割合や、新規感染者の割合を考えるときに使うんだ。観察する人数や時間が変わると数え方が変わる点がポイント。僕らが友達と話すときにも、頻度と発生率の違いを意識して話すと、伝わりやすくなるよ。周りのデータを見たとき、どちらの指標を使えば伝わりやすいかを一度考えてみよう。なお、同じデータでも使う指標を変えると見える意味が大きく変わるので、最初の一歩として両者の意味をしっかり押さえることが大切だね。
次の記事: 売約と成約の違いを徹底解説!初心者でもわかりやすい3つのポイント »





















