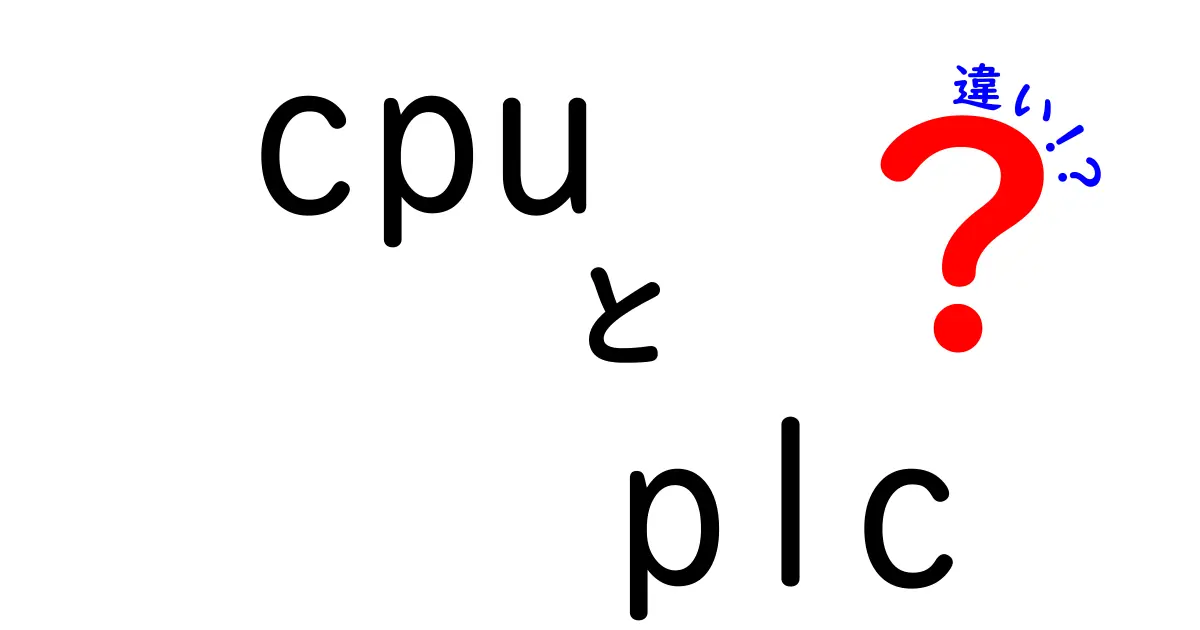

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
CPUとPLCの違いを徹底解説!現場での使い分けと選び方を分かりやすく解説
前提:CPUとPLCの基本を押さえる
CPUとは中央処理装置のことで、主にコンピュータの中枢として動作します。
一方 PLCとは現場の自動化機器を制御するための専用の装置です。
この2つは似ているようで目的と動作環境が大きく異なります。
この違いを理解するにはまず用語の整理が必要です。
CPUは汎用性が高く複雑な計算やデータ処理を行いますが、PLCは現場の信号の読み取りと出力制御に特化しています。
リアルタイム性や信頼性を求められる場面が多い現場ではPLCが選ばれやすく、PCやサーバー上のCPUはデータ処理や分析に適しています。
この差を知ることで新しいシステムを設計する際の見積もりやスケジュール感が変わります。
CPUとPLCは同じ会社の機器でも連携しますが、通信プロトコルやデータ形式の違いがボトルネックになることがあります。
代表的な違いとしては実行環境の安定性、リアルタイム性の保証、拡張性の方向性が挙げられます。
このセクションの要点は、機械を動かす前提としてどちらを中心に据えるかを決める指針を持つことです。
現場の要件を整理すれば、CPU中心の監視システムと PLC中心の直接制御の2つの設計パスを比較できるようになります。
さらに、以下のポイントも念頭に置いてください。
- 汎用性が高いCPUは複雑なロジックやデータ処理に強い
- 現場適性の高いPLCは耐環境性と信頼性が向上
このバランスが現場での最適解を生み出します。
根本的な違いを理解する
ここでは技術的な観点での違いを深掘りします。CPUは汎用の計算能力を提供するため、OSの存在、スケジューリング、メモリ管理といった要素が絡みますが、PLCはリアルタイム性を最優先します。
リアルタイム性とは、信号の変化に対して決められた時間内に応答する能力のことです。PLCはこの点で determinism が高く、時間の予測が立てやすい設計になっています。
この違いが現場の制御ループの安定性に直結します。
さらにプログラミングの観点でも違いが出ます。CPUはCやPythonといった一般的なプログラミング言語を使いますが、PLCはラダー言語やファンクションブロックといった現場寄りの言語が主流です。
このため、運用コストや人材の教育にも影響が出ます。
表現方法としては両者を同時に扱うケースが増えています。例えば、現場のI/OをPLCで直接制御し、データをCPU上のデータベースで分析するといったハイブリッド構成です。
このような組み合わせは柔軟性を高めますが、通信設計とタイミング設計を丁寧に行わないと遅延や同期の問題が発生します。
つまり、どのタスクをどのデバイスに割り当てるかが設計の肝になります。
現場での使い分けと選び方
現場の要件を整理することが最初の一歩です。作業の自動化範囲、信頼性の程度、保守のしやすさ、予算の制約などを整理することでCPU寄りかPLC寄りかの判断がしやすくなります。
例えば、複数の機械を連携させながらデータを収集し、リアルタイムの監視だけをCPUで行うといったパターンがあります。
また、PLCを中心とする設計でも、上位の監視システムと連携してデータ可視化を行うことで現場の意思決定を迅速化できます。
適切な選定をするには以下の観点を押さえると良いです。
- リアルタイム性の要件と決定性の程度
- 環境条件と筐体耐久性
- プログラミングの習熟度と教育コスト
- 拡張性と将来のメンテナンス性
- コストと導入スケジュール
このセクションの要点は、現場のニーズに対して最適な“中心装置”を選ぶための指針を持つことです。
ただし実務ではCPUとPLCを組み合わせたハイブリッド設計が一般的になっており、それぞれの強みを活かすことが成功の鍵となります。
僕たちは日常の雑談の中でよくCPUとPLCの話題をします。例えば授業で作る小さなロボットカーの話。CPUが道具としての“考える頭”だとしたら、PLCは現場で“ボタンを押して機械を動かす指揮官”のような存在だと思います。 PLCの世界では現場の信号を読み取り、条件が揃えば即座に出力を変える。CPUは複雑な計算とデータ処理をこなします。この2つをどう組み合わせるかで、システムの信頼性と柔軟性が大きく変わるのです。





















