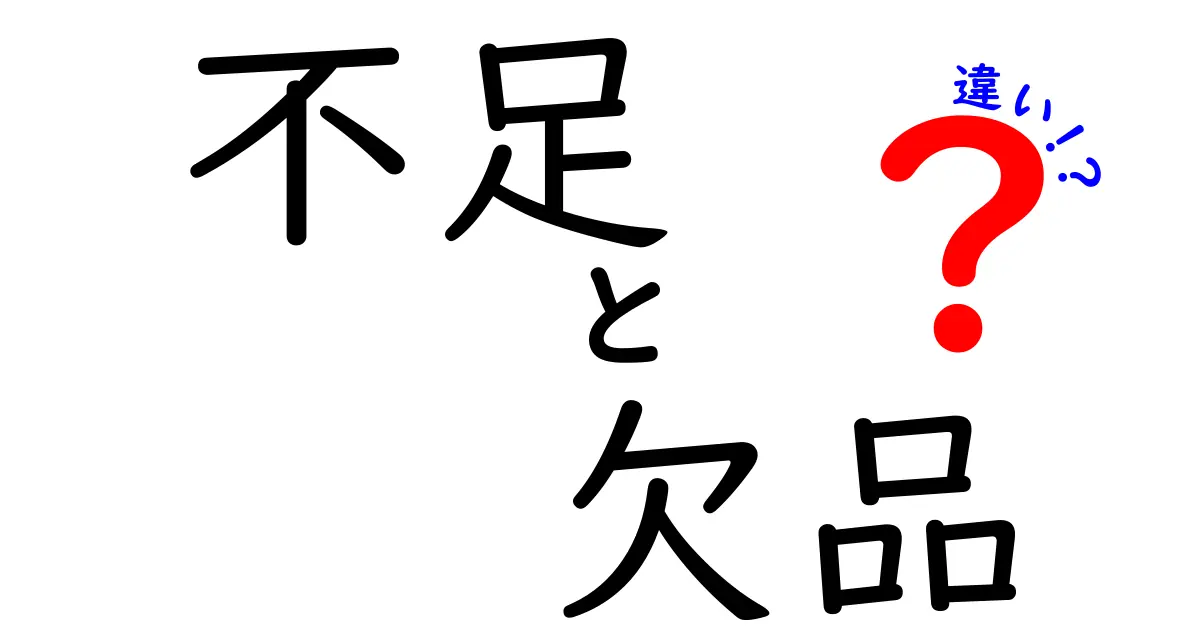

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
不足・欠品・違いの基本を理解する
ここではまず3つの用語の基本を押さえます。不足は全体の量が必要量に満たない状態を指します。部活用品が足りず練習が続けられないとき、学校の給食材料が不足している場合など、需要(使いたい人の数)と供給(用意できる量)の差が原因です。
この差は天候の影響や季節変動、発注ミス、工場のトラブルなど、さまざまな理由で生まれます。
一方欠品は在庫が0に近い状態、実際には倉庫や店舗の棚にその品がなく、次の入荷を待つ状况を指します。欠品が起こると、販売機会を逃したり、顧客の信頼を損ねたりします。
つまり不足と欠品の違いの視点は「管理の視点」と「現場の状況」にあります。
違いを理解することは、発注の安定、顧客対応の改善、業務のスムーズ化につながります。
用語の違いを分かりやすく覚えるコツ
不足と欠品を頭の中で分けるコツとして、不足は「全体の量が足りない状態」であり、需要と供給の差が原因です。
欠品は「棚や倉庫に品がなく、入荷待ちの状態」です。覚え方としては、不足は「不足分を埋める努力が必要」=調整・予測・発注点の設定、欠品は「今は手に入らないだけ」=品切れ情報と入荷通知を活用、つまり計画と情報管理の違いだと覚えると混乱が減ります。日常の例としては、学校のパンが不足しているというときは教室全体の消費量を見直すこと、欠品は店頭でパンが売り切れているが次の日には入荷すること、といった状況です。これらのイメージを持っておくと、ニュースやニュースのコメントで不足と欠品の話を聞いたときにすぐ理解できます。
現場で起こる具体的な例と対策
現場では不足と欠品が同時に起こることも珍しくありません。例えば学校の給食で野菜が不足する場合、調理に使う野菜の需要が急に増え、供給が追い付かなくなると不足が生まれます。ここで大切なのは「需要予測と安全在庫」の組み合わせです。需要予測を正しく行えば、どの材料がどのくらい必要かを前もって知ることができます。安全在庫とは、通常の発注量に対してさらに少し余裕を持つ在庫のことで、急な需要増にも対応できます。
欠品を減らすには、発注点を適切に設定し、サプライヤーと連携して代替品の準備や入荷スケジュールの共有を行うことが効果的です。日常的な対策としては、在庫管理表を毎日更新する、入荷予定を全員に共有する、欠品情報を即座に顧客へ伝える、などの基本が重要です。これらの取り組みは、売上を守り、信頼を保つ基本となります。
また次の表を使って不足と欠品と違いのポイントを整理します。
このように「不足」「欠品」「違い」を分けて考えると、原因を特定しやすく、対策も具体的に立てやすくなります。
最後に覚えておくべきポイントをまとめます。
不足は全体の量の不足、欠品は棚や倉庫の在庫切れ、違いは視点の違い。これを常に意識するだけで、スケジュール管理や購買計画がぐんと安定します。
欠品とは今その商品が手元にない状態のこと。でも背後には発注の仕方、入荷のタイミング、代替品の準備、顧客への連絡のタイミングが絡んでいます。欠品を減らすには需要の予測を見直し、入荷通知を活用し、サプライヤーとの信頼関係を築くことが大切。ちょっとした工夫で欠品は減らせる、という実践的な話を雑談風に語ります。





















