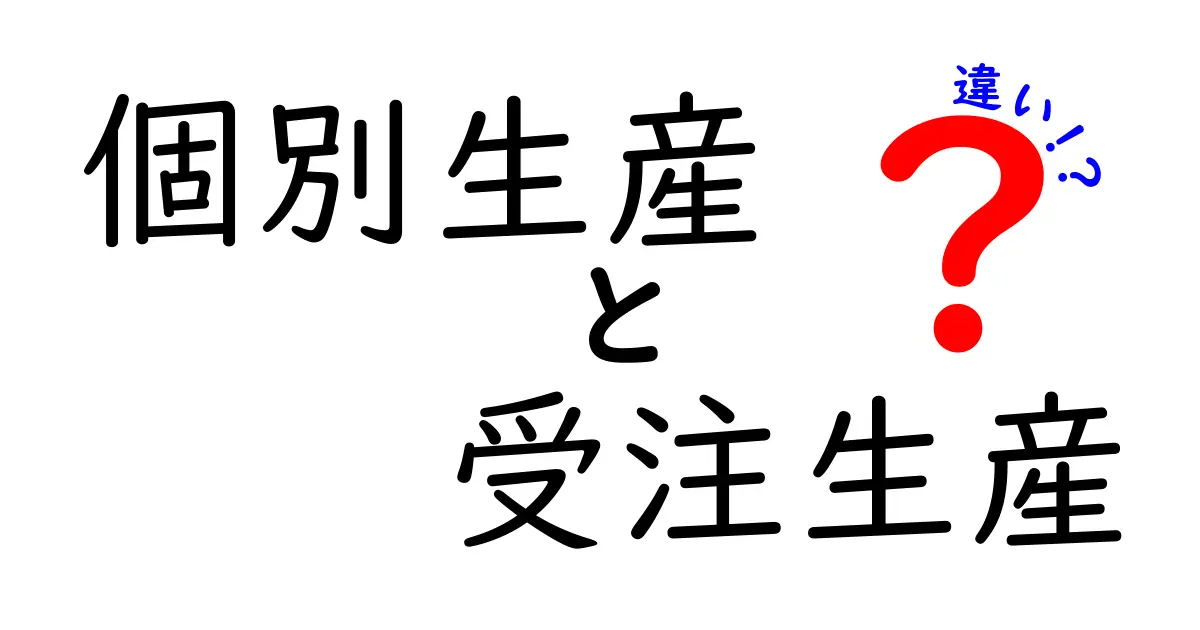

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
個別生産と受注生産の違いを理解する基本
「個別生産」と「受注生産」は、生産の考え方の違いを表す言葉です。個別生産は、型にはまらず一品ずつ作るイメージで、設計から加工、仕上げまでを一つの品物として完結させることが多い製造方法を指します。これに対して受注生産は、お客様の注文を受けてから生産を開始する方式で、在庫を持たず、需要が確定してから材料や工程を動かします。こうした違いは、製品の特性、需要の変動、資金繰り、在庫管理の方法に大きな影響を与えます。実際の現場では、家具職人の一品物や布製品の特注など、様々な場面でこの二つの考え方が混在しています。
例えば、顧客の希望する色やサイズ、機能を細かく指定してもらい、設計図を作成してから加工を進めるのが個別生産の典型です。この場合、同じ型の別の品番を作るときにも設計と準備に時間がかかりやすいため、納期が長くなることがあります。さらに、完成品は世界で一つだけの特徴を持つため、顧客満足度が高くなる一方で、コストの上昇と在庫のリスク低減のバランスで経営判断が難しくなることもあります。
一方、受注生産は顧客の注文が確定した段階で材料を発注し、組み立て・検査・出荷までの流れを整えます。在庫過剰のリスクを減らせる反面、注文の取りこぼしを防ぐ工夫が必要で、受注後の生産計画を速やかに立てる能力が求められます。実務では、受注状況をリアルタイムで把握できるITシステムや、発注・生産・納品の一連の動きをつなぐ生産管理が重要です。
仕組みと流れの違い
「個別生産」と「受注生産」の流れを図にすると、最初の設計・仕様確定の段階、資材の手配・加工、品質確認、梱包・出荷という共通要素がありますが、進行の順序とタイミングが異なります。
個別生産では、最初に細かな仕様を決め、技術者が一品ずつ設計図を作成してから部材を揃え、加工を進めます。
そのため、同じ材料を使っても、別の注文が入るたびに計画を更新し、柔軟に対応する体制が必要です。
受注生産では、まず受注データを受け取り、需要を予測だけでなく実績と照らし合わせて生産計画を作ります。材料を最適なタイミングで発注し、工場のラインを組み替えたり、部品を同時並行で加工する工夫が重要です。
このような違いは、現場の組織にも反映されます。個別生産は小規模な工房に適しており、職人の技量と柔軟性に依存することが多いのに対し、受注生産は生産ラインと情報システムの連携が鍵となります。品質管理の観点でも、個別生産は品質を一品ごとに確認するのが基本ですが、受注生産では統一された品質基準に基づく検査を速やかに回す仕組みが求められます。
現場の事例と注意点
実際の事例をみると、家具メーカーA社は受注生産を中心に展開しています。在庫を持たず、注文が入るとすぐに木材をカットし、カラーやサイズを顧客の希望通りに仕上げます。納期は注文後2週間程度ですが、天候や原材料の入荷状況で前後することもあります。透明性のある納期表示と迅速な情報共有が重要です。別のケースとして、DIY部品を扱う会社B社は、標準品の在庫を多めに持ちつつ、受注が入ればその在庫を組み合わせて特別仕様品へ展開する方法をとっています。こうした工夫をすることで、在庫の過不足を抑え、顧客の要望に応じた柔軟性を保つことが可能になります。
結論としては、企業は自社の市場と製品特性に合わせて両方式を組み合わせるのが一般的です。需要の変動性が大きい場合は受注生産寄り、差別化が重要で在庫を許容できる場合は個別生産寄り、このような判断をデータと現場の声で支えることが大切です。今後はAIを使った需要予測や、柔軟な生産ラインの構築がさらに重要になります。
ある日、学校の演劇部で新しい小物を作る話。部員は『個別生産』と『受注生産』の違いを友達に説明していた。受注生産は『お客さんの注文が決まってから作る』ということ。最初はよく混同していたが、実際には在庫を抱えず、注文を待つ待ち時間をさばくための工夫が必要という話。デザインの自由度と納期のバランスをとるには、仕様の取り決めが早く正確であることが肝心だ。早くて丁寧な情報共有が、顧客満足につながる。
次の記事: 入庫と入荷の違いを徹底解説|現場で混乱しないための3つのポイント »





















