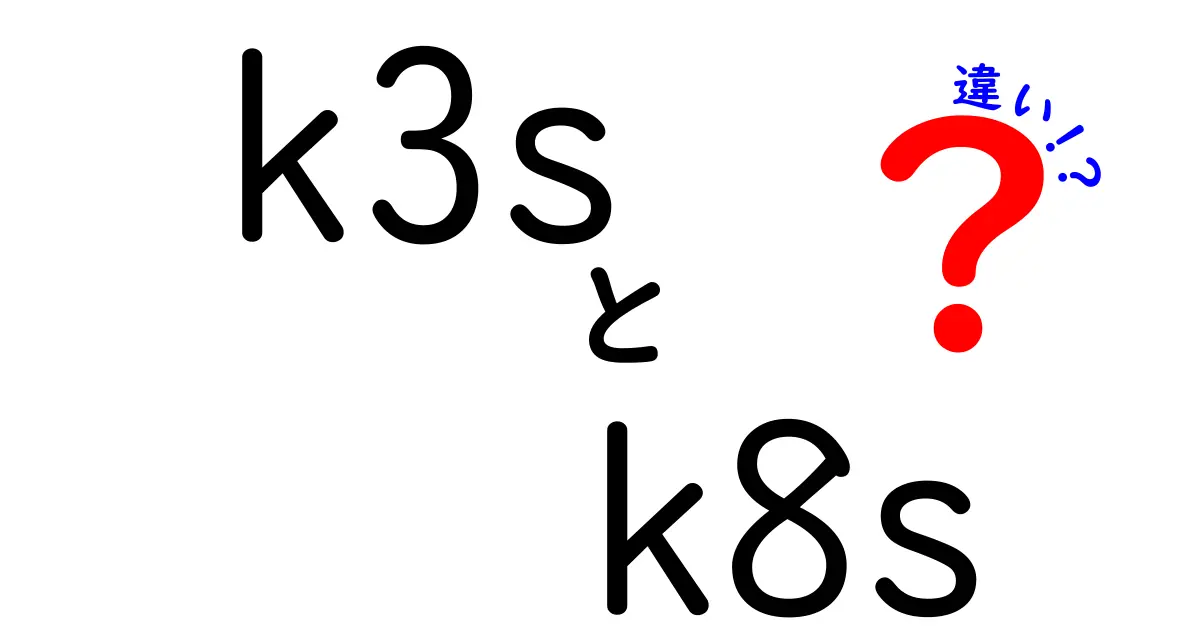

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに k3sとk8sの違いを知ろう
k3sとk8sはどちらも Kubernetes に関係する技術ですが 実際の使われ方や導入の難易度が大きく異なります。Kubernetes 本体は機能が豊富で安定運用を前提とした大規模環境に向いていますが 設定や運用が難しくなることも多いです。これに対して k3s は軽量版として設計されており 学習用や小規模なプロジェクト あるいはエッジデバイスでの利用を想定して作られています。つまり 同じ Kubernetes の世界に属していますが 現場のニーズによって最適解が変わるのです。
この記事では 中学生でも分かる言葉で 両者の基本を整理し どんな場面でどちらを選ぶべきかを具体的に解説します。まずは両者の位置づけをざっくり押さえましょう。
ポイントとなるのは三つの観点です 一つ目は学習コストと導入の手軽さ 二つ目は機能の範囲と拡張性 三つ目はリソースの消費と運用の難易度です。Kubernetes の名前を聞くと難しそうに思えるかもしれませんが 実際にはどの程度の規模で 管理者がどの程度の責任を持つのかで選択肢が変わります。
この三つの観点を軸に これから具体的な特徴と使い分けのコツを紹介します。
k3sの特徴と用途
k3s は軽量版の Kubernetes として設計されています。小さなデバイスやリソースが限られた環境でも動くように 余分な部品を削ぎ落とし 導入のハードルを下げることを第一に考えています。エッジデバイス IoT機器 自宅の開発環境 Raspberry Pi などの低スペックなマシンでの運用が得意です。インストールはワンライナーで終わることが多く 初期設定の手間が少ないのも大きなメリットです。
ただし そうした軽量化の代わりに デフォルトの機能が絞られている場合があり 外部データベースの利用や高度なカスタマイズを望む場合は追加の設定が必要になります。運用面では 学習コストが低い 一方で 大規模な本番運用を直ちに想定するのは難しいことも覚えておきましょう。
k3s の利点をまとめると次の通りです。
・導入の手軽さが高い ・資源の少ない環境で動作 ・開発・学習・試験用途に適している
これらはエッジ環境での動作や教育用のデモ 作業の自動化の学習などに特に向いています。反面 大規模な本番環境や複雑な運用ポリシーを求める場面には向かない場合があります。
k8sの強みと課題
k8s は Kubernetes の正式版で機能が豊富 です。大規模なクラスタ運用を想定し 高い可用性 スケーラビリティ 生産性の高い開発フローを実現します。多様なネットワークストレージプラグイン CI CD ツールとの連携 そしてクラウドとオンプレミスを横断するハイブリッド運用など 可能性が広いのが特徴です。
ただしその分導入と運用は複雑で 学習コストが高いことが多いです。クラスタの設計 セキュリティ設定 アップデート戦略 監視とバックアップの仕組みなど を計画的に整える必要があります。リソース要件も高めで 小規模な環境にはオーバースペックになることがあります。
k8s の強みを活かす場面は 大規模なマイクロサービス運用 ロードバランシングの高度な設定 企業規模のセキュリティ要件を満たす場合などです。活発なコミュニティと公式ドキュメントが充実しており 問題が発生したときの解決策を見つけやすい点も魅力です。
どう選ぶ?用途別の判断ポイント
選択の基本は環境の規模と目的です。小規模で学習や試作 本番環境がまだ安定していない段階なら k3s が現実的な選択肢です。エッジデバイスでの運用 コストを抑えつつ Kubernetes を体験するには理想的です。
一方で 複数のクラウドやオンプレミスを跨ぐ大規模なサービスを安定運用したい場合は k8s を選ぶべきです。運用体制も大事で 監視 バックアップ ロールバックの仕組みを整えておくことが成功の鍵になります。
実際の判断には次のポイントを押さえると良いでしょう。まず環境の資源量と拡張性の要求 次にセキュリティや運用のポリシー そして学習コストと導入の時間感です。これらを整理しておけば どちらを選ぶべきかの結論が見えやすくなります。
最後に移行計画を用意しておくと安心です。小さく始めて徐々に本番環境へ移行するステップが現実的で 混乱を避けられます。
比較表で違いを一目で見る
以下の表は代表的な違いを簡潔に並べたものです 表を見ればどの場面でどちらを選ぶべきかがつかみやすくなります。
この表をヒントに 自分の環境に合った選択をしましょう 重要な点は 規模と運用体制 です。小さく始めて徐々に機能を拡張していくアプローチが安全です。
まとめ
k3s は 軽量で導入が楽 な点が魅力のエッジ寄りの選択肢 一方 k8s は 大規模運用に強い 拡張性と安定性を備えています。自分のプロジェクトの規模資源 学習コストや将来の展望を考え 使い分けることが大切です。
具体的には 小規模な試作や教育用途には k3s 大規模な本番環境には k8s を検討すると良いでしょう。いったん両方の基本を理解しておくと 実務での選択肢が広がります。
先日 学校の発表準備で k3s の話をしていたときのことです 友達が軽量さを強調して すぐ動くのが魅力だと言いました そこで私はこう答えました なるほど 速さだけが魅力ではなく 実際には使う場所が大事なんだと 例えば自宅のラズベリーパイで学習用に回すなら k3s が最適です しかし大規模な社内システムを運用するなら k8s の方が安定性と拡張性を提供します つまり 選択は環境と目的次第なんですね これを知っていると 何を学ぶべきか どう設計を始めるべきか 見通しが立ちやすくなります





















