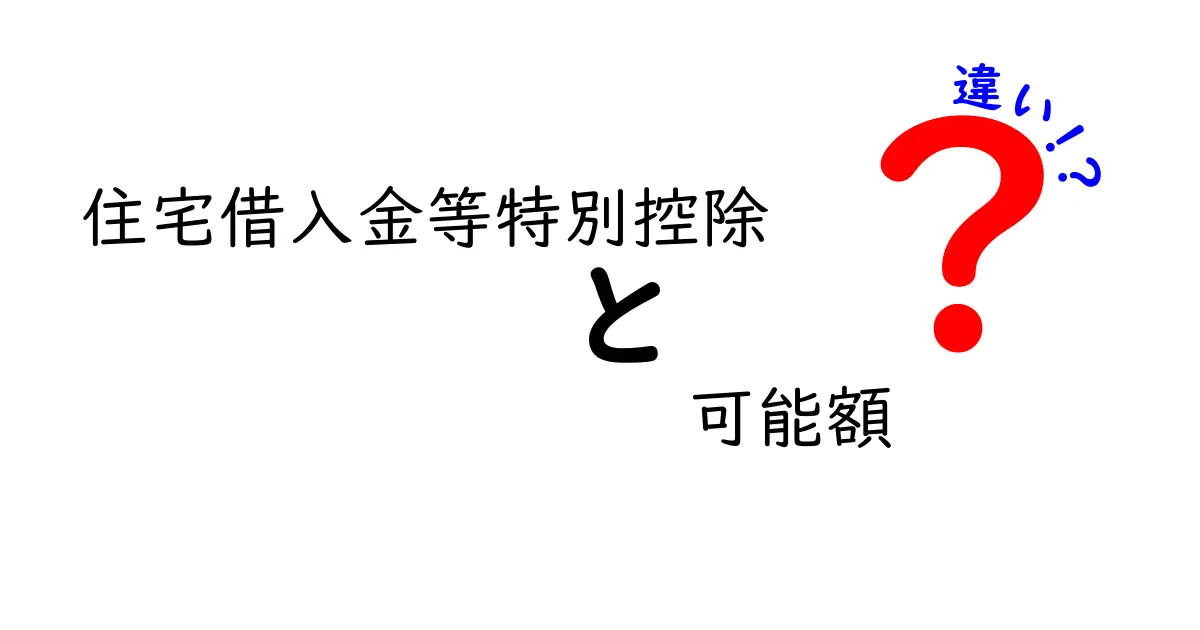

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
住宅借入金等特別控除とは何か?基本から学ぼう
住宅借入金等特別控除は、住宅ローンを組んでマイホームを購入したときに使える税金の控除制度です。
簡単に言うと、毎年の所得税や住民税が減る制度で、家を買う人にとって大きなメリットとなります。
この制度は、ローンの残高に応じて一定の割合で税金が控除されるので、返済の負担を和らげる役割があります。
ただし、条件や控除額の計算方法が複雑で、特に控除できる可能額に違いがあるのがポイントです。
ここからは、住宅借入金等特別控除の可能額の違いについてわかりやすく解説します。
住宅借入金等特別控除の可能額は何によって違うのか?
住宅借入金等特別控除の可能額は、主に以下の3つで違いが出ます。
- 居住開始の年
控除の適用開始年によって控除率や控除期間が変わるため、可能額に差が出ます。 - 住宅の種類(新築・中古や一定の品質基準など)
例えば省エネ性能の高い住宅や一定の性能を満たした住宅は控除額が優遇されます。 - ローン残高の上限
ローン残高に上限があり、その範囲内で控除額が決まります。借入金額が大きくても上限を超える分は控除されません。
これらの条件を踏まえると、同じ住宅ローンを組んでも控除額の可能な範囲が変わってくるのです。
次に具体的な数字や計算例を見てみましょう。
控除可能額の計算例と違いを表で比較してみよう
控除可能額は、一般的に以下の式で計算されます。
控除額=年末の住宅ローン残高 × 控除率(1%が多い)
ただし、控除期間や控除できるローン残高の上限が決まっています。例えば、2023年に居住を開始した場合、控除期間は最長13年、新築住宅ならローン残高の上限は4,000万円といった決まりがあります。
下の表で新築住宅と中古住宅での違いをまとめてみました。
| 住宅の種類 | 控除期間 | ローン残高の上限 | 年間の控除可能額上限 |
|---|---|---|---|
| 新築住宅(省エネ等の優良住宅含む) | 13年 | 4,000万円 | 最大40万円 |
| 中古住宅 | 10年 | 2,000万円 | 最大20万円 |
このように、住宅の種類や適用開始年によって可能額の合計や年ごとの控除額に大きな差が生じる点を押さえておきましょう。
まとめ:活用するためのポイントと注意点
住宅借入金等特別控除は、家を買ってローンを返していく人にとって非常に重要な節税制度です。
しかし控除の可能額は住宅タイプ・ローン額・開始年などで違いがあるため、自分の場合がどれに当てはまるのか正しく理解しましょう。
また、申告には確定申告が必要なケースもあるため、必要な書類や手続きについても事前に確認しておくことがポイントです。
最後に、控除の条件や金額は税制改正で変わることが多いので、最新情報を常にチェックして賢く活用してください。
住宅借入金等特別控除の可能額がなぜ違うかというと、居住開始の年ごとに税制が変わっているからなんです。\n\n例えば、2022年にマイホームを買った人と2024年に買った人では、控除される金額や期間のルールが異なります。\n\nこの違いは、一見わかりづらいですが、実は国が住宅ローン支援のために毎年見直しをしていて、それによって細かく変更されているんですよ。\n\nだから、控除額を最大化したいなら、その年のルールをしっかりチェックすることが大切です!
前の記事: « 生活保護と生活保障の違いとは?わかりやすく解説!





















