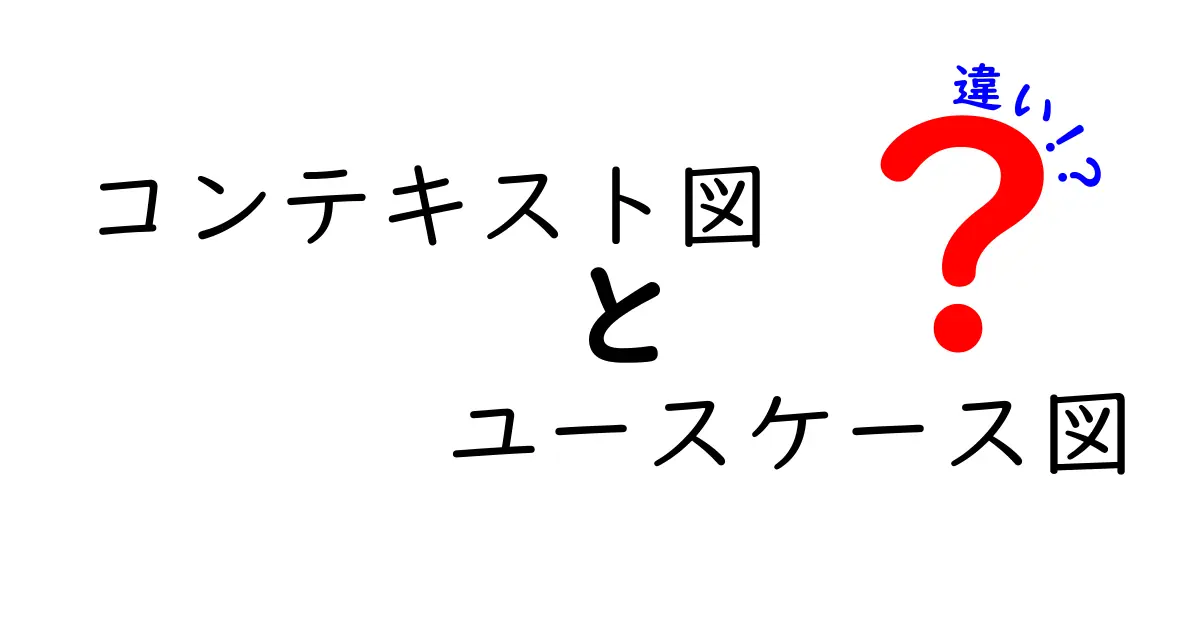

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:コンテキスト図とユースケース図の基本を知ろう
この章ではコンテキスト図とユースケース図がそれぞれ何を表すのかを、日常の身近な例を使ってやさしく解説します。
まず、コンテキスト図はシステムの“境界”と“外部の関係者”を一望できる絵です。たとえば学校の図書館システムを例に取ると、司書さん、学生、学校のネットワーク、図書館の外部の業者などがシステムの周りを取り囲む形で描かれます。これにより、どんな外の人や組織とつながっているのか、どこに情報が出入りするのかが一目で分かります。
一方、ユースケース図は「システムが提供する機能」と、それを使う人(アクター)とのやり取りを中心に描きます。ここでは“何ができるのか”という機能の粒度と、誰がその機能を使うのかが重要になるのです。
この二つは似ているようで役割が違います。前者は“範囲と外部関係”を把握する地図、後者は“機能と利用者の関係”を整理する設計図と考えると分かりやすいです。
この入り口をしっかり押さえると、要件定義の初期段階での誤解を減らせ、後の設計フェーズがぐんと楽になります。以降の章では、それぞれの特徴・違い・使い分けのコツを具体的な例とともに詳しく見ていきます。
コンテキスト図とユースケース図の違いを詳しく見る
結論から言うと、コンテキスト図は“システムの全体像と外部の接点”を示すのに対し、ユースケース図は“システムが提供する機能と利用者の関係”を示します。
ここでのポイントは抽象度と焦点の違いです。
具体例を使って確認しましょう。銀行のオンラインサービスを例にすると、
・コンテキスト図では外部の顧客、他の金融機関、決済ゲートウェイなどが自社システムの周囲に配置され、どんな情報がどこへ行くのかが見えます。
・ユースケース図では「口座開設」「振込」「残高照会」といった機能と、それを使うアクターが矢印で結ばれます。これにより、誰が何をできるのか、機能間の関係性が明確になります。
この違いを意識することで、要件の誤解を避け、会議の時間を短くする効果も高まります。
表現のスタイルと現場での使い分け
まずは表現のスタイルを理解しましょう。
コンテキスト図は全体像を示すため、境界線を太く描くことが多く、外部の要素を円や四角で表してシンプルに描くことが一般的です。
これに対して、ユースケース図は機能を集合的に並べ、アクターと機能を結ぶ矢印の流れで関係を説明します。
現場での使い分けのコツとしては、(1)要件の初期検討にはコンテキスト図、(2)機能の整理と振る舞いの検証にはユースケース図、という順序を意識すると効率が上がります。
また、両方を並べて比較できるように、最初にコンテキスト図を描き、それを基にユースケース図へと落とし込む方法が現実的です。
この表を参考にして、会議の初期段階で両方の図を使い分けると、関係者全員が同じイメージを共有しやすくなります。
さらに注意したいのは表現の過度な細分化を避け、実際の業務で役立つ情報を絞って描くことです。
図は“伝えるための道具”なので、分かりやすさを最優先に考えましょう。
最終的に、コンテキスト図とユースケース図をセットで用意することで、要件の抜け漏れを防ぎ、設計の土台を安定させることができます。
ユースケース図って、なんとなく難しそうに見えるけど、実は日常の会話の延長線上にある話題だよ。たとえばゲームを作るとき、プレイヤーがどんな操作をするか、どの機能が反応するかを整理するのがユースケース図。僕たちが友達と新しいアプリの話をするとき、"ログインする機能とパスワードを入力する画面がどうつながるか"を頭の中で整理するのと同じ作業なんだ。最初はシンプルに、主要な機能と主な利用者だけを描いてみて、後から必要に応じて細かい機能を追加していくとよいよ。こうした思考の癖をつけると、プロジェクトがどんな小さな変更にも強くなるんだ。





















