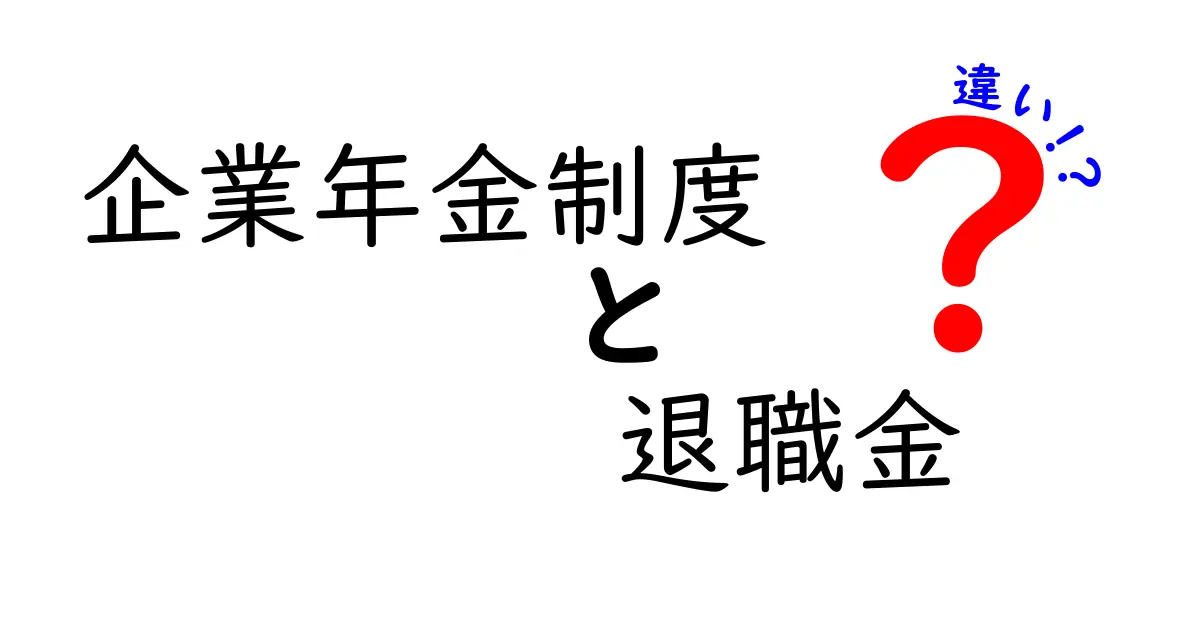

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
本記事の目的と概要
このページでは、企業年金制度と退職金の違いを、中学生にもわかるように丁寧に解説します。企業で働くとともらえるお金にはいくつかの種類があり、それぞれ受け取る時期や条件、税金の扱いが異なります。ここでは「企業年金制度」と「退職金」という2つの仕組みを中心に、日常生活や将来の資金設計にどう影響するかを、やさしい言葉と具体的な例を交えて説明します。さらに、実務での選択ポイントや注意点も紹介します。
定義と基本的なしくみ
まず、「企業年金制度」と「退職金」の意味を整理しましょう。企業年金制度は、会社が従業員の老後のために積み立てたり、給付を設計したりする制度です。代表的なタイプには、将来の給付額が確定している確定給付型(DB)と、毎年の掛金が決まっており将来受け取る額が変わる確定拠出型(DC)などがあります。一方、退職金は退職時に一度だけ受け取る現金のことを指し、会社の規模や業績、在籍年数によって金額が決まります。退職金は過去の勤務に対する「謝意の形」として支払われる意味合いが強く、分割して受け取るケースもあります。
この2つの違いを理解するには、受け取り方が「分割されるか」「一括で支給されるか」そして「税金の扱いがどうなるか」を押さえると理解しやすいです。企業年金は積み立ての拠出額や利息・運用成績に応じて金額が変わる場合があるため、将来の見通しを立てやすい反面、給付の安定性は制度設計に大きく左右されます。退職金は総額が大まかに決まっていることが多く、受け取り方次第では手取りの金額が大きく変わることがあります。
受取時期と受け取り方の違い
企業年金は在職中に積み立てが進み、退職後に年金として受け取ることが多いです。場合によっては分割して月々受け取る「年金払い」が選択され、一定の期間または終身で支給されます。退職金は退職直後に一括で受け取るケースが多いですが、会社の制度次第で分割払いを選べる場合もあります。つまり、企業年金は「長く受け取り続ける設計」で、退職金は「一時的な大きな現金受取り」という性質が強いのです。
また、年金として受け取る場合は、就業期間や拠出額、運用結果が将来の月額に影響します。退職金は在籍年数や役職、退職理由などが大きく影響します。この違いを理解しておくと、老後の現金の流れを先に描くことができます。
税金と社会保険の取り扱い
税金の扱いは制度ごとに異なります。退職金は「退職所得控除」という特別な控除が適用され、税金の負担が比較的軽くなる場合が多いですが、受け取り方によっては課税額が変わります。企業年金の給付は「公的年金等控除」や「雑所得・給与所得・公的年金等控除」など、所得の区分に応じて課税され方が変わります。実務的には、退職金を一括で受け取ると多段階の控除が適用され、税負担が軽くなるケースが多いです。一方で企業年金の月額受取は毎年の所得として扱われ、税率が変動することがあります。
社会保険の扱いは、給与所得扱いか年金所得扱いかで変わることがあります。就労中の積立金は“給与の一部”として扱われる場合が多く、退職後の給付は年金所得や雑所得として扱われる仕組みが一般的です。
実務での選択ポイントと比較表
実務では、企業年金と退職金の両方を組み合わせて設計する企業が多いです。ここでのポイントは、将来の生活設計とリスクの分散をどう図るかです。以下のポイントを押さえると、個人の資金計画が立てやすくなります。
- 自分の勤務年数と将来の退職時期を予測する
- 年金の支給開始年齢や受取額の見通しを確認する
- 税制上の控除や所得区分を理解する
- 企業の財務状況と制度の安定性を考慮する
- ライフイベント(住宅、教育、医療)の資金需要と照合する
表を使って簡易比較をしておくと、イメージがつかみやすくなります。以下は、代表的な違いを整理した簡易表です。
このように、目的に応じて組み合わせを考えることが重要です。詳しい金額は自身の勤務先の人事部門や財務部門に相談し、試算ツールを使って確認すると良いでしょう。
まとめ
企業年金制度と退職金は、名前は似ていますが「受け取り方」「税金の扱い」「将来の計画への影響」が大きく異なります。退職金は一時金としての性質が強く、受取時の税制の恩恵を受けやすいことが多い一方、企業年金は長期にわたって安定した収入を生み出す仕組みで、老後の生活設計を支える重要な柱となります。自分のキャリアや家族の状況に合わせて、どの程度を退職金として受け取り、どの程度を年金として受け取るかを、時間をかけて検討しましょう。
放課後、友達のアオイとケンが学校のカフェテリアで将来のお金の話をしています。アオイは退職金が一度きりの大金だと思っていて、ずっと貯金しておけば大丈夫だと考えていました。しかし、ケンは「企業年金制度」という長く続く収入の仕組みがあることを伝えます。退職後も定期的にお金が入ってくるのと、退職時に一括で多額を受け取るのでは、生活の安定感が全く違います。2人は、税金の取り扱いがどう変わるのか、長い目で見た資金設計の大切さについて語り合います。結論はシンプルで、「いくつかの仕組みを組み合わせて使うと、リスクを分散しやすい」ということです。話が進むにつれて、2人の頭の中には、将来の自分たちの生活を想像する地図が描かれていきます。





















