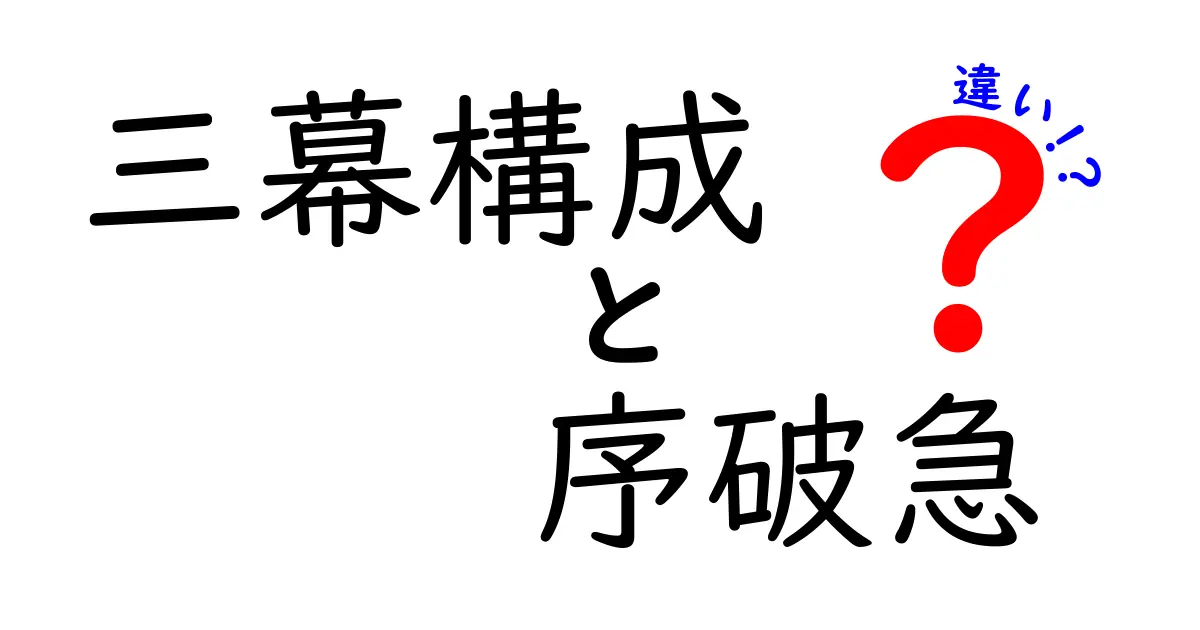

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
三幕構成とは何か、そして序破急の位置づけ
三幕構成は、物語を三つの大きな部分に分けて進める考え方です。映画や舞台、漫画のストーリーづくりの基礎として長く使われてきました。まずは導入、登場人物、世界観を丁寧に紹介して読者が作品の世界に入りやすくします。これを「序」と呼びます。次に起こる出来事が物語を動かしていく部分、つまり対立や困難が生まれる展開の段取りが「破」です。最後に対立を解決し、物語全体の結末に向かって収束させるのが「急」です。序破急を正しく配分することで、読み手や観客の感情を段階的に高めることができます。
この考え方は、初心者にも取り組みやすいので、物語を作るときに最初に頭に入れておくと便利です。
以下では、序・破・急のそれぞれの役割を実例とともに詳しく見ていき、どう違いを生かせば自然で引きつける物語になるのかを解説します。
ポイントとして、導入の時間を短くしすぎないこと、展開では新鮮な緊張感を作り出すこと、クライマックスは過剰にならないように終結へ向けてのよじれを用意することが大切です。
序・破・急の違いを具体に解説
この節ではまず序の役割を詳しく確認します。序は物語の地図を描き、登場人物の関係性や世界観のルールを読者に伝えます。ここがしっかりしていないと、後で起こる出来事を理解できず、読者は混乱してしまいます。次に破の役割です。破は対立や葛藤を広げ、物語に緊張感を生み出します。新しい情報が次々と出てくると、読者は「次はどうなるのか」と先を読みたくなるのです。最後に急。急は対立のクライマックスと結末へ向かう部分で、感情の高まりを最大化して読み手に満足感を与えます。
この三つの段階をどう組み合わせるかが、作品のリズムと波の作り方を決めます。序で静かな入口を作り、破で緊張を上げ、急で余韻と解決を迎える――この順番が、物語を自然に美しく動かすコツです。
読み手が共感しやすいのは、登場人物のとる行動が「序→破→急」の順序で納得できるときです。頻繁に新情報を出しすぎず、ポイントだけを順番に出すと理解が深まります。
使い方のコツと例
三幕構成を実際の作品づくりに活かすコツをいくつか紹介します。まずは全体像の設計。物語を紙の上で三つのブロックに区切り、各ブロックの目的を決めます。次に序の長さを調整。導入は読者の興味を引くために丁寧に。時間をかけすぎず、要点を絞るのがコツです。破では葛藤の広げ方を工夫します。新しい情報を少しずつ出すことで、読者の謎解き欲を刺激します。急では結末の余韻を残すための一手を用意します。ここで、以下の表を参考に、三幕の役割と感情の動きを整理すると分かりやすくなります。要素 序 破 急 役割 導入・設定 対立・展開 解決・結末 感情の動き 穏やか・期待 緊張・驚き 満足・解放 長さの目安 全体の20-35% 全体の40-60% 全体の20-30%
最後に、実際の例として「学校の文化祭での短い劇」を設定してみましょう。序は登校前の準備と台本の読み合わせ、登場人物の関係性の説明。破では予期せぬトラブルや演出の変更が入り、観客の緊張感が高まります。急ではトラブルの解決とキャストの成長、そして観客への感謝のメッセージで終わります。この流れを守るだけで、短い話でも「起承転結」がはっきりした物語に仕上がりやすくなります。
総括として、序破急は難しいテクニックではなく、物語の流れを自然にするための道具です。使い方を覚え、実際の作品づくりで試してみると、読者や観客に伝わりやすいストーリーが作れるようになります。
ねえ、三幕構成の序破急って、なんとなく難しそうに感じることがあるよね。私たちが日常で感じる“おはなしのリズム”を思い出してみて。序は導入の雰囲気づくり、破は起こるトラブルの展開、急はそのトラブルの解決と結末へ向かう瞬間のドラマ。友だちと話しているとき、会話の導入と話の展開、そして最後のオチが自然につながると楽しくなるでしょ。それと同じで、物語も三つの段階を丁寧に組み合わせると、読んでいる人が自然と引き込まれるんだ。私が最近考えた小さな物語のコツは、序で登場人物の信頼関係を示し、破で小さな対立を作って、急で結末をしっかり見せること。これだけで、長い話じゃなくても十分にドラマ性が出せるんだよ。





















