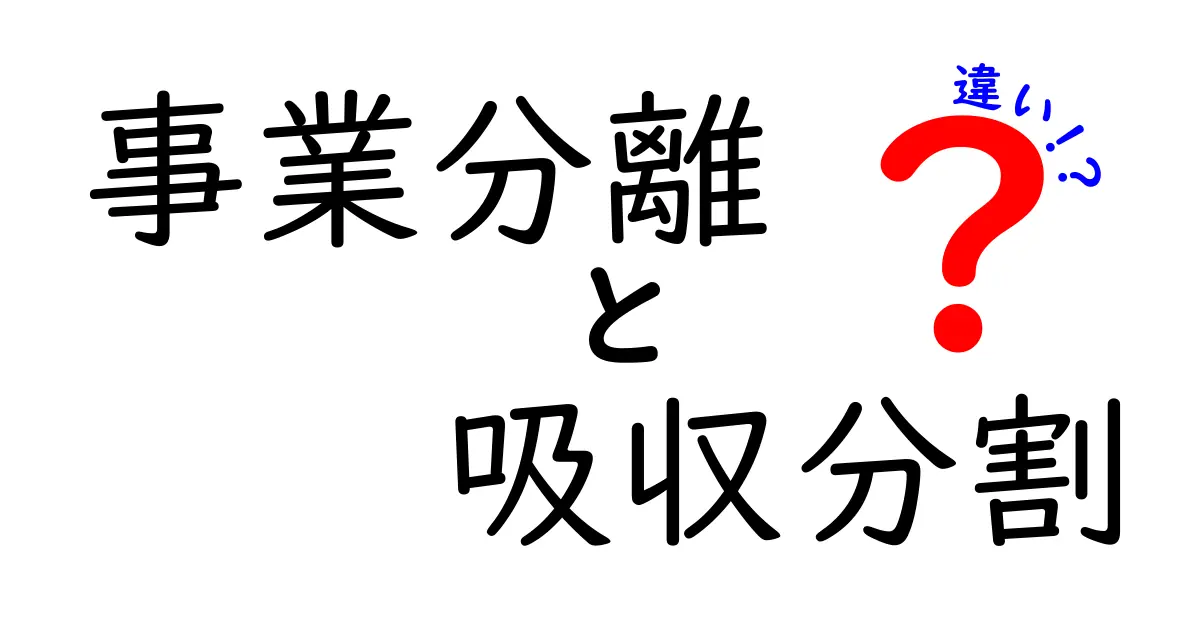

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
事業分離と吸収分割の違いを徹底解説:基礎から実務まで
事業分離とは、ある企業が自社の中の一部の事業を切り出し、別の会社へ移す手続きのことを指します。つまり分けて新しい会社に任せるイメージです。これに対して、吸収分割とは、ある会社が自社の事業を別の既存の会社に引き継がせる手続きで、受け手の会社が事業を吸収する形になります。法的な性質が異なる点が大きな違いです。事業分離は新設するかどうかを含む選択で、事例として新設分離と吸収分離のいずれかに分かれるケースがあります。一方、吸収分割は既存の会社間での資産と事業の移転に近く、契約関係の引継ぎや従業員の雇用条件の取り扱いが実務上の大きなポイントになります。これらを整理すると社内の意思決定が分かりやすくなります。なお承認手続きとして株主総会の承認や監督機関の認可が必要になる場合が多く、事前分析と計画が欠かせません。ここから実務のポイントを具体例とともに整理します。
事業分離のイメージとしては、組織の再編で新設の会社を作って分離した部門だけを移す形です。資産と負債の範囲を明確にし、顧客情報や知的財産の扱いをどうするかを決めます。従業員の雇用継続についても扱いが分かれます。吸収分割は受け皿となる既存会社がすでにある場合に選択されることが多く、移転の際の契約調整や税務の取り扱いが中心課題になります。いずれの場合も文書化と周到な計画が大切であり、突然の実施は混乱を招きやすいです。次の節では実務上の比較と実務上の注意点を表にまとめて紹介します。
事業分離のイメージとしては、組織の再編で新設の会社を作って分離した部門だけを移す形です。資産と負債の範囲を明確にし、顧客情報や知的財産の扱いをどうするかを決めます。従業員の雇用継続についても扱いが分かれます。吸収分割は受け皿となる既存会社がすでにある場合に選択されることが多く、移転の際の契約調整や税務の取り扱いが中心課題になります。いずれの場合も文書化と周到な計画が大切であり、突然の実施は混乱を招きやすいです。次の節では実務上の比較と実務上の注意点を表にまとめて紹介します。
実務での選択ポイントとよくある誤解を解く
実務での判断ポイントは、まず新設か既存かを決めることです。新設事業分離は新設会社を作るため株主の承認資本金の設定ガバナンス設計などが新たに必要になります。対して吸収分割は既存会社間の統合性が強く契約関係の調整と税務処理を慎重に行います。
従業員の扱いも大きな点です。雇用契約の承継が行われるケースと転籍の扱いが必要になるケースがあり、従業員の生活にも影響します。税務面の取り扱いは資産評価やのれんの扱い、減価償却の継続性、譲渡所得の課税など専門的な知識を要します。実務では事前に複数のシナリオを用意して影響を比較し最適な手法を選ぶのが一般的です。次に比較表と注意点を整理しますので読みやすいように紹介します。
まとめとして、事業分離と吸収分割は目的と状況に応じて使い分けるべき手法です。法務税務人事の専門家と協力して計画を立てることが成功の鍵です。ニュースや資料を読むときには、両者の違いを頭の中で整理する癖をつけましょう。
吸収分割は難しく感じる名前だけど、実は身近な発想の話だよ。友だちのグループ分けに例えると、ある班がそのまま別の班に機械や資料を渡して運営を続ける感じ。最初は混乱しやすいけれど、事前に役割と責任を共有するとスムーズになる。この記事の実務セクションで触れたように、契約の継続性や従業員の扱い、財産の評価をどうするかを決めることが要のポイント。小さな疑問を一つずつ解いていくと、分割の世界が見えやすくなるよ。
前の記事: « 事業分離と事業譲渡の違いを徹底解説|中学生にも分かる図解付き





















