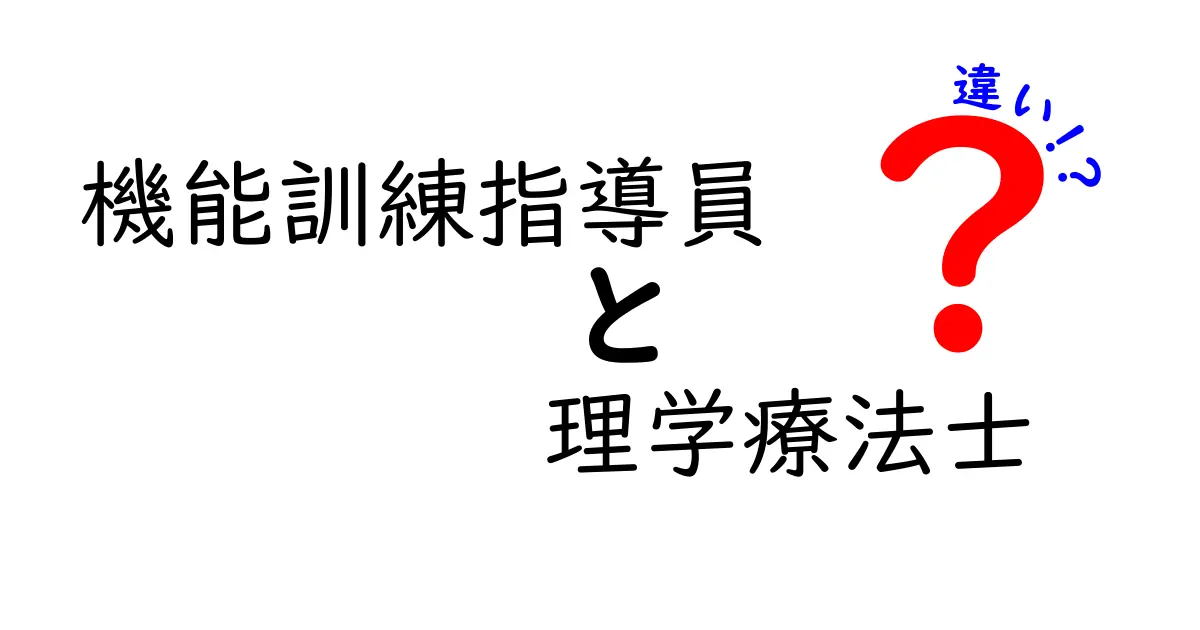

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
機能訓練指導員と理学療法士の基本的な役割を比較
機能訓練指導員は主に介護施設やデイサービスなどの現場で、利用者の生活動作の改善を目指して個別訓練の計画と実施を担当します。資格要件は講習を修了することが基本で、介護の現場に近い形で運動療法を日常生活へ落とし込む役割です。彼らは運動の強度や頻度を現場の状況に合わせて調整しますが、医療的な評価や診断は行いません。その代わり、利用者の動作を観察して、転倒予防や日常動作の改善につながるトレーニングを提案します。現場の雰囲気や利用者の体力の変化を把握する能力が重要で、安全と継続性を最優先にします。
一方で理学療法士は医療系の国家資格を持つ専門家として、医師の診断に基づくリハビリテーションの中心的役割を担います。対象は怪我から慢性疾患、神経系の障害まで幅広く、痛みの評価、機能の評価、治療計画の作成と実施、経過観察までを行います。診療の場だけでなく在宅リハビリでも活躍し、エビデンスに基づく手技や運動療法を用いて機能の改善を目指します。経験豊富な理学療法士は、時に複雑な症状を持つ人の問題を解く「医療のキーストーン」としての役割を果たします。
この二つの職種の違いを一言で言うと、現場の生活動作を直接改善するのが機能訓練指導員、医療的評価と総合的な治療計画を作るのが理学療法士というイメージです。ただし現場によっては連携が欠かせず、デイサービスでも理学療法士が常駐するケース、病院やクリニックでも機能訓練指導員が補助的な役割を担うケースなど、組織の方針によって役割が重なることもあります。
現場での違いが生まれる場面と選び方のコツ
現場での違いが最も現れやすいのは「評価の深さ」と「治療の範囲」です。機能訓練指導員は日常生活動作の改善に重点を置き、訓練のプランニングとモニタリングを中心に活動します。対して理学療法士は医師の診断に基づく評価を行い、痛みの原因分析や具体的な治療法を提案します。
また対象者の設定が異なることも多いです。高齢者の転倒予防や日常動作の安定化を目指すデイサービスの現場では機能訓練指導員の関与が多く、病院のリハビリや在宅での長期治療では理学療法士が主導します。連携のポイントはチームとして情報共有を密に行い、利用者の安全を最優先にすることです。
下の表は代表的な違いを分かりやすくまとめたものです。現場で迷ったときの判断材料として役立ててください。
なお、どちらの職種も利用者の生活の質の向上を第一に考える点は共通しています。
ねえ、理学療法士って痛みの原因を探して体の動きを整えるプロだよね。ある日、祖母が階段を昇るときに膝が痛いと言っていたので病院へ連れて行った。診察のあと、理学療法士の先生が痛みの原因を丁寧に説明してくれて、どう動けば楽になるかを具体的に教えてくれた。彼らは機械的に治すのではなく、日常の動作の中で体の使い方を少しずつ変えることを重ねていく。だから私たちはリハビリを習慣にして、階段の昇り降りを普通にできる日を目指す。理学療法士の仕事は、技術と観察力、それと患者さんへの共感の三つが合わさって成立しているんだと強く感じた。





















