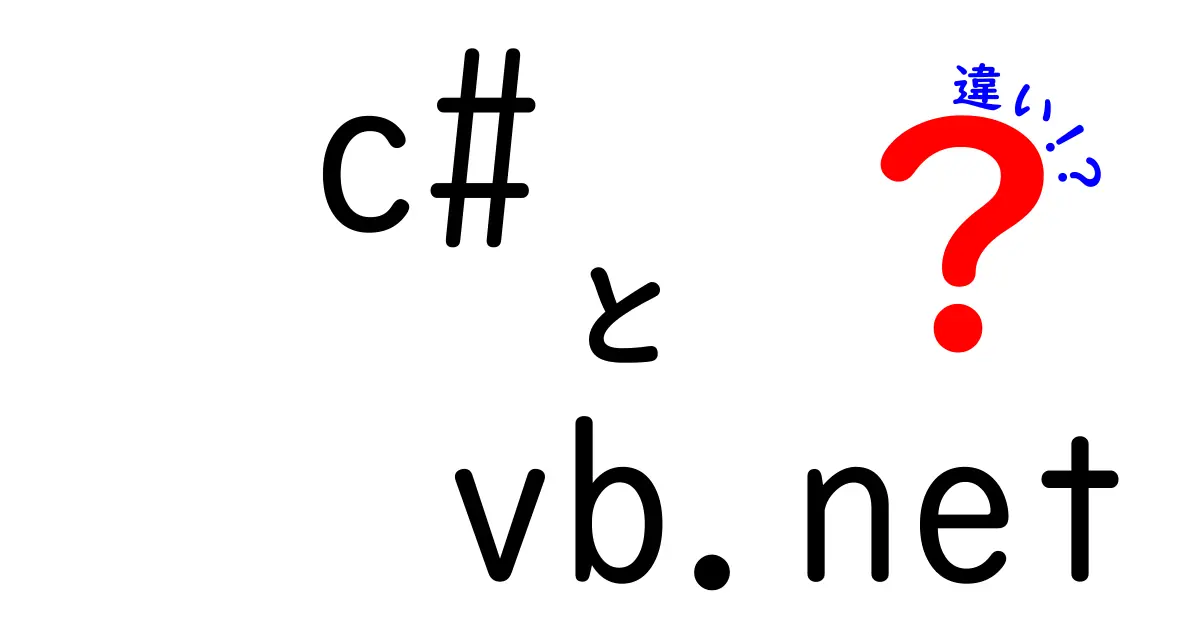

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
構文・記法の違いを軸に見る
C#とVB.NETはどちらも .NET 環境で動くプログラミング言語ですが、見た目の構造や書き方には大きな違いがあります。主な違いの一つはキーワードと記法の形式です。C#は英語風のキーワードと中括弧を使い、VB.NETは日本語にも近いキーワードと End If や Then などのブロック構文を使います。これにより、同じ処理でもコードの読みやすさや書き方が変わります。
また、読みやすさは人によって違います。プログラミング初心者の中学生でも、VB.NETの長い単語と自然な英語風ではなく日本語的な要素を含む構文に慣れると取っつきやすいと感じる場合があります。一方で、C#は現場での標準として広く使われ、コード規約が明確で短い文にまとまりやすいという利点があります。
もう一つの大きな違いは型推論や変数宣言の仕方です。C#では型を明示する場合が多く、varを使って型推論を行う場面もありますが、読み手にとっては型を意識しやすい構文です。VB.NETでは Dim という宣言を使い、Option Infer On のときに限り型推論が働き、初心者にも「何が入るのか」が分かりやすい場面が多いです。
この点は、開発チームの方針や教育方針にも影響します。強い型チェックを好む人は C#、直感的な表現を重視する人は VB.NET を選ぶケースが多いです。
実務での選択のコツと具体例
実務での選択のコツとして、以下の視点を整理します。
まずは「既存コードベースの影響」が最重要です。多くの企業では過去からの資産を守るため、現行の VB.NET や C# を急には変えません。次に「採用市場とチームのスキル」も大きな要因です。C# の方が求人が多く、学習資源も豊富です。
また「エコシステムの整備」も無視できません。ASP.NET、Blazor、Xamarin、.NET MAUI など、最新の技術スタックが C# での実装を前提に動くことが多いです。VB.NET でも対応は可能ですが、サポートの頻度や新機能の取り込みが C# に比べて遅れることがあります。
実務での判断のコツとしては、小規模なプロトタイプを作ってみること、チーム内でペアプログラミングを実施すること、そして 規約の厳格化とテストの自動化を組み合わせることが有効です。これにより学習コストを抑えつつ、実際の効果を測定できます。最後に、プロジェクトの将来性を見据え、長期的には C# を標準として採用するケースが増える傾向にありますが、既存の投資を守るため VB.NET を選ぶ選択肢も残っています。
結局のところ、現場の要件と人材の現状に最も適した言語を選ぶことが大切です。
このような比較を踏まえ、初めて学ぶ人は自分の感覚で読みやすい方を選ぶのが良いでしょう。
ただし、就職市場やプロジェクトの方針を視野に入れると、C#の需要が高い現場が多い点を無視できません。特に新しい技術やクラウド関連の開発を目指すなら、まずは C#を習得する選択も有力です。
はじめのうちは、ByValとByRefの違いを実感できるサンプルを作るのがいいですね。私が友達と話して気づいたのは、C#では渡し方を明示するのが普通で、ByValの挙動を意識しなくても済む場面が多いということ。VB.NETではデフォルトの渡し方やオプション設定によって挙動が変わることがあり、思わぬバグの原因になることも。だからこそ、関数の宣言時にどう値を受け取り、どう返すかを丁寧に考える癖をつけると、コードの品質がぐんと上がります。結局、ILに落ち着くと同じ動きをするので、理解の核は「渡し方の意図を明確に書くこと」と「どの言語でも同じ論理を適用する力」ここに集約されます。小さな実験を繰り返して感覚をつかむのが、成長への近道です。





















